講談社現代新書作品一覧

スポ-ツ名勝負物語
講談社現代新書
奇跡のプレー!感動の瞬間!
野茂英雄、伊達公子、古賀稔彦、勇利アルバチャコフ、松井秀喜、神戸製鋼、日本サッカー五輪代表……。
優勝を賭けた一投一打、奇跡のゴール、回生のトライ、チャンピオンを射止めたパンチ――野茂、松井、伊達、古賀、勇利、イチローなど名選手たちの、勝負を分けた至高の瞬間を活写する。
[主砲の責任]――私の脳裡に、ひとつの風景が甦った。この試合からちょうど1年前の日本シリーズ。ヤクルト対オリックスの第1戦。ブロス――古田のスワローズバッテリーは、イチローに対し、徹底した内角攻めを行い、彼の“振り子打法”を崩してしまった。負けず嫌いのイチローは力で牛耳られたことが悔しくて仕方ない。これを機にアウトコースを捨て、インサイドのストレート1本に狙いをしぼった。力での復讐を試みたのである。そして最終戦、ついにリベンジを果たす。ブロスのインハイのストレートを右中間スタンドに狙い打ったのだ。負けっぱなしに終わらなかったところにイチローの非凡さがうかがえた。しかし、イチローはシリーズを通して活躍することができなかった。当然だろう。復讐したい一心でゲームに臨んでいるわけだから、おこぼれのようなヒットなど欲しくもない。まったく同じことが松井にも言えた。――本書より

小説・倫理学講義
講談社現代新書
不倫は許されるか?民主主義は正しいか?プラトン、カント、ニーチェなど古今の思想から今日的テーマに斬り込む超小説!
長嶋教授失踪!?事件を巡って巻き起こる議論の嵐。不倫とは、嘘とは、民主主義とは?プラトン、ニーチェなど古今の思想を手がかりに倫理学の今日的課題を問う。
[不倫は道徳的に許されないか]――「きっとその倫理学者は考えたのね、不倫はなぜ道徳的に許されないのか、と」「それは愚問だ。道徳に反することを不倫というのだから、『不倫は道徳的に許されない』というのは、トートロジーでしかない。むしろこう問うべきなのだ。独身女性と妻子持ちとの恋愛はなぜ不倫にあたるのか、と」「倫理学者は、結局その難問を解くことができなかった」「いや、そうではない。答えは簡単だ。そうゆうことが不倫にあたらないということになると、結婚制度は意味を失って、結婚制度を土台にして築かれたこの社会は、秩序を維持できなくなり、やがて崩壊の危機にさらされることになる。道徳は神がつくったものではない。共同体が自己を維持するためにつくりあげたものだ。だから道徳は、独身女性と妻子持ちとの恋愛を禁じるのだ」――本書より

開かれた鎖国
講談社現代新書
唯一の国際港・長崎の知られざる事件と意外な日常とは?巧妙な物流・情報システムを詳細に分析し、鎖国観を根本から問い直す。
[唯一の海外交流の舞台]――大航海の波に乗って現われた南蛮人は異質のヨーロッパ文化を運んで来た。鎖国下、日蘭交流の時代を通じても、その流入は変わることはなかった。もたらす担い手が替わり、質的変化をみただけである。……長崎出島は鎖国・禁教下の日本における、まさに唯一の恒常的海外交流の舞台であった……。毎年、来航する入り船は、海外・世界からの人・物・情報を運んできたのである。……バタビアへ向けて帰る、毎年の出船は、鎖国日本を海外・世界に報らせる物を積み、人を乗せ、情報を運んでいったのである。――本書より

パソコン翻訳の世界
講談社現代新書
人類の夢、自動翻訳が実用レベルに達してきた。翻訳ソフトの選び方と使い方、周辺ソフト紹介から機械翻訳の歴史まで、第一人者が懇切に説く。
ブリッジ翻訳で世界の情報を読む――インターネットの情報は英語だけではありません。フランス、ドイツ、スペインなど、かつてイギリスのほかにも世界中に植民地を広げた国の言葉による情報がたくさんあります。……こうした言語を英語に翻訳するソフトは欧米で開発された実用性の高いものがいくつも商品化されています。しかもこうした英語と欧州語間の翻訳は同じ言語グループ同士の翻訳なので、正解率が8割をゆうに超え9割に迫るものもあります。欧州語からの英語訳が機械翻訳で簡単に手に入れば、この英語訳をさらに英日翻訳システムで翻訳することによって、こうした言語を使う世界中の文化圏の情報を即座に日本語で読むことができるのです。――本書より
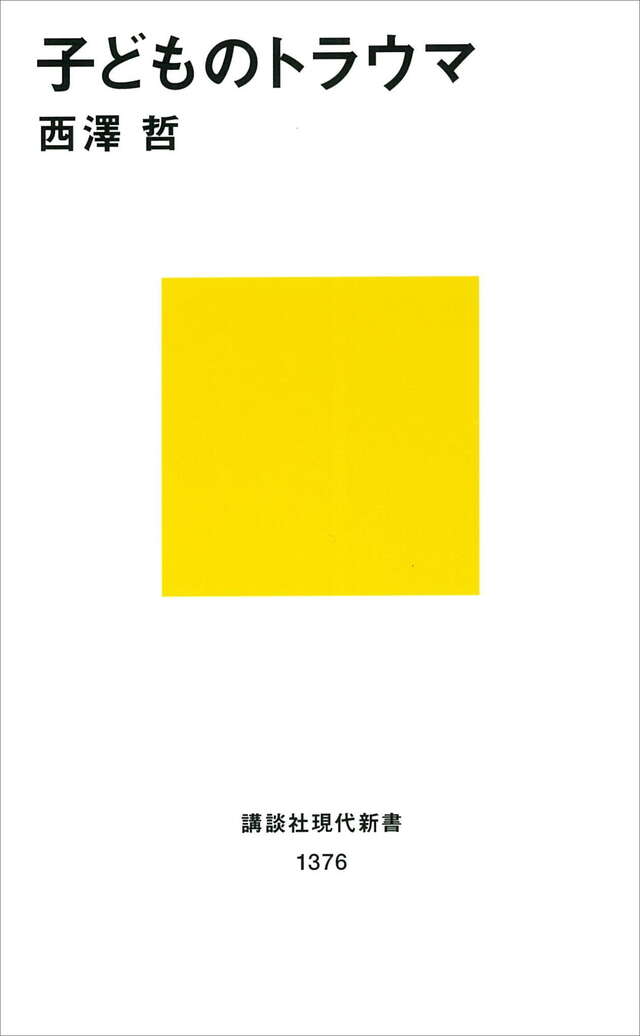
子どものトラウマ
講談社現代新書
身体の傷は治っても心の傷は消えない。人格を、ときには人生さえ支配してしまうトラウマとは何か。第一線での臨床活動をふまえて「子どもの虐待」の問題をとらえなおし、傷ついた子と親の心の回復を説く。(講談社現代新書)
トラウマの視点から親子の関係を問い直す。なぜ子どもを傷つけてしまうのか。傷ついた心はどのように癒されるのか。現場の体験を通して子ども虐待の深層をえぐり、子と親の心の再生と回復の道を語る。

日本の安全保障
講談社現代新書
「周辺有事」とは何か。ガイドライン見直しの核心とは?アジア諸国の軍拡、沖縄の米軍基地問題、シーレーンの危機――冷戦後の新しい視点からリアルに論じつくす必読書!
イギリス軍を上回った自衛隊の軍事力――日本は日米防衛協力のための指針を見直してもなお、基本的には専守防衛であり、アジア・太平洋地域の平和と安定に対しては、間接的な貢献に止め、あくまでも盾としての役割に固執する方針を採っている。……それは、確かにアジア・太平洋地域においては、日本の軍事力に自分で足かせをかけるものとして、ほかの国からは歓迎されるものと言うこともできよう。日本人の多くは気づいていないが、すでに日本の自衛隊は世界でも有数の「軍事力」となっている。……ドル換算による防衛費は、明らかに米国に次ぐ世界第2位である。兵員の数は総兵力でイギリスを上回り、装備もほとんどの分野で英軍を上回っている。――本書より

白村江
講談社現代新書
海水みな赤し――唐・新羅連合軍の前に倭国の百済救援作戦は打ち砕かれた。日本の国家形成途上に起こった壮大なパワーゲームを検証し、古代史の通税を覆す力作。
2日間の戦闘を読み解く――倭国水軍はこの日、再度唐軍に攻撃を敢行した。しかし、この日の総攻撃に入るまでには、前夜、倭国水軍のなかで意見の分裂と対立があった。そのため、倭国水軍の攻撃は全体的な統制の採れていない、極めてちぐはぐなものであった。……唐船は倭船のなかに火矢を射込んだ。倭兵は懸命に消化につとめたが、間に合わなかった。多くの倭船が炎につつまれ、倭兵は放り出されるようにして錦江に飛び込んでいった。船より落ちた者は唐兵の放つ矢の恰好の標的となるか、あるいは溺れ死ぬしかなかった。たちまちのうちに、錦江河口の海水が倭兵の流す血に染まっていった。――本書より

ファッションの技法
講談社現代新書
隠すこと・見せること――実際、ファッションとは他人に対して自分を「見せる」ことだ。けれども、その時わたしたちは、同時に自分を「隠して」いる――ほかでもない、衣服を身にまとうことによって。ファッションとは、着衣によって自分を隠しつつ、隠すことによって自分を見せる技法なのである。そこでは、「遠ざかる」ことが「近づく」ことであり、まなざしを「拒む」ことがまなざしを「ひきよせる」ことにひとしい。そう、ファッションは、コケットリーのように<あいだをゆれる>のだ。見えることと見えないこと、隠すことと見せること、着衣と裸体のあいだを。コケットリーという誘惑の形式は、身体の可視的な表面に生起するファッショナブルな現象なのである。それは、まなざしを惑わしながら誘惑する。――本書より

英語アナログ上達法
講談社現代新書
日本の受験英語は、なぜ使えないのか?デジタル暗記学習法では決して教わらない「thereのこころは捨て言葉」「toのこころは到達」とは――。目からウロコのアナログ発想で基本から鍛え直す上達の決め手!

<むなしさ>の心理学
講談社現代新書
心のメッセージ――むなしさは、私たちの人生に何が欠けているかを告げ知らせてくれる貴重なメッセージだ……。だから、私たちのむなしさからの出発は、自分の内側で口を開けているそのむなしさから目を逸らさずに、きちんとそれを見つめることから始めなくてはならない。あるいはこう言ってもいいかもしれない。むなしさと、しばらくの間、いっしょにいること。むなしさに、時折、やさしく触れてみること。そしてそこから、どんな声が聞こえてくるか、ていねいに問いかけてみること。……
心のむなしさに何か大切な意味が秘められているということを、既に暗に感じとっていたはずなのだから。――本書より

天才になる!
講談社現代新書
はじめての自伝
写真を取ったら、オレ、何もなくなっちゃうから。オレの人生って写真そのものだから。
「天才アラーキー」はいかにして生まれたか。破天荒な修業時代、超絶的写真論を語りつくす。

ウイルスVS.人体
講談社現代新書
ここまでわかった「永遠なる侵略者」の正体!ウイルスは何を考えているか?
[ウイルスの戦略]――ウイルス感染を全身に広げないようにする生体の防御機構のひとつであるはずのアポトーシスが、癌やエイズなどの局面では、むしろウイルスの戦略に利用されたとも思える結果になってしまうのである。宿主――ウイルス関係はむかしの戦争にたとえられる。ウイルスは矛をもって宿主を攻めたて、宿主のほうは盾をもってこれに立ち向かうことになる。ウイルスの矛が宿主の盾を打ち破って感染することに成功すると、文字どおり、矛盾が起こることになる。最大の矛盾は、この盾となっているはずの防御機構そのものが生体を病気にさせる原動力であるという、ある種のウイルス病が存在することであろう。こうなってくると、われわれの精巧緻密な免疫系もかたなしである。策士が策に溺れてしまうわけだ。――本書より

フリ-メイスンとモ-ツァルト
講談社現代新書
天才の生涯と名曲をつらぬく秘められたメッセージ!
[メイスンリーへの入会――1784年12月14日、モーツァルトはヴィーンのロッジ「慈善」に入会した。……入会時のマスターはオットー・フォン・ゲミンゲンであった。「慈善」は「真の調和」と共に、合理的な考え方を基盤とする啓蒙主義的なロッジであった。「慈善」を選んだことは、モーツァルトがロッジに何を求めようとしていたかを示すもので、その後もモーツァルトのメイスンリーないしロッジに対する考え方は変わらなかったと見てよいだろう。……大きい「真の調和」よりも小さい「慈善」を選んだのは、1つはゲミンゲンと旧知の仲であったためであろうが、いま1つは、ヴィーンのエリートがきら星のように並ぶ「真の調和」では、一介のフリーランスの音楽家ではその中に埋没してしまうように感じたためでもあろう。――本書より

愛する家族を喪うとき
講談社現代新書
人生最大の悲しみをいかに乗りこえるか。相次ぐ永訣に直面した著者がつづる渾身の書!息子よ母よ妹よ!
[意識の底に眠る息子]――私が息子を喪ったのは、1993(平成5)年2月26日のことだ。病いで入院し、そして1週間後に急死してしまった。22歳の世間のどこにでもいるような平凡な学徒だった。不意に病いに冒され、そして、入院してそれこそ死など予想できない状態で逝った。……今こうして筆を進めているときから数えて3年以上前である。4年目にはいっても私のこころは癒えない。……たぶん息子の死は、終生私のこころの傷になるのだろうが、私はそれに耐えるのを自らに課す以外にないと、こころに決めているのである。……アメリカの諺に、「涙は泣く人だけが理解する言葉である」という言い伝えがあるそうだが、確かに私はその意味を理解できる――本書より

パソコンを疑う
講談社現代新書
メーカーの罪、ユーザーの無知。だから使いこなせない!痛烈無比の大批判
[怒濤のパソコン産業に反撃]――個人個人のコンピュータという意味でパーソナルコンピュータと呼ばれる部類のコンピュータのソフトウェアはとくに、従来的な工業製品のような作られ方、提供のされ方がふさわしくない。にもかかわらずここ20年近く、感性が粗雑鈍感でビジネス的に元気な人びとの手によってコンピュータソフトウェアの古典的な工業製品化が推進されてきた。パソコンのユーザは、それら専門的工業製品をただ単純に“あてがわれて”きた。それで果たしてうまくいったのか?全然うまくいってない!(中略)本書は、昨日までの怒濤のような、粗雑粗暴なるパソコン産業初期史に対する、コンピュータのソフトウェアに関する正しい常識の側からの反撃の、最初の試みの1つである。――本書より

新書アフリカ史
講談社現代新書
人類誕生から混沌の現代へ、壮大なスケールで描く民族と文明の興亡。新たなアフリカ像を提示し、世界史の読み直しを迫る必読の歴史書!
[「浮遊するアイデンティティ」の可能性]──エチオピアでは、単一のネイションを前提としない国家が成立した。1991年に政権の座についた新政府は、徹底した多元主義政策を推進し、93年にはエリトリアの分離独立を円満に承認した。94年に制定された憲法では、各民族に分離独立の権利を(名目的ではなく)保障した。国家は緩やかな統合体となったのである。これは近代市民社会の国家観と訣別した。新たな国家形態の実験でもある。こうした緩やかで単一でないアイデンティティは、実のところ、アフリカ社会が長年つくりあげてきた社会編成の原理でもある。それは柔軟で多元的なアイデンティティに基づく社会と言ってもよい。……
アフリカの柔軟で多元的なアイデンティティを評して、「浮遊するアイデンティティ」と呼んだ人類学者がいたが、単一のアイデンティティを強要する国家や民族という集団同士の殺戮や対立を忌避するためには、浮遊する柔軟なアイデンティティが必要となるだろう。アフリカ社会にはこうした可能性が秘められているのである。──本書より

犯罪学入門
講談社現代新書
日常の平安をおびやかすさまざまな逸脱行動や組織の暴走……具体的事例をふまえつつ、常識ではとらえがたいその内実、法との関連、社会の対応など幅広い知識を提供する。
〔犯罪と法〕──レイブリング・パースペクティヴは犯罪が必ずしも絶対的なものではなく、相対的なものであることに着目した。人類の歴史を見ても、また異なる社会を見ても、ある時代において犯罪と定義されていたものが、そうでなくなったりする。さらに社会状況に応じて異なり、日常生活においては厳しく非難される殺人でさえもが戦場においては英雄的行為と見なされる。
レイブリング・パースペクティヴは、まず第一に、犯罪が犯罪とされるにあたっては、前提としてそれが法律によって禁止されていなければならないという、従来見逃されがちであった基本的事実を指摘し、法律が制定される過程を調査し、それが社会の集団の組織の間のポリティクス、勢力関係に大きく依存していることを検証した。──本書より

はじめての一眼レフ
講談社現代新書
基本から応用テクニックまで、写真の腕をいかに磨くか。まずは日常の中に発見を求める「ご近所写真術」から始めよう。
〔「ご近所写真術」のすすめ〕──時間と金をかけて遠くに行かなくとも写真は撮れる!「近所」もまた写真撮影の現場として面白いし、刺激に満ちた空間なのだ。なにしろ、そこで実際に自分が暮らしているのだから、否でも応でも「わたしの日常」と向かい合わなければいけないことになる。それは文学でいう「私性」などという難しい世界に固執することではなく、明日を生きていくための、ささやかな実験のようなものだと思っている。
気軽に写真を撮り、その結果を見る。また撮る。そんな単純な繰り返しの作業の中から、「見る」ことの楽しさや驚きを発見できる。そしてそこにあるモノ、ここにいる自分自身をゆっくりと確認していける。近所を歩くこともまたおおいなる旅のひとつなのではないだろうか。──本書より

精神医学とナチズム
講談社現代新書
ヒトラーに心酔したユング、ナチ党員だったハイデガー。現代思想史上に輝かしい足跡を残した「知の巨人たち」の知られざる暗部がいま明かされる。
〔「アーリア人」ユング〕──フロイトはユングのオカルト現象や宗教への興味に危険性を感じ、ユングはフロイトの性欲説一点張りの頑固さに辟易していた。1913年、二人の対立は決定的となり、ユングはIPV会長を辞任する。ユングは「一種の心理的危機に陥り、第一次大戦が終了するまでほとんど引きこもった生活をおくっていた」と多くの評伝は伝えている。
しかしながらまさにこの時期、永世中立国であるスイス国民のユングは、ドイツの敵国イギリス・フランス人捕虜収容所で衛生士官の軍務に就いていた。そのときの写真には、生き生きとした表情のユングがはっきりと写し出されている。──本書より

金融ビッグバン
講談社現代新書
2001年をメドに動き出した金融制度の大改革。自由で公正で国際的で活力ある金融市場は本当に生まれるのか。日本経済は再浮上するのか。