講談社現代新書作品一覧

想像力
講談社現代新書
「ないもの」を思い浮かべる不思議な能力、想像力。日常生活から芸術まで、つねに「新しさ」を生みつづけるメカニズムは何か? ことばとの複雑な関係を解明しつつ、誰にも備わるこの能力を、存分に発揮させる方法を考える。
誰もがもつ創造の泉――想像力は芸術活動と関連づけられることが多い。また、天賦の才を与えられた人が行う創造とからめて想像力を議論することも多かった。しかし、私は、想像力は、ごく普通の人間の日々の営みや活動の過程で活発に働いているものだと考えている。…… 日々の営みや活動の中で、つねに人は「もの」や「こと」に働きかけ、それらを変形し、新しい形を創り出している。その結果をもたられる所産は、その時点でのさまざまな条件のもとに成立したもので、それはさらに人々の働きかけによって受け継がれ、また変容を遂げていく。想像力はそのような人々の営みに深く関わり、修正や変容をもたらし、新しいものを創り出す触発剤として働いているのである。――本書より

統合ヨ-ロッパの民族問題
講談社現代新書
ユーゴ内戦、チェコスロヴァキア分裂、国外ハンガリー人をめぐる国境問題…。「ヨーロッパ統合」へと向かう冷戦後の世界で、なぜ旧東欧は解体を続けるのか。「民主化」「市場化」を果たしEUに加盟する日は来るのか。「統合」「ヨーロッパ回帰」をキーワードに、民主問題の本質を探る。
「ヨーロッパ回帰」をめぐる3つの動き――1989年の東欧の体制転換以降、東欧においては3つの動きが象徴的に現れている。1つは、「中欧」の再編である。これは、「東欧」に代わる歴史的「中欧」理念の再興とともに、EUやNATOへの足がかりともなるさまざまな中欧の地域協力の成長というかたちで現れている。2つめは、民族問題の新たな成長である。現代東欧の民族問題は、歴史的な民族問題の再生という以上に、「民主化」「市場化」に象徴される政治的・経済的な発展と、国境修正を含む「国民国家」の枠組みの再調整の流れのなかで現れてきている。3つめは、EC/EU、NATOへの接近である。これをいうまでもなく、現在信仰中のヨーロッパの経済・市場統合、安全保障の統合的システムへの参入ということであろう。これらは全体として、「ヨーロッパ回帰」をめぐる一連の動きとしてとらえることができよう。――本書より

はじめてのビジネス英会話
講談社現代新書
「景気はどうですか」は英語で何と言う?「最高です」など11種の答え方とは?「目標設定こそすべて」戦略から「質問で会話の主導権を」戦術、「時間づくり」まで。豊富な実例を掲げ、ビギナー用基礎の基礎を満載。
面白い話題をストックしよう――会話における本質は、やはり「内容」です。……話題になりそうなトピックに関して自分の意見を持つ努力をして、それを理論的に、時には少々ドラマチックに話せるようにしましょう。自分が自信を持ってしゃべれる話題、相手に興味を持って受け入れられそうな話題をいつもストックしておくことも大切です。……しかし自分の専門分野や趣味の話ばかりする人はあまり歓迎されません。外国人と広い意味でのビジネス会話をする時には、日本では「書生論」などと呼ばれて軽視される傾向にある「天下国家論」も、たまにはできるようでなければなりません。面白そうな話題をストックしておくといっても、たとえばその日の新聞で読んだことでも、個人的なユーモラスなエピソードでもいいのです。いくつかを頭の中に整理しておいて、その場に応じて出していくようにするのです。――本書より

江戸語・東京語・標準語
講談社現代新書
武家と町人、山手と下町、標準語と方言。話しことばは時代を映す鏡であった。何がことばを変えてきたのか?江戸開府から明治を経て現代まで、日本語を通してたどるもうひとつの近代史。
「おっかさん」と「おかあさん」――国定教科書に採用されたことばの特徴的な例として「おかあさん」の場合を見てみよう。現在「母」をあらわすことばとして、最も一般的に使われているのは「おかあさん」だろう。しかし、この言い方は、少なくとも明治初期の関東以北にはなかった。幕末の日本語と英語を対比させたアーネスト・サトーの『会話篇』、ヘボンの『和英語林集成』でも、motherに対する日本語として挙げているのは、「はは」「ははさま」「母堂」「御母堂」「おっかさん」「おふくろ」で、ここには「おかあさん」ということばは出てこない。(中略)それなのに、なぜ、当時の国定教科書は「おっかさん」を捨てて「おかあさん」を採用したのだろうか?――本書より

「水滸伝」を読む
講談社現代新書
水沢の要塞・梁山泊に集結した108人の個性豊かな英雄豪傑たちの活躍を描き、ながく読みつがれ、民衆の支持を得てきた大河小説の面白さを史実と虚構の間から読み解く。
ひとり者の世界――『水滸伝』には多くのひとり者が登場する。そして、かれらがおんなに興味をもたないことを潔しとする調子で話が進む。これは現実の反映であろうか。都市化が顕著になると、流入者がふえる。かれらのなかには、多くの“一旗組”がいたであろう。それまでの自らの生活を放棄して、都市で一旗あげるのにかけた者たちである。かれらは、それゆえに、自らを自らの所属する組織から切り離したものたちである。そして、これは、当時の都市、否、当時の社会で生活していたもののかなりの家族組織が崩壊していたことを示すのではないか。おんなに興味をもたないのは、潔いのではない。かれらが家族を構成していないからである。――本書より

言葉のアヴァンギャルド
講談社現代新書
世紀が移り、新たな芸術が「運動」し始める。「切断の意識」につらぬかれた前衛──未来派、ダダ、シュレアリストたちが企てる言葉の解体・解放の冒険的な試み。意味を無化する方向に働く「20世紀の想像力」を考察する。
「20世紀」の表現者──彼らのほとんど唯一の共通項は、あの二重の「切断」の意識だったといってよい。一切の「過去」や「伝統」と断絶すること、そして「意味」や「内容」の支配から「外観」と「かたち」を解放することによって、アヴァンギャルド諸派は20世紀的なものの最初の表現者となったのである。──本書より

「戦後補償」を考える
講談社現代新書
朝鮮人・中国人の強制連行・強制労働、従軍慰安婦、占領下の住民虐殺など、戦争が生みだした悲劇の責任と、今なお未解決の補償問題を幅広い視野から考察する。
「戦後補償」とは――戦後50年になろうとしてる今、アジアの各地から日本政府、あるいは日本の企業に対して戦後補償の請求がなされている。住民虐殺、「従軍慰安婦」、強制連行・強制労働、軍票の被害など、その請求の内容はさまざまである。これらの請求に特徴的なことは、それが国家から国家に対してなされているのではなく、被害者本人あるいはその遺族から、直接、日本政府あるいは日本の企業に対してなされていることである。――本書より

ポスト不況の日本経済
講談社現代新書
「平成不況」は、なぜ戦後最大級になったのか? この不況を経て日本経済はどう変わるのか? 徹底的な分析と総括の中から、再生への道筋を展望する。
「世紀末不況」を超えて――多少の景気変動が「薄明かり」をもたらしたとしても、戦後からの長い歩みのなかに位置づけるならば、日本経済はいま明らかに「谷底」にいる。だからこそ、いま求められているものは、この「世紀末不況」の徹底的な分析とその総括である。「21世紀」という視点に立って、いまなにが終り、なにが始まろうとしているのかを明らかにしておくことである。そして、見通しの利かないこの「谷底」から、日本経済の「未来」を見通す「論理」を、その「頂き」へいたる道筋を見つけ出すことである。――本書より

海外ミステリ歳時記
講談社現代新書
春はバラとカーニヴァル、夏はヴァカンス、船の旅、秋はスポーツ、美術品……。古典から最新作まで500点を「四季」で読む決定版ミステリ・ガイド。
園芸とミステリ──1920年代のイギリスの長篇ミステリ界では、ミステリ以外の分野に顕著な業績を残した作家が、ミステリにも進出した例が多かった。たとえば『クマのプーさん』など童話や詩で知られるA・A・ミルンが『赤い館の秘密』を書き、また当時はダートムア地方を舞台とする田園小説で著名だったイーデン・フィルポッツは『赤毛のレドメイン家』や『闇からの声』などを書いた。1924年に名作ミステリとの誉れ高い『矢の家』を発表したA・E・W・メースンもその1人で、この作家の場合もミステリより普通の小説や戯曲の方が多い。ただしその『矢の家』で探偵役として活躍するアノー警部は、すでに1910年の『薔薇の別荘』に初登場していた。いささか唐突かもしれないが、ここでもまたバラがタイトルに冠されている。この『薔薇の別荘』という作品は、ミステリの歴史を考える上では、1920年代の隆盛への前哨戦を成す作品と考えられよう。さて『薔薇の別荘』は、南フランスの保養地が舞台で……。本書より

イスラ-ムとは何か
講談社現代新書
クルアーンが語る、神と使徒と共同体の根本原理と、その実践。イスラーム理解が拓く、世界への新たなる視点。
学者の対決――時は移って9世紀、所は帝都バグダード。……アッバース朝は栄華の絶頂にあった。……都のモスクの1つで今、学者たちが集っていた。居並んでいるのは、この都を代表する大家たち、……いつものモスクの情景さとして変わらない。……違っているのは、座を支配している異様な緊張感だった。今日は、重鎮たちに相対して、1人の見慣れぬ学者が座っている。この人の名をブハーリーと言う。ブハラ出身者、を意味する名前である。……長ずるに及んで、諸国を遍歴してハディースを学び、類稀な逸材として、名が高まった。その人が帝都にやって来るという。都のハディース学者たちは、彼がどれほどの学者か試してやろうと、待ち構えていた。今日は、その対面の日なのである。いや、対決の日、と言うべきか。10人の学者が100のハディースについて、ブハーリーの知識を試す。ハディース百番勝負、とでも言うべきか。――本書より

「松代大本営」の真実
講談社現代新書
天皇を信州へ。半世紀前、「日本の敗戦」を前提に、この地下要塞計画は実行に移されていった。発掘した新資料を駆使し、「神聖なる大工事」の全貌を、いま明らかにする。
破壊せよ──現在一括して松代大本営と呼ばれる軍事施設群について、処分勧告がなされていたのは、「C軍用飛行場」欄に1つ、「D兵器庫」欄に3つあった。「長野軍用飛行場=爆撃によって破損し高性能航空機には危険=滑走路は接収すべし」「須坂の兵器および弾薬倉庫=4ヵ所の絹糸倉庫内=日本人に返還」「善白鉄道の兵器および弾薬倉庫=2ヵ所の鉄道トンネル内=日本人に返還」「中野の弾薬庫=多くの洞窟内に存在=洞窟を閉鎖せよ」松代大本営の総本山として、目指すべき項目は、いうまでもなく「B地下要塞」。そこには、こうあった。「日本帝国総指揮部のための地下司令部と推測され、地下通路によって連結されたコンクリートの司令部建造物と広大な網状の洞窟、ただし未完成」。(中略)そして、その「処分」欄には、こう明記されていた。Destroy──本書より

王朝貴族物語
講談社現代新書
午前3時の起床、吉凶占いから、夜の社交までの一日。激烈な出世競走、土地や富への欲望。恋の歓びと怨霊への恐怖。豊富なエピソードでつづる奈良平安華麗絵巻。
貴族たちの朝――貴族の一日は、……午前3時ごろから始まる…… まず起きると、属星の名号を微音で七遍となえる。生年によって、各自自己の運命の所属する星が、北斗七星の中の星の一つに定まっており、それが属星である。次に、鏡で、自分の顔を見て、心身の調子を判断する。次に、当時の暦は具注暦といって、吉凶などの注が具体的に記入されているので、それを見てその日の吉凶を確かめる。次が洗面。楊枝で歯の掃除をし、西を向いて手を洗い、神仏の礼拝をする。仏名をとなえ、信仰する神社を祈念する。…… 軽朝食がすむと身だしなみ。髪に櫛を入れるのは、毎日ではなく3日に1度でよい。手の爪は丑の日に、足の爪は寅の日に切る。次に入浴だが、日を選んで5日に1度である。日の選びかたも細かく定まっている。毎月1日に入浴すると短命、8日に入ると長命。11日は目が明らかになり、18日に入ると盗賊に会う。午の日では愛敬を失い、亥の日では恥を見る。悪日(寅辰午戌)は入浴してはならない。これではいったい、月に何回入浴できるのだろうか。――本書より
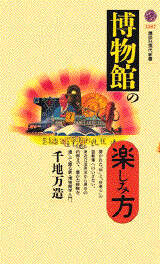
博物館の楽しみ方
講談社現代新書
開かれた「知」と「好奇心」の遊戯場へのいざない。身近な活用法から展示の内側まで、豊かな経験を通して語る新・博物館学入門。
展示の裏側──展示されている「もの」には、それがその場所に置かれるまでに、それぞれ、その「もの」だけが知っている経緯がある。博物館は、なぜ、どのようにして「もの」を集めるのか。博物館は、地域の人々や社会とどんな関わりをもっているのか。展示の裏側で、学芸員たちがどんな仕事をしているのか。それらを知ることは、博物館を楽しみ、より上手く利用するために必要である。本書は日本各地の博物館を紹介する案内書ではない。いくつかの博物館を巡りながら、それぞれを違った切り口から見ることによって、「博物館とは何か?」「博物館はわれわれとどんな関わりをもっているのか?」を読者とともに考え、博物館をより身近なものとして感じ、楽しんでもらうことを目的として筆をとったものである。──本書より

政治家の誕生
講談社現代新書
強健の行使に禁欲的で、現実に対する深い洞察と、豊かな構想力をもつ。暴力ではなく、言葉を手段として改革を実現する──近代イングランドを舞台に、あるべき政治家像を描く。
政治家とは──歴史をひもといてみると、いつの時代も、政治家の評判はかんばしいものではなかった。しかし侮蔑や厳しい批判にさらされつづけた多くの政治家のもとで、人々が平和と繁栄を享受したことも忘れられてはならない。批判にさらされながらも、なおかつ、結果として人々に平和と繁栄をもたらしたという事実のなかに、われわれはもしかしたら、政治家による統治が他のどのような統治よりも優れている点を見ることができるのかもしれない。政治家が政治の表舞台から姿を消したとき、人々が独裁者や軍人、あるいは狂信的な指導者の強権のもとにおかれ、自由を失い、ときにおびただしい血が流されたことを歴史はこれまで何度も見てきている。──本書より

恐竜ルネサンス
講談社現代新書
北極を中心に恐竜は「渡り」をしていた。温かい血や羽毛をもち、子供の世話をし、敏捷に動き集団で狩りをする新しい恐竜像を、世界的権威が日本人読者に向けて書き下ろす。
渡りをする恐竜たち──極地の恐竜化石は、カナダのユーコンと北西地方や、シベリアでも発見されてきた。……極地域は中生代には、今日よりもずっと暖かかったけれども、冬のあいだはなお暗かった。このため植物は休眠中となって、大きな植物食恐竜が食べるに充分な食物はなかったであろう。……ハドロサウルス類、角竜類、ティラノサウルス類は、食物が冬中もっとたくさんあった低緯度の土地へと移動した。……ハドロサウルス類は、北極の夏で豊富な食物源を利用するために、春になると群れを作って北進した。その地で彼らは秋が来るまで分散したであろう。秋には、近づいてくる完全な暗やみの時期が、たいていの植物に冬の休眠状態に入ることをうながした。そこでハドロサウルス類は、再び集まって群れをなし、冬中食物を得ることができる地域へと南下したのだろう。長い移動は1年のうち4ヵ月を占めたかもしれないが、ハドロサウルス類は長い脚をもち効率的に歩いたので、十分可能であった。──本書より

協奏曲の名曲・名盤
講談社現代新書
オーケストラと絡みつつ色彩を増すピアノ、自在に遊ぶヴァイオリン、多様に表情を変えるチェロ、けだかく輝くクラリネット──。協奏曲の快楽を追求し、ヴィヴァルディからショスタコーヴィチまで、名盤の聴きどころを語る。
シューマン・ピアノ協奏曲イ短調Op.54──コルトーのは1951年のライブで音が悪く、ピアノもミスタッチだらけだが、(中略)とにかくものすごい演奏だ。昔の巨匠の表現力がいかに濃厚自在であったか、いかに劇的かつロマンティックであったか、いかに作曲者の魂の奥底までをあぶり出すほど深かったかが納得されよう。(中略)遅いテンポを主体に気持ちをこめぬき、粘り、音符の一つひとつにすべての愛情をそそぎこみ、即興的に崩し、病的なまでのピアニッシモをひびかせ、あるいは意外にすっと通り抜ける。それらが全部芸になっているのだ。芸ができて初めて芸術にまで高まるのである。この音の悪い、ミス・タッチの多いCDを聴いて感動できた人は、すでに芸術の深奥に達しているといえよう。それこそクラシック音楽が行きつく最後の愉しみの境地である。──本書より

ケネディ その実像を求めて
講談社現代新書
賛否両極から虚実とりまぜて語られてきたケネディ。だが、ダラスで凶弾に倒れた若き大統領は本当は何を目ざし、何を残したのか。その生涯と暗殺の謎とを検証する。
ケネディへの旅──そもそも、暗殺されてから30年近くが経ったいまになっても人々に忘れられず、こうした映画が作られるケネディとは、本当はいったいどんな人物だったのだろう?……これほど長い歳月が経過したあとでも人々にその若い死を惜しまれるほどの魅力のある大統領だったのだろうか。……暗殺事件の真犯人はわからないにしても、オズワルトも含めて誰と誰がその可能性のある人物(ないし組織)なのかを知りたいと思った。そのためには、彼の経歴や生い立ちを調べることがどうしても必要だった。……そして、その映画を見た1年後、とうとう私はケネディへの旅を始めていたのである。──本書より

赤ん坊から見た世界
講談社現代新書
その目に映るものは何? なぜ知識もなく複雑な文化世界に入れる? 物理を理解し、言語以前の思考ができる、謎と魅力にみちた、人間の「原型」に迫る。
言語以前の思考――満1歳から1歳半にかけて、子どもの思考は大いに発展していく。そのような、まだほとんど言葉が出ていないような子どもが、意味やカテゴリーの体系をもっているといわれると驚くかもしれない。とくに、言葉と思考を同一に見ている立場からすれば、言語以前にカテゴリーのような高度な思考の基本があるなど、奇妙に思われることだろう。しかし、最近の証拠に照らしていえば、むしろ言語と言語による意味は、言語以前の思考を基礎にして成立するのである。最近の多くの研究によれば明らかに、乳児期の後半において子どもたちは、さまざまなカテゴリーを形成しているのである。そのカテゴリーの根本は、しかし、抽象的な思考というよりも、外界の知覚に関連したイメージ的な思考によっている。――本書より

情報操作のトリック その歴史と方法
講談社現代新書
ナポレオン、ヒットラーによる情報操作から、投書や広告を利用した最新の情報操作まで、具体的な事例を通して、事実と異なる「事実」がいかにつくられていくのかを見る。
洗脳とサブリミナル――自由がなく、自分でコントロールできない状態が続くと、まず自分が結果をコントロールできないという認知を、何事につてもするようになる。それによって、反応開始が遅延したり、消極性が支配的になってくる。そこから、さまざまな感情障害が生ずる。( 中略) 抑鬱気分、無力感が常に襲い、自尊心の低下が見られるようになる。自尊心が低いと、自分のアイデンティティを保つための構えもないので、やはり説得を受けやすくなる。このような状況下で説得されると、その情報が自分自身の態度の体系の中に容易に組み込まれ、しかもそれが持続することになる。共産主義の信奉者となった元捕虜のパイロットに対し、通常の状況下で自由主義の態度に戻そうとしても、異なった態度の体系を内面化しているために、非常な困難を伴うことになるのである。――本書より

外国語としての日本語その教え方・学び方
講談社現代新書
ふだん何気なく使っている日本語の意外な横顔。独特のアクセンや敬語、微妙な表現・言葉の使い分けなど、視点を変えると見えてくる日本語再発見の書。
「迷惑の受け身」――次のような場合はどうだろうか。「木村がいびきをかいてね」と「木村にいびきをかかれてね」。前者なら、木村君のいびきを面白がっているのかもしれない。しかし、後者のように受け身形で使った場合には、明らかに「いびきがうるさくて、眠れなかった」とはっきりと、迷惑だった自分の体験を、受け身表現の中に込めている。留学生がこういった会話に、相手の期待通りに反応できない場合、日本人学生は「留学生ってさ、やっぱりカルチャーが違うっていうか。日本語はできても、どこか通じないんですよね」となってしまう。これらは明らかに日本語の問題なのだが、日本人学生自身、何が問題の鍵なのか判断できない場合が多い。「カルチャーが違う」では解決できない、日本語の受け身の問題がそこに潜んでいる。――本書より