講談社選書メチエ作品一覧

儒教と中国 「二千年の正統思想」の起源
講談社選書メチエ
皇帝と天子 中華と夷狄「大一統」
中国史を貫く“統治と権力”の思想構造
儒教が「国教」となったのはいつか。皇帝と天子は同じものか。曹操はなぜ文学を称揚したか。諸葛亮は何を守ろうとしたのか。「竹林の七賢」は何に抵抗したか。国家の正統性を主張し、統治制度や世界観の裏づけとなる「正統思想」の位置に儒教が上り、その思想内容が変転していく様を、体系性と神秘思想の鄭玄、合理性と現実主義の王粛、光武帝、王もう、曹操や諸葛亮など、多彩な人物を軸にして、「漢」の成立と衰退、三国、魏晉時代の歴史を交えながら描き出す。
【目次】
序章 二千年の正統思想
1. 注に込められた思想性
2. 経典解釈の二つの方向
第一章 権力に擦り寄る儒者
1. 儒家の形成
2. 漢初の黄老思想
3. 『漢書』の曲筆と天人相関論
4. 公羊伝と武帝期の政治状況
5. 石渠閣会議と匈奴
6. 儒教への心酔
第二章 中国の原基
1. 図讖の宣布
2. 「儒教の国教化」論
3. 「古典中国」の形成
4. 「寛」治の盛行
5. 皇帝と天子
6. 礼と故事
第三章 後漢の衰退と聖漢へのまなざし
1. 外戚の正統性
2. 皇帝の延長権力の横暴
3. 後漢からの自律性
4. 儒教への異議申し立て
5. 聖漢の賛美と未来への経学
6. 六天説と天の無謬性
第四章 時務を知る──『三国志』の時代と儒教
1. 儒将
2. 「猛」政
3. 「文学」の宣揚
4. 諸葛亮の漢代的精神
5. 諸葛亮の「猛」政
6. 蜀学を尊重
第五章 曲学阿世──抵抗する竹林の七賢
1. それぞれの皇帝の正統性
2. 天は一つ
3. 「孔子も人を殺した」
4. 不孝の理由
5. 周・孔をうとんじる
6. 君無道
第六章 「儒教国家」の再編と限界
1. 封建・井田・学校
2. 人は生まれにより異なる
3. 「夷狄は教化できない」
終章 「古典中国」と二つの「儒教国家」
1. 古典と「古典中国」
2. 大一統──統治制度
3. 華夷──世界観
4. 天子──支配の正統性
引用・参考文献
あとがき
索引

選書日本中世史 4 僧侶と海商たちの東シナ海
講談社選書メチエ
選書日本中世史 第4弾!
「海域交流」から「中世」を照射する!
遣唐使が途絶してからも、大陸との交流はむしろ活発に行われていた。その担い手は利を求め海を闊歩する海商たち。そして、彼らの助けを得て何百もの僧侶たちがあらたな教えを求めて大陸へと向かっていた。多くの記録を史料に残した僧たちの足跡を辿ることで、海域交流の実相に迫り、歴史世界としての東シナ海を描き出す!

ことばと身体 「言語の手前」の人類学
講談社選書メチエ
わたしが話す。あなたが自分の体にふれる。このとき、何が交されているのか?
わたしたちが会話をしているとき、そこではことばだけが交わされているのではない。どんなに些細な、他愛のないおしゃべりであっても、自分の体にさわったり、身ぶりをしたり、ごく短い間があったり、ときには何かを演じたり、身体まるごとつかったコミュニケーションが繰りひろげられている。ブッシュマンの家族、日本の大学生、民俗芸能という多様な会話の現場を、徹底的にミクロに観察することで、コミュニケーションとは何か、社会とは何かという大いなる問いに挑む。現象学、社会システム理論、言語行為論などを参照しながら、徹底的に「身体」に根ざして考える“唯身論”人類学の試み。
【目次】
唯身論のために──まえがきにかえて
本書の表記法について
序章 言語の手前からの出発
第一章 グイの父子像──あたりまえのことを記述する
一 グイとの出会い
二 父と子の相互行為
三 父と子の表情空間
第二章 自分にさわりながら話す──日常会話における自己接触
一 微小な経験の自然誌へ向けて
二 字義的文脈に規定された自己接触
三 会話者の基本的な身がまえと会話の時間構造
四 関係性の露呈──自己接触の文脈分析
五 完結可能性の投射
六 独我論の綻び──考察
第三章 身体による相互行為への投錨──会話テキストはいかにわからないか
一 テキストを前にして
二 身ぶりと動作による意味の開示
三 身ぶりによる意味の充実
四 位相の複合と社会関係
五 「わからなさ」の壁
六 身体が投錨する意味
第四章 民俗芸能における身体資源の伝承──西浦田楽の練習場面から
一 「観音様」との出会い
二 身体資源の再配分
三 ニイから若い衆への指導
四 年長者たちの愉しみと挑戦
五 身体資源と実践共同体
第五章 相互行為から社会へ──「会話の人類学」再訪
一 社会とは何か──理論的背景
二 分析の背景
三 外部世界への接続
四 「場」の内部を志向する行為
五 情況に埋めこまれた「場」──事象次元での連接
六 過去への遡行──時間次元での連結
七 不快の表情空間──社会的次元への接合
八 相互行為を超える意味
終章 唯身論の人類学へ向けて
一 思考の枠組
二 明らかになったこと
注
あしたのために──あとがきにかえて

満州事変と政党政治 軍部と政党の激闘
講談社選書メチエ
激闘86日 万策尽き政党政治は終焉した
従来考えられていた以上に堅固だった戦前政党政治が、なぜ軍部に打破されたのか。そこには陸軍革新派による綿密な国家改造・実権奪取構想があった。最後の政党政治内閣首班、若槻礼次郎の「弱腰」との評価を覆し、満州事変を画期とする内閣と軍部の暗闘が若槻内閣総辞職=軍の勝利に至る86日間を、綿密な史料分析に基づき活写する。
【目次】
プロローグ 共同謀議──一九二八年三月一日「木曜会」
第一章 発端──柳条湖鉄道爆破
第二章 東京・三宅坂──陸軍省・参謀本部
第三章 東京・永田町──首相官邸
第四章 奉天──関東軍司令部
第五章 構想の対抗──政党政治と昭和陸軍
第六章 満蒙新政権への対応
第七章 北満進出と錦州攻撃をめぐる攻防
第八章 若槻内閣総辞職と荒木陸相の就任
エピローグ 五・一五事件と政党政治の終焉
註
あとがき
索引
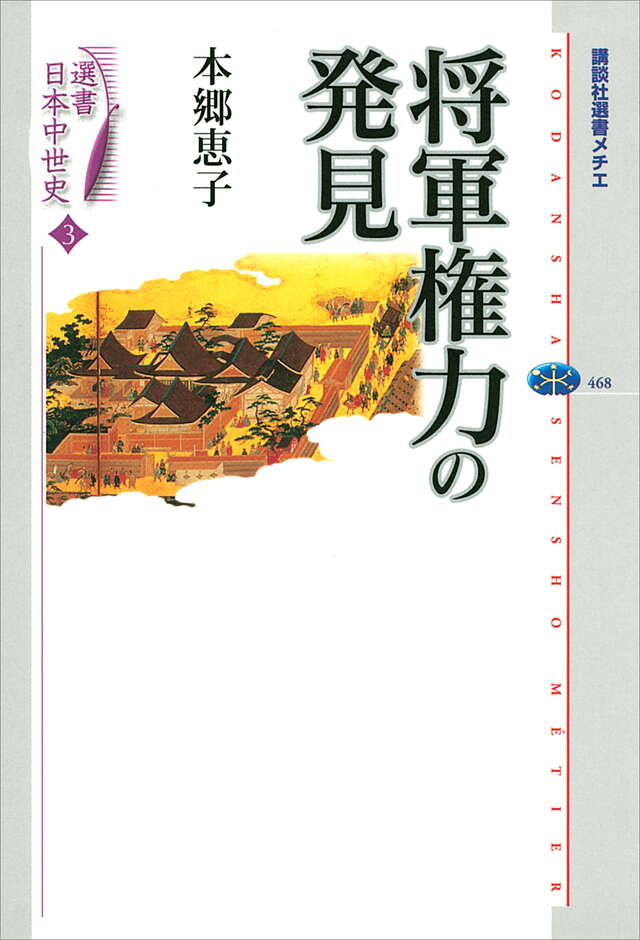
選書日本中世史 3 将軍権力の発見
講談社選書メチエ
選書日本中世史 第3弾!
公家政権と武家政権と寺社勢力……室町幕府の傑出した統治構造とは!?
室町幕府にできて、鎌倉幕府にはできなかったこと。それは、「太平の世」前夜の、動乱の続く地方に対して中央政権として安定的に君臨することである。そのために室町幕府が考え出した統治構造とは? 自明のものとされてきた将軍の主従性的支配権に一石を投じ、天皇・公家の持つ力の本質を検証することで、明らかになった将軍権力とは、いったいどんなものだったのか? 「わかりにくい中世をどうわかりやすくするか」の大問題に真っ向から挑む、刺激に満ちた1冊。

ギリシア文明とはなにか
講談社選書メチエ
オリエント・ギリシアを包含する「東地中海文化圏」の視点から独自の史観を展開
地中海世界は「東」と「西」に分かれている。ギリシア文明は、エジプト・ペルシアなどオリエント「先進国」のはざまのローカルな「東地中海文明」だった。その小さなギリシアが歴史の僥倖によりオリエントを征服し、西洋文明の源泉となる。「自由」と「海」の小さな文明が歴史に残した偉大な足跡を辿る。
【目次】
はじめに
序 章 地中海の古代──ペルシア戦争前
第一章 ギリシア対エジプト・ペルシア
1 エジプト・ギリシア
2 ペルシア戦争
3 内戦
4 クセノポン
5 傭兵
第二章 アレクサンドロス
1 ギリシア統一
2 オピス演説
3 富と文明
4 跪拝礼
5 弟子と師
第三章 ギリシア対ローマ
1 東地中海文化圏
2 カトー
3 ポリュビオス
4 「新」「旧」ギリシア
5 ユダヤ・ローマ・ギリシア
終 章 生き残る文化圏──西と東のローマ
おわりに
参考文献
関連年表
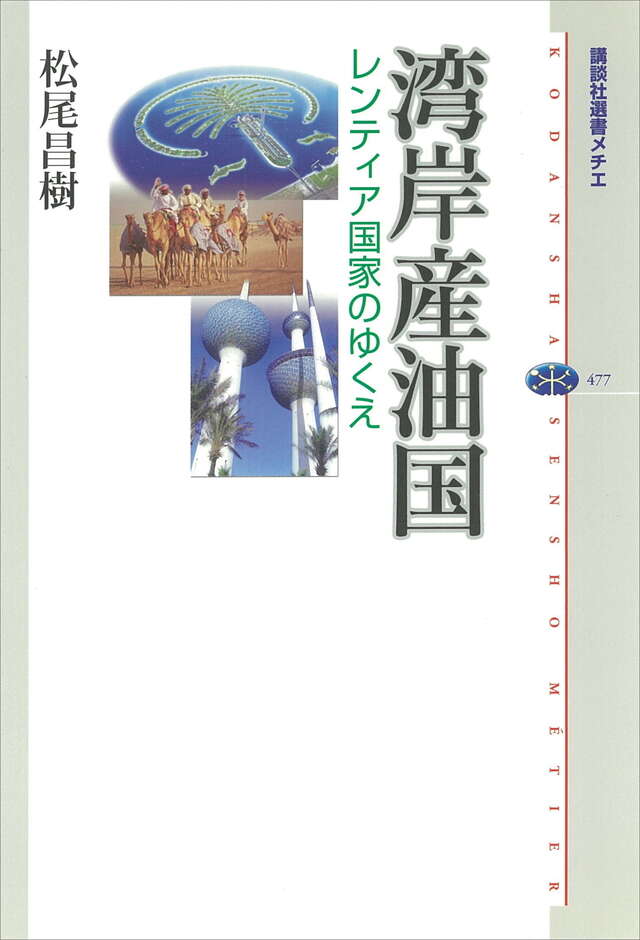
湾岸産油国 レンティア国家のゆくえ
講談社選書メチエ
莫大な石油収入と王朝君主制
豊かさと非民主政が両立する国々
クウェイト、カタル、バハレーン、UAE、オマーン。湾岸産油国は、驚くべき特徴に満ちている。莫大な石油収入によって、所得税はなし、教育費は無料。1人あたりのGDPが日本の2倍の国もある。一方で、「経済発展が民主化を促進する」という定説はあてはまらず、君主制が維持されたままだ。2009年のドバイ・ショックで、世界経済における影響の大きさを知らしめた「石油王が統治する金満国家」を詳細に分析、政治・経済・社会の実体に迫る。
【目次』
はじめに
第1章 湾岸産油国とは
五つの国々/共通する特徴/レンティア国家仮説/王朝君主制/議会制度/国民統合/イスラームと君主制/エスノクラシー
第2章 国家形成への道のり
「新しい」国/自然と地理/前史/オマーンとイギリス/「休戦海岸」の成立/ウトゥブ族の移住/石油前夜/近代的君主制の成立/与えられた独立
第3章 レンティア国家仮説
二つの論点/民主化と社会発展/資源の呪い/レント収入とは/レント依存が意味するもの/もう一つのレンティア国家仮説/忠誠はいつまで「買える」か
第4章 王朝君主制
「王朝君主制」の意味/「主権の諸省」の独占/なぜ協力するのか/なぜ王朝君主制は頑健なのか/王朝君主制の将来(1)─王位継承権/オマーンにおける権力配分/バハレーンとカタルの場合/クウェイトの問題/王朝君主制の将来(2)─君主と首相、皇太子の権力バランス
第5章 国民統合
国民意識/国民統合とナショナリズム/誰が国民なのか/歴史と国民統合/「国史」の類型/「祖国防衛」の物語/湾岸戦争の記憶/語れない歴史/「文化」を通じたとりひき
第6章 湾岸産油国型エスノクラシー
現代の奴隷制?/湾岸産油国型エスノクラシーとは/外国人への依存/自国民優遇政策/自国民プレミアム/自国民労働者と外国人労働者の分化/他者としての外国人/湾岸産油国型エスノクラシーの将来
第7章 湾岸産油国の未来
「崩壊説」への疑問/石油の生産寿命/石油枯渇危機論の奇妙さ/石油が生産され続けても、「崩壊」は到来するか/「崩壊」の後に到来するもの/湾岸産油国へのまなざし/グローバル化の中で
注
参考文献
あとがき

日本人の階層意識
講談社選書メチエ
格差意識の広がりと「一億総中流」のからくり。現実の日本人は、学歴もさまざま、職業も年収もさまざまなのに、なぜ人口の9割が「自分は中流」と思っていたのか? 社会と意識のあいだには「みえない境界」があって、それが人びとの階層意識を枠づけている。格差意識の広がりも、「みえない境界」に目を向けることで、別の一面が顕わになる。時間・空間・価値意識をキーワードに「日本人」を分析する。
【目次】
序 章 階層意識の「みえない境界」
1 「その趣味はあなたの趣味ですか」
2 枠づけられる階層意識
3 自由と不自由の間
4 本書の試み
第1章 時間と階層意識
1 学歴の価値
職業より学歴/進学率の変化/階層帰属意識の変化/階層構造と階層帰属意識
2 地位の継承
経路依存性/継承された地位とそうでない地位/社会的地位の価値変動/歴史の中の個人
第2章 地域と階層意識
1 大都市圏か地方か
地域で変わる階層帰属意識/大学進学率と地域/上層ホワイトカラー率と地域/空間化された階層意識
2 相対的不満
相対的不満とは/進学率にみる相対的不満/上層ホワイトカラー率にみる相対的不満/空間化と非空間化
第3章 競争を好む人びと
1 豊かさの配分原理
実績か努力か/無知のヴェール
2 空間化される競争社会観
価値意識の地域差/望ましくない空間化
3 ひきずられる価値意識
地域と階層構造と価値意識/空間化の自己強化
4 問題の隠蔽化
階層的利害の危険性/みえていないものからの影響
第4章 「日本人」と階層意識
1 「一億総中流」とは何だったのか
日本特有の現象?/曖昧な輪郭
2 「中流」の構
社会的地位の非一貫性/「中流」という階層イメージ
3 格差社会論の誕生
ばらばらだった判断基準/大きな「静かなる変容」
4 なぜ「努力好き」なのか
個人プレーよりチームプレー/「意に反する」長時間労働/「日本人」という境界
終 章 意識と社会
1 私たちの意識は私たちのものか
2 時間という境界
3 空間という境界
4 境界を知るということ
註
あとがき

ピラミッドへの道 古代エジプト文明の黎明
講談社選書メチエ
いったいピラミッドとは何なのか。王墓なのか、そうでないのか。古代エジプト文明と、あの巨大な建築群はいかにして生まれたのか。
メソポタミアや地中海世界、ナイル源流アフリカとのインタラクション、サハラ砂漠が緑のサヴァンナであった可能性、
王のシンボル図像が物語る動乱と変革の痕跡、ミイラのない石棺、ピラミッド・コンプレックスの構造……
大胆な構想と精緻な分析を武器に・文字以前・の歴史を描き出す!
【目次】
プロローグ
ピラミッドを理解するために/キーワードと各章の内容
第0章 ピラミッドを語る前に
ヘロドトスとピラミッド/ピラミッドの基礎知識/古代エジプト人の宗教観/古代エジプトの王権観/オシリス、ホルス、セト/古代エジプトの地理と風土/ナイルに暮らすエジプト人と異民族/ピラミッド理解への道
第一章 ピラミッドへのプレリュード
古代エジプト文明への憧れ/光は東方からか?/南方のアフリカからの影響/北の地中海世界からの文化的影響/西方世界=「緑のサハラ」の存在意義/岩絵に見られる太古の記憶/ナイル世界へのもう一つの刺激/環状列石と暦の役割/北アフリカにおける牛の埋葬/ナイル世界はカレー鍋か?
第二章 ピラミッドの萌生期
ナイル河谷における埋葬の始まり/ピラミッド以前のアビドスの王墓/ウンム・エル=カアブの葬祭周壁/ウンム・エル=カアブの船坑墓/古代エジプトの図像としての船/古代エジプトの神々と船/世界各地に見られる舟葬と舟葬墓
第三章 ピラミッドができるまで
アビドスとサッカラの王墓地論争/統一王朝出現以前の古代エジプト王たち/最初の古代エジプト王/埋葬習慣としての殉葬と墓の構造/第二王朝期の古代エジプト王たち/カセケムウイ王のプロフィール/アニミズムとトーテミズムに見る王名/混沌からさらなる混沌へ
第四章 ピラミッド時代の到来──ネチェリケト王と階段ピラミッド
階段ピラミッドとイムヘテプ/ネチェリケト王は階段ピラミッドに埋葬されたか?/階段ピラミッドをいかに理解するか/ネチェリケト王とその時代/王権確立の象徴としての階段ピラミッド/ピラミッド出現に自然環境が与えた影響
第五章 ピラミッドとは何か?
聖域としてのピラミッド・コンプレックス/ピラミッドは王墓なのか?/ピラミッド異説1 フォン・デニケンの『未来の記憶』/ピラミッド異説2 メンデルスゾーンのピラミッド公共事業説/ピラミッド異説3 ボーヴァルとギルバートの「ピラミッド・オリオン説」〔以下略〕
エピローグ
あとがき
地図
参考

近代日本の戦争と宗教
講談社選書メチエ
戊辰戦争から日露戦争まで
宗教は国家といかに向き合ったか
戊辰戦争によって新たな政権が誕生してから、日清戦争・日露戦争の勝利によって対外的な地位を向上させるまで、明治国家のあゆみには、戦争がともなっていた。そうした戦いのなか、神社界、仏教界、キリスト教界は、いかなる反応をみせたのか。従軍布教や軍資金の提供といった積極的な協力姿勢から、反戦論・非戦論をはじめとする、消極的姿勢──、本書は、その実態を描いてみようとするものである。
【目次】
プロローグ──「前奏曲」として
第一章 戊辰戦争と宗教──権力交代劇の狭間で
一 戦争と本願寺
二 神職たちの戦争と天皇の祈り
三 徳川家菩提寺のゆくえ
第二章 台湾出兵──初めての海外派兵と軍資献納
一 初の海外派兵と大教院
二 出兵と神宮・出雲大社
三 その他の神社界の動向と外交交渉の妥結
四 凱旋と教導職賀章上呈
第三章 西南戦争──日本最後の内戦の中で
一 教部省の廃止と戦争の勃発
二 戦争下における真宗
三 戦争下における神社
四 真宗解禁の意義とその後の田中直哉
第四章 日清戦争──アジアの大国との決戦と軍事支援
一 戦争の勃発と仏教界の協力
二 キリスト教界の協力と戦争観
三 神道界の動き
四 「従軍」から「開教」へ
第五章 日露戦争──列強との対決と「団結」
一 ロシア正教迫害問題の発生と正教側の対応
二 ロシア正教問題に対する政府・宗教界・軍の対応
三 日本軍の展開と従軍布教
四 キリスト教界と非戦の声
エピローグ──「交響曲」へ向かって
あとがき
註
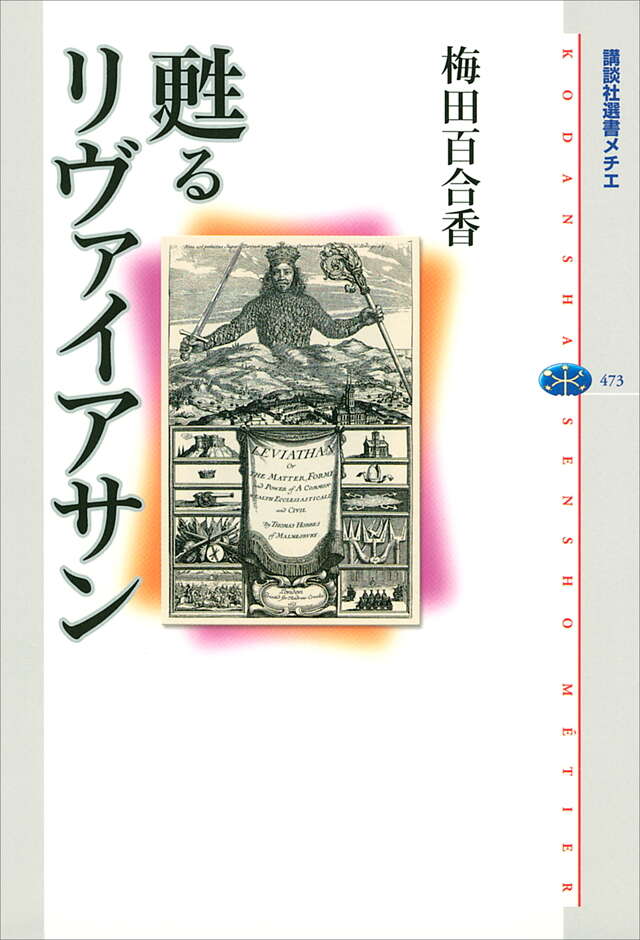
甦るリヴァイアサン
講談社選書メチエ
近代政治という「怪物」の正体に迫る
現代世界は、「万人の万人に対する闘争状態」か?「国家権力」は「悪」なのか?悪名高きホッブズのテーゼの真意を原典に即して解明し、アレント・ネオコン・ネグリ=ハートの思想と対峙させながら、近代政治哲学を切り開いた古典を「希望の書」として読み直す。
【目次】
はじめに
第一部 ホッブズの近代性とその意義
第一章 世界観の転換──ピューリタン革命と「神の王国」論
1 ホッブズの生涯と時代の課題
2 自然状態──神と人間
3 「神の王国」論とホッブズの世界観
第二章 社会契約論──自然法と自然権
1 主権者と自然法
2 臣民の自由──自己保存権の留保=従わない自由
3 抵抗権問題──敵か臣民か
4 自然法を守る義務と内面の自由
第三章 軍事論──戦争拒否の自由と国家防衛義務
1 主権と軍事力
2 イングランドの現実──軍事革命と常備軍
3 軍隊の現実──強制徴募の問題
4 戦争拒否の自由と国家防衛義務
第四章 国際関係論──自然法と諸国民の法
1 ホッブズと国際関係論
2 ホッブズの自然法と諸国民の法
第二部 ホッブズと近代批判者
第五章 ホッブズとアレント──必然と自由、義務と愛
1 ホッブズの人間像とアレントの「労働する動物」
2 ホッブズとアレントにおける社会契約の二類型
第六章 ホッブズとレオ・シュトラウス──政治哲学と道徳的基礎
1 シュトラウスとホッブズの政治哲学
2 シュトラウスの意義と問題
3 シュトラウスのアメリカとホッブズ
第七章 ホッブズとネグリ=ハート──国民国家と〈帝国〉
1 主権──国民国家
2 主権──〈帝国〉
3 近代とポストモダン──過去と未来の間
終 章 ホッブズと希望 ホッブズ思想の可能性
注
あとがき
索引

選書日本中世史 2 自由にしてケシカラン人々の世紀
講談社選書メチエ
選書日本中世史 第2弾!
可能態としての中世社会
この社会を変えることの困難さ、いまこの社会を生きることの困難さは、「公」が曖昧な形で「私」を包摂しているという、日本社会の<公共性>の構造に由来している。しかし、南北朝と戦国という中世における2つの「変革期」、それはたしかに、社会が変わる可能性をもっていた時代であった。その「変革可能性」が隆起しては陥没していったさまを、深く鋭い歴史学の視線と、きわめて平易で軽妙な語り口とで、あざやかに、そして熱く論じる!

台湾ナショナリズム 東アジア近代のアポリア
講談社選書メチエ
日本人にとって台湾とは何なのか
親日か反日か。統一か独立か。
しばしば二項対立で語られがちな台湾ナショナリズムは、日本と大陸中国、冷戦期とポスト冷戦期、米国のプレゼンスの低下と中国の台頭など、長期的かつ複数の視座で整理すると今なお続く東アジア近代のアポリア(難題)として見えてくる。日本人にとって重要な歴史経験でもある「台湾問題」を、詳細に読み直す。
【目次】
序 章 なぜ「台湾ナショナリズム」を考えるのか
第1章 日本が見た台湾
第2章 大陸中国が見た台湾
第3章 東アジア冷戦/ポスト冷戦が見た台湾
第4章 東アジア近代が見た台湾
結語に代えて 複数のプロセスとして見ること

ハプスブルクとオスマン帝国-歴史を変えた<政治>の発明
講談社選書メチエ
「トルコの脅威」が近代ヨーロッパを生んだ
圧倒的軍事力を誇るオスマントルコから、いかにヨーロッパを防衛するか?最前線に立たされたハプスブルクが取った対抗策──それは情報を収集し、バラバラな諸侯をデータを挙げて説得して糾合する一方、民衆を反トルコプロパガンダで動員することだった。
近代政治誕生のドラマを解明する画期的論考!

選書日本中世史 1 武力による政治の誕生
講談社選書メチエ
歴史の見方が変わる!
選書日本中世史シリーズ 全5巻スタート
天皇から幕府へ。「文」から「武」へ。
中世は日本のヘゲモニーの大転換期だった。宮廷と幕府=2つの政権の並立から幕府中心の日本へ。日本史の大きな流れを分節する歴史の「構造」を解明し、移行の画期としての鎌倉幕府の意義を再検討する。

アテネ民主政 命をかけた八人の政治家
講談社選書メチエ
人物が語る古代アテネ民主政の実像。最大級の名誉と弾劾裁判による死罪、しかも無給。にもかかわらず彼らはなぜ政治家を目指したのか? 生の軌跡を追うことで見えてくる、古代ギリシャ精神の真髄!
数多くの市民が直接政治に携わり、特定の個人に権力が長期間集中するのを極力避ける、という徹底した直接民主政を約180年にわたって安定持続させた古代ギリシア屈指のポリス、アテネ。成功すれば最大限の名誉を与えられ、ひとつ間違えば弾劾裁判で死罪になるという「緊張状態」にさらされながら、政治家であろうとした8人の男たち。その生の軌跡を追うことで見えてくる、古代ギリシア精神の真髄と民主政治の原点とは?
【目次】
はじめに──民主政最後の政治家の死
序 章 アテネ民主政という世界
第1章 僭主の香りする勇士 ミルティアデス
第2章 一匹狼の策士 テミストクレス
第3章 貴族のなかの貴族 キモン
第4章 最後のカリスマ指導者 ペリクレス
第6章 民主政復興の英雄 トラシュブロス
第7章 したたかな名将 イフィクラテス
第8章 反マケドニアの闘士 デモステネス
終 章 アテネ民主政とは何だったのか
主な参考文献
図版出典一覧
あとがき
関連年表
人名索引

海から見た日本人-海人で読む日本の歴史
講談社選書メチエ
日本は海人列島である。「単一的」な外見の下に重層する多彩な貌……「海」をキーワードに人類学・神話学・考古学などさまざまな分野の知見を学際的に綜合し、日本人の複合的構造性を解明する。従来の日本人論を一新する画期的論考!
【目次】
はじめに
序章 和洋洋折衷の島 小笠原から
第一章 ホモ・サピエンスと日本列島
1 人類の起源と最初の移動
2 日本人の起源論争
3 近年の見解
4 日本語の系譜
5 「日本人」をどう考えるか
第二章 海を越える黒い石と白い貝
1 人類の海上渡航
2 海を越える黒い石
3 日本列島と黒曜石
4 海を渡った貝
5 南太平洋のイモガイ製腕輪
6 旅というハビトゥス
第三章 海を渡ってきた稲
1 海を越えた稲
2 稲の遺伝子、ヒトの遺伝子
3 弥生時代の景観
4 倭の水人
5 倭人の心象風景
第四章 海人の比較考古学
1 海を越える人々
2 海人の民族考古学
3 日本古代の海人
4 海人という生き方
第五章 海を越える魂
1 魂を運ぶ舟
2 東南アジアにおける船のシンボリズム
3 海辺の聖地
4 星の航海士
5 儀礼としての航海
第六章 海人列島残照
1 海人列島
2 琉球から
3 海人文化ルネサンス
おわりに
引用文献
索引

洋服・散髪・脱刀 服制の明治維新
講談社選書メチエ
維新の立役者たちが本気で悩んだ“装い”の近代化。直垂を着たい老華族、刀を持ちたい士族、月代を剃れないことに戸惑う庶民たち……近代化を図る日本が自らの装いを確立するにいたるまでの維新の指導者たちの苦闘と統治される人々の混乱の跡を、国家による服装の制度「服制」という視点から辿る。
【目次】
序章
第一章 王政復古の服制
第二章 文明開化の服制
第三章 無視される服制
第四章 対立する服制
第五章 大日本帝国の服制
終章 「王政復古の服制」から「大日本帝国の服制」
あとがき
参考文献

完全解読 カント『純粋理性批判』
講談社選書メチエ
世界初のこころみ
超難解哲学書を原典に忠実に、かつ平易に解読
大好評、知の高峰を読み平らげるメチエ「完全解読」シリーズ第2弾。
古代ギリシア以来の哲学をコペルニクス的に転回し、近代哲学の礎を築いたカント三批判書の第1書。「物自体」「カテゴリー」「アンチノミー」などのキー概念を中心に、難解でなる著作の理路を徹底的かつ平易に解読する。

本居宣長『古事記伝』を読む 1
講談社選書メチエ
宣長はどのように『古事記』をつくりあげたか
最初から最後まですべて読む画期的試み!
誰もがその名は知っている本居宣長の大著『古事記伝』。しかし、全巻読み通した人はほとんどいないといっていいだろう。つまみ食い的に読んで彼の思想を語る前に、まず、細部まで精緻に読み抜こうではないか。とはいえ、宣長の注解は多岐・厖大にわたり、簡単に読み切れるものではない。本書は、現代の代表的『古事記』研究者が、その責任において、徹底的に、かつわかりやすく『古事記伝』全44巻を読み解いていく画期的なシリーズである。そこに浮かび上がってくる宣長の無類のおもしろさ、そして思想の核心とは──。