講談社学術文庫作品一覧

トロイア戦記
講談社学術文庫
『トロイア戦記』はホメーロスの『イーリアス』と『オデュッセイア』を架橋する壮大な長編叙事詩である。作者は3世紀のギリシャの詩人クイントゥス。『イーリアス』のあとを受け、アマゾーンの女王の華麗な活躍、戦争の端緒を開いた王子パリスの末路、木馬作戦の顛末、絶世の美女ヘレネーの数奇な運命等、魅力あふれる多数の挿話をちりばめつつ、トロイア崩壊までを描く。本邦初訳。

あるカトリック女性思想家の回想録
講談社学術文庫
ロシアのユダヤ人迫害を逃れ、フランスへ移住した哲学者で、詩人で、祈りの人、ライサ・マリタン。パリでの壮大な精神のドラマ、数々の出会いと友情──哲学者ベルクソン、画家ルオー、作家レオン・ブロワ。科学的実証主義万能の時代、人間存在の根源は何かをひたすら求め彷徨う、深く澄んだ魂をもつ1人の女性が、半生を回顧し、その懊悩(おうのう)の軌跡を美しい詩的文章で綴る。

栄西 喫茶養生記
講談社学術文庫
茶は養生の仙薬なり。延齢の妙術なり。
禅僧栄西が説く茶の効能
鎌倉時代、広い知識と行動力で、先進的知識人として活躍した栄西は、二度にわたり宋に入り、中国文化の摂取につとめた。そして、中国の禅院で行われていた飲茶の習慣を日本でも行うべく、当地で得た茶の実を建仁寺境内に植栽し、日本の茶の始祖になる。本書は、「養生の法」として喫茶を説いた茶書の古典。
●大きな文字で読みやすい

歎異抄
講談社学術文庫
悪人正機説や他力本願で知られる真宗の開祖・親鸞。危険思想視され烈しい弾圧にあいながらも、人々に受け入れられていった、その教えの本質とは何か。師の苦悩と信仰の極みを弟子の唯円が綴った聖典に詳細な語釈、現代語訳、丁寧な解説をほどこした。日本人の「こころ」を追究する著者の手でよみがえる流麗な文章に秘められた生命への深い思想性。
梅原学が探る日本人の「こころ」
親鸞の苦悩と信仰の極み
悪人正機説や他力本願で知られる真宗の開祖・親鸞。危険思想視され烈しい弾圧にあいながらも、人々に受け入れられていった、その教えの本質とは何か。師の苦悩と信仰の極みを弟子の唯円が綴った聖典に詳細な語釈、現代語訳、丁寧な解説をほどこした。日本人の「こころ」を追究する著者の手でよみがえる流麗な文章に秘められた生命への深い思想性。
●大きな文字で読みやすい

平家後抄(下)
講談社学術文庫
『平家物語』その後 清盛の血脈を追う
壇ノ浦での「平家滅亡」は虚構であった!
厳しい平家狩りの目をくぐり抜けてきた人びとにも、安穏の日はなかなか訪れない。しかし、勝者源氏は14世紀に到り亡びてしまう。平家の末流は、宗家、西洞院家、四条家などに繋り、以後の歴史の折々に大きな影響を与え続けてきた。詳細な資料調査と実地踏査によって明らかにされる『平家物語』その後。

巨大古墳 治水王と天皇陵
講談社学術文庫
5世紀ごろに数多く作られた巨大古墳。謎の多い誉田山(こんだやま)古墳(応神陵)、大山(だいせん)古墳(仁徳陵)など雄大な古墳が作られた時代の実態を、数々の発掘調査に携わった著者が鋭い史眼で解明し、さらに、多数の航空写真や図解によって、古墳時代・古代人からのメッセージを鳥瞰する。古代史ファン、研究者待望の書。

地震の社会史
講談社学術文庫
1855年、震度6の地震が百万都市江戸を襲った。安政大地震である。明日を見失った被災民は、生へ向う意志と復興への願いをこめて、地震鯰絵やかわら版に熱狂する。これら民衆のメッセージは、時空を越えて現代のわれわれにも何事かを訴えかけているに違いない。残された資料の中に災害史の新しい可能性を探る好著。

夢中問答集
講談社学術文庫
天龍寺を開山し、造園の妙を各地に施した、悟達明眼の夢窓国師は、北条家、足利家、後醍醐天皇からも深く帰依され、世に7朝の帝師と仰がれた。在俗の政治家、足利尊氏の弟直義(ただよし)の、信心の基本、大乗の慈悲、坐禅と学問などの問いに答えて、欲心を捨てることの大切さと仏道の要諦を指し示す。無礙自在の禅者の声が、時空を超えて響きわたる。(講談社学術文庫)
天龍寺を開山し、造園の妙を各地に施した、悟達明眼の夢窓国師は、北条家、足利家、後醍醐天皇からも深く帰依され、世に7朝の帝師と仰がれた。在俗の政治家、足利尊氏の弟直義(ただよし)の、信心の基本、大乗の慈悲、坐禅と学問などの問いに答えて、欲心を捨てることの大切さと仏道の要諦を指し示す。無礙自在の禅者の声が、時空を超えて響きわたる。

恋愛と贅沢と資本主義
講談社学術文庫
著者はM・ウェーバーと並び称された経済史家である。ウェーバーが資本主義成立の要因をプロテスタンティズムの禁欲的倫理に求めたのに対し、著者は贅沢こそそのひとつと結論づけた。贅沢の背景には女性がいて、贅沢は姦通や蓄妾、売春と深く結びついていたというのである。かくて著者は断ずる。「非合法的恋愛の合法的な子供である奢侈は、資本主義を生み落とすことになった」と。(講談社学術文庫)
著者はM・ウェーバーと並び称された経済史家である。ウェーバーが資本主義成立の要因をプロテスタンティズムの禁欲的倫理に求めたのに対し、著者は贅沢こそそのひとつと結論づけた。贅沢の背景には女性がいて、贅沢は姦通や蓄妾、売春と深く結びついていたというのである。かくて著者は断ずる。「非合法的恋愛の合法的な子供である奢侈は、資本主義を生み落とすことになった」と。

道元との対話
講談社学術文庫
アジア各地の民族の社会・文化・宗教を調査し、その多様性の底にひそむものを探究してきた著者は、『正法眼蔵』を常に傍らに置き、道元に対面してきた。北ラオス、パ・タン村のベッドに夜ごと横たわるとき、闇の中で自分と大地が一体となり、それを受けとめてくれる掌の存在を感じる……。著者独特の言葉で語る道元の真の姿。

論理分析哲学
講談社学術文庫
概念の厳密さを求める努力は論理分析哲学を生んだ。アリストテレス、フレーゲ、ヴィトゲンシュタインは、言語や論理について、いかに考えてきたか。実存主義・新スコラ学・現象学・マルクス主義と並ぶ現代哲学の一大潮流であり、近代科学の発展と共に歩み、人類の未来へ確実な進路を見出す方法でもある論理分析哲学はどんな思想かを分かりやすく紹介する。

倫理学ノート
講談社学術文庫
ケインズ、ロレンス、ムアたちに代表される20世紀前半以来の英語圏倫理学の伝統──。その“欺瞞”に異を唱える著者は、メタ倫理学や新厚生経済学の不毛を断罪し、自然の弁証法を通して「新しい時代の功利主義」を提唱する。本書は、後期清水社会学を代表する名著であり、新たな倫理学を思索し構築するための出発点である。

世界宗教事典
講談社学術文庫
現代を読み解くには世界宗教の基礎知識が不可欠である。中東のイスラム教徒とユダヤ教徒、イスラム教のスンニ派とシーア派、インドのヒンズー教徒とシク教徒等、宗教紛争の根にあるものとは何か?本書は、世界の主要な宗教・宗派、教典、宗教史上の事件や運動等を地域別、系統別に整理し、とくに日本との関連に留意しながら解説する。講談社学術文庫『日本宗教事典』の姉妹篇。

平家後抄(上)
講談社学術文庫
平家は壇ノ浦で滅んだのか?『平家物語』その後
女系を通じ現代にまで繋がる平家血流の研究
平維盛の子、平家の最後の嫡流六代の斬刑により、「平家は永く絶えにけり」と『平家物語』は結ぶ。しかし、壇ノ浦の惨敗の後、都に帰還した平家の女性(にょしょう)たちの血は、皇族、貴族の中に脈々と生き続け、実に現代にまで続いていることを忘れてはならない。北山の准后藤原貞子に仮託して、壇ノ浦以後の平家の動静を克明にたどる名著。

ゲシュタポ・狂気の歴史
講談社学術文庫
数百万の生命を奪い、魂を苦悶させたナチ権力の中枢・ゲシュタポ。それは暴力と情報が結合した「装置」だった。この〈悪魔の機械〉は、どのように誕生し暴走したのか。そして、その力の源はどこにあったのか。戦後、ナチの戦犯・協力者取り調べの任にあたったフランス人警察官が、膨大な資料と証言をとおして全欧州を巻き込んだ狂気の実像を描く、異色の人間研究。
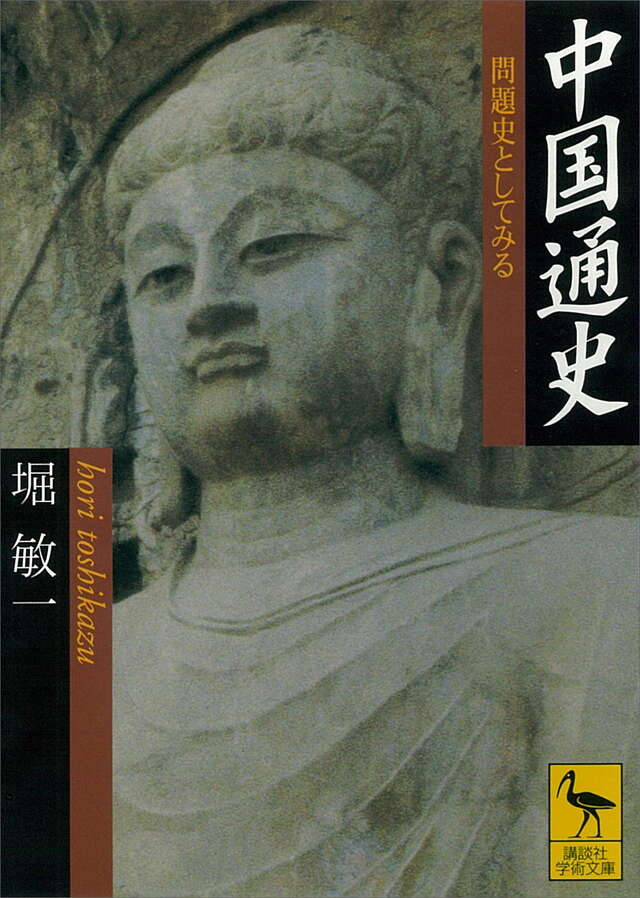
中国通史 問題史としてみる
講談社学術文庫
歴史をみるうえで、なぜその事実が選択されたのか、何が大切で、どういう点が問題になるのか等に意を注ぎ、中国文明の誕生から現代までの歴史を綿密に辿る。江南の河姆渡(かぼと)遺跡や四川の三星堆(さんせいたい)遺跡など近年の新しい発掘と研究の著しい成果を踏まえ、民衆の歴史や思想・文化にも注意を払い、総合的観点から中国史の全体像を描き出した意欲作。(講談社学術文庫)
歴史をみるうえで、なぜその事実が選択されたのか、何が大切で、どういう点が問題になるのか等に意を注ぎ、中国文明の誕生から現代までの歴史を綿密に辿る。江南の河姆渡(かぼと)遺跡や四川の三星堆(さんせいたい)遺跡など近年の新しい発掘と研究の著しい成果を踏まえ、民衆の歴史や思想・文化にも注意を払い、総合的観点から中国史の全体像を描き出した意欲作。文庫オリジナル。

平戸オランダ商館日記 近世外交の確立
講談社学術文庫
1609年、平戸に商館が開かれ、日蘭交渉は始まった。キリスト教布教を目的とせず商人に徹したオランダは対日貿易の覇者となるが、やがて出島に囲い込まれていく。将軍・閣老らの肉声を伝える貴重な史料であり、唯一自由を享受したオランダ人ならではの目で日本の動静を鋭く観察した記録でもある日記を中心に近世日本の外交政策確立過程を描く。
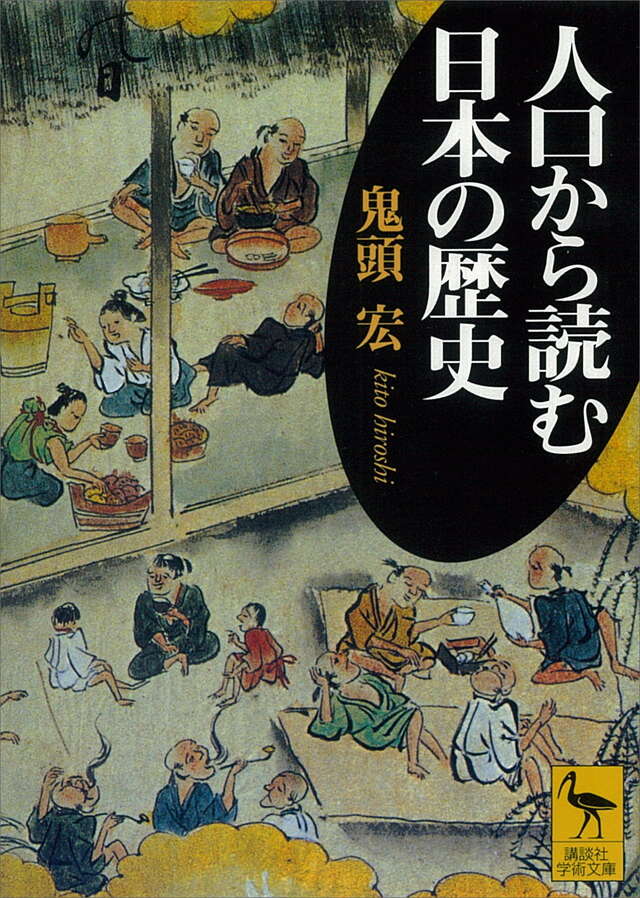
人口から読む日本の歴史
講談社学術文庫
増加と停滞を繰り返す、4つの大きな波を示しつつ、1万年にわたり増え続けた日本の人口。そのダイナミズムを歴史人口学によって分析し、また人々の暮らしの変容と人生をいきいきと描き出す。近代以降の文明システムのあり方そのものが問われ、時代は大きな転換期にさしかかった。その大変動のなか少子高齢化社会を迎えるわれわれが進む道とは何か。
【目次】
第1章 縄文サイクル
第2章 稲作農耕国家の成立と人口
第3章 経済社会化と第三の波
第4章 江戸時代人の結婚と出産
第5章 江戸時代の死亡と寿命
第6章 人口調節機構
第7章 工業化と第四の波
終章 日本人口の二十一世紀

葛城と古代国家
講談社学術文庫
統一王朝大和朝廷が成立する以前、大和には倭国(やまとのくに)と葛城国(かづらきのくに)が存在していた。百済からの渡来人、蘇我氏とその一族が定着した地、海外の新文化の流入路で数多くの古墳が残る葛城は、どのような国だったのだろうか。考古学の成果と諸史料の綿密な検討によって、その支配の実態と大和との関係を系統的に解明する。
《付》河内王朝論批判

帰ってきたファーブル
講談社学術文庫
ファーブルは個々の虫たちの詳細な観察によって、生命の営みの不可思議を探求した。多様な種の1つにすぎない人間の本質は、進化論の呪縛の中で生物を記号化し、遺伝子やホルモンを道具化した今日の生物学ではなく、ファーブルの視点によってのみ捉えられるだろう。博物学(ナチュラル・ヒストリー)的アプローチの復権を主張した名著。