講談社選書メチエ作品一覧
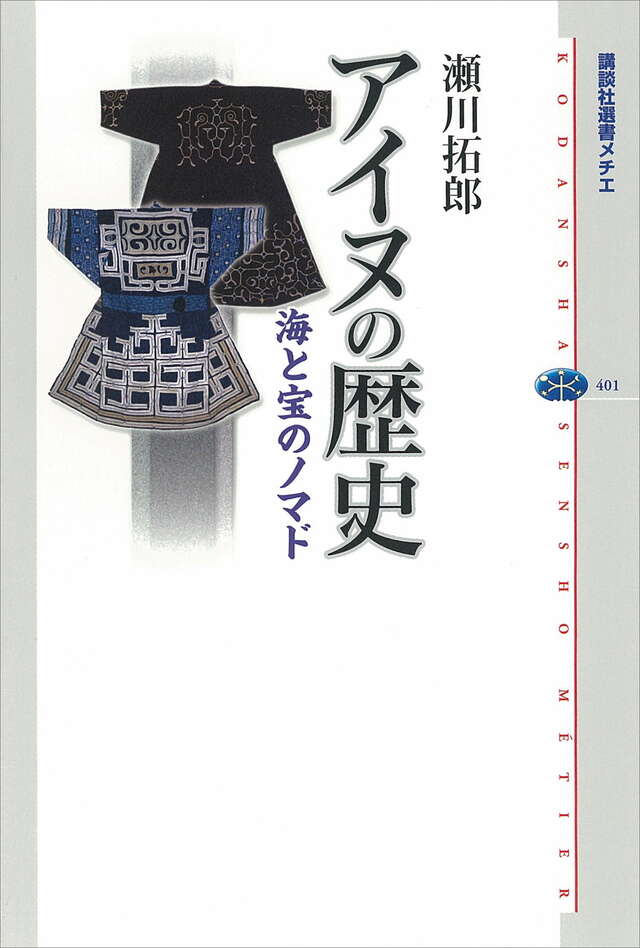
アイヌの歴史 海と宝のノマド
講談社選書メチエ
宝を求め、サハリン・アムール川流域に進出する戦うアイヌ。激しい格差、サケ漁をめぐる内部対立、「日本」との交渉――社会の矛盾に悩むアイヌ。北の縄文から近世まで、常識を覆すダイナミックな「進化と変容」。(講談社選書メチエ)
常識を覆す、ダイナミックなアイヌ像を提示。宝を求め、サハリンで戦うアイヌ。格差社会に悩むアイヌ。北の縄文から近世まで、異文化との交流・対立と通じダイナミックに展開する北の採集民族のリアルな歴史。
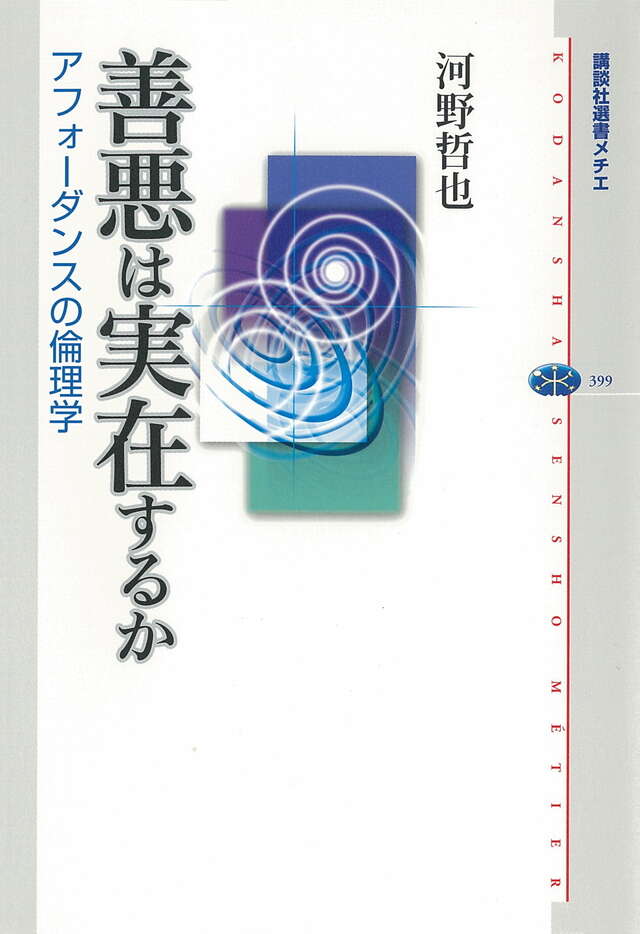
善悪は実在するか アフォーダンスの倫理学
講談社選書メチエ
「主観」の呪縛から倫理を解放する試み! 哲学と心理学に革命をもたらしたアフォーダンス理論。その知見をもとに「意味や価値、善悪は主観的なもの」という現代の常識を乗り越え、道徳の根源を見つめ直す。
環境の中の存在という視点をもって、近代以降の哲学、心理学で主流をなしてきた認識論と存在論に再考を促すほどの大きなインパクトを与えたアフォーダンス理論。その革新性は、価値や意味を主観の中の観念のようなものから、環境に実在するものとして捉えなおすという、大きな転回を倫理学に引き起こすものでもあった。「善悪は主観的なもの」という現代の常識を乗り越え、道徳の根源を見つめなおす試みが、いまここに始まる!
【目次】
序論 個別の存在を肯定する哲学へ
私たちはカクテルについて語ることができるか/世界から切り離された主観/「郵便ポスト」は実在しない?/主観主義とプラトン主義の結託/近代における法的なものの優位/ほか
第一章 アフォーダンス──実在する価値と意味
カクテルを語る心理学/アフォーダンスという「環境の特性」/アフォーダンスの特徴/アフォーダンスと出来事/出来事の知覚、出来事の存在論/ほか
第二章 生命の規範と社会の規範 53
事実と価値は本当に別のものか?/個人の欲求と規範の対立/生命は規範を含んでいる/平均と異常/正常と病理/社会的規範という紛い物/社会は生物に似ていない/逸脱と異常に敏感な社会/ルールに従っていること/なぜルールが規範になるのか/規範が問題になるとき/法の不条理な特徴/本当の問題
第三章 道徳的価値の実在性
道徳の相対主義/主観主義の問題点/道徳の実在論と反実在論/主観とは誰の主観のことなのか?/道徳の問題となる行為の特徴/誰かの行為が、誰かに影響を与えること/出来事と行為の実在/ほか
第四章 道徳の規範性はどこからくるのか
共感と道徳の認知科学/他人を理解することの身体性/入り組み合った私と他者/ギブソンの社会─道徳心理学/学習理論による説明の矛盾/「~すべし」はいかにして成り立つか/動物の道徳性──利他行動と互酬性/原初的な正義のかたち/呼びかけと応答の互酬/なぜ「人」を殺してはならないのか/ほか
第五章 法化されない道徳と「直接の共同体」
法的倫理の陥穽と徳倫理学/ケアの倫理学/ケアにおける人間関係/具体的な他者/サド侯爵の共和国/田山花袋に見る利己主義の限界/「直接の共同体」の可能性/犯罪被害者たちの不満/ほか
註
あとがき
索引
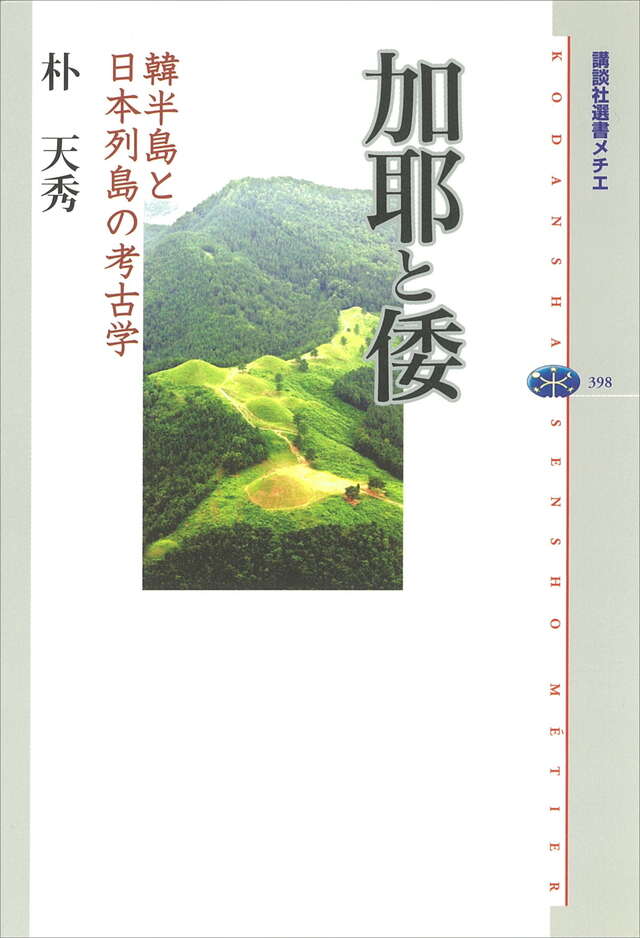
加耶と倭 韓半島と日本列島の考古学
講談社選書メチエ
謎多き古代日韓関係を韓半島側から検証する
任那日本府はなかった。韓半島に存在する倭人前方後円墳の意義とは。藤ノ木古墳になぜ新羅産馬具が副葬されたのか。韓日考古学の成果を総合し、加耶から百済・新羅に至る古代韓日交渉史を新たな視点で読み直す画期的論考。
【目次】
第1章 古代韓日交渉史を見なおす
1 古代の韓日交渉史への問題提起
2 古代韓日交渉史研究の新しい地平
3 新たな古代韓日交渉史へ
第2章 加耶と倭――古代韓日交渉の始まり
1 金官加耶と倭
2 阿羅加耶と倭
3 小加耶と倭
4 大加耶と倭
第3章 「任那日本府」はなかった――百済と倭
1 在地首長か倭人か
2 前方後円墳はいつ造られたか
3 個々の前方後円墳の分析
4 被葬者はだれか
5 倭人の役割はなにか
6 なぜ倭人の前方後円墳が造られたのか
第4章 藤ノ木古墳馬具の出自はどこか――新羅と倭
1 新羅と倭は敵対的ではなかった
2 日本列島の新羅文物
3 新羅地域の日本列島文物
4 頻繁な交渉はなぜ起こったか
終章 古代韓日交渉をどう見るか
註
カラー図版出典
本文図版出典
あとがき
索引
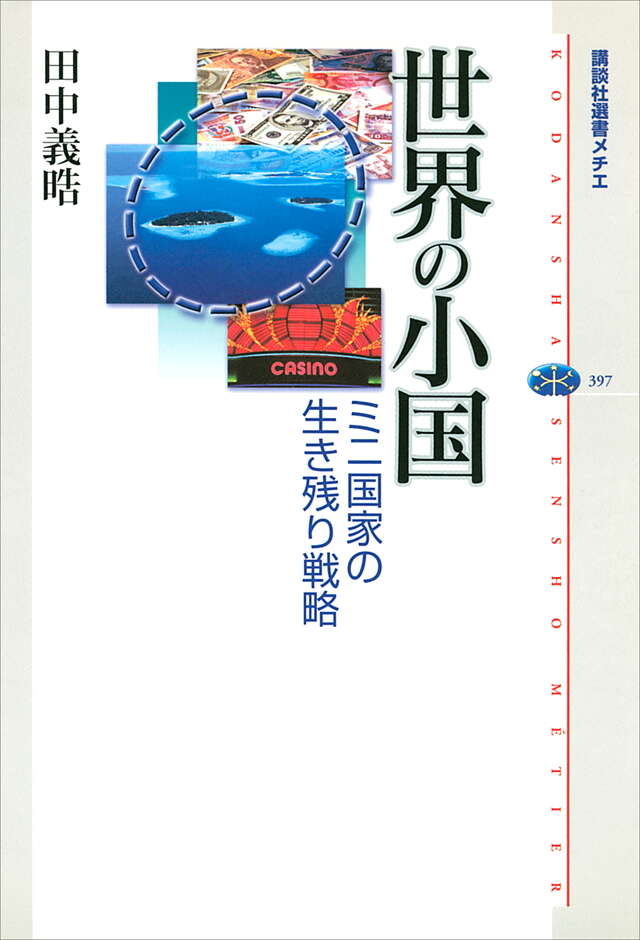
世界の小国 ミニ国家の生き残り戦略
講談社選書メチエ
したたかな外交戦略と個性的な経済政策。大国主導の国際社会を生き抜く術とは?
ツバルのドメイン名ビジネス、バハマのオフショア金融センター、ルクセンブルクの欧州外交戦略……。大国ではありえない個性的でしたたかな国家運営をする小さな国々。最高の政治的贅沢か、それとも国際社会のお荷物なのか? 世界の国家数の2割強を占め、今後も増え続けるであろう小国の魅力と、小ささゆえの有利性と不利性を国際関係論のエキスパートが論考する。
【目次】
はじめに 新たな国際的プレーヤー
今、なぜ小国なのか/小国の定義
第1章 ツバルという国
週二便の国際線/独立への道/依存経済/ドメイン名ビジネス
第2章 小国の系譜
「小面積の共和国」という理想/古代都市国家の興亡/中世・近世ヨーロッパの小国家群/第三世界との共通点
第3章 小国の誕生
「世界最古の共和国」サンマリノ/激動のヨーロッパ史の中で/「植民地独立付与宣言」を追い風に/国連が「産婆役」/主権国家といえるのか/民族自決権の功罪
第4章 国際政治のキャスティング・ボート
「世界の良心」/京都議定書をめぐる対立/IWCをハイジャック/援助外交のコスト・パフォーマンス/共産主義を崩壊させたバチカン/保守的教義への批判
第5章 グローバリゼーションという逆説
世界のオフショア金融センターとして/「タックス・ヘイヴン」バハマ/ダーティー・マネーの温床?/タックス・ヘイヴンvs.経済協力開発機構
第6章 太平洋島嶼国をめぐる国際政治
「不穏な太平洋」/米ソ角逐を手玉に/中・台の援助競争/フィジーをゆるがせた民族主義/ソロモン諸島の「国家破綻」/変化した安全保障のパラダイム
第7章 カリブ海と太平洋の小島嶼経済
両地域の類似点、相違点/経済困難を抱える太平洋の小島嶼国/オセアニア島嶼経済の四類型/より発展したカリブ海地域/「3S」に賭ける/地域統合でさらなる発展
第8章 欧州の伝統的小国家群
経済オリンピックの勝者/成功の背景/モナコのジレンマ/リヒテンシュタインとサンマリノの経済戦略/「小国性」を武器にするルクセンブルク
第9章 アラブの小さな首長国
カタールとバーレーン/「中東のCNN」アルジャジーラ/アメリカとサウジアラビアのはざまで/「レンティア国家」/岐路に立つバーレーン
第10章 アフリカ大陸の六つのミニ途上国
小さな最貧国/「富める国と貧しい民」赤道ギニア/観光立国セーシェル
終 章 小国が拓く新時代
政治的ダーウィニズムをこえて/小国から見た世界/不安定要因か、社会の木鐸か/日本との関係
あとがき
参考文献
小国案内

近代日本の右翼思想
講談社選書メチエ
躓きの石としての天皇 超克されざる「近代」
――近代日本のパラドクス
革命への赤き心は、なにゆえ脱臼され、無限の現状肯定へと転化されなければならないのか。躓きの石としての天皇、超克されざる「近代」――北一輝から蓑田胸喜まで、西田幾多郎から長谷川如是閑まで、大正・昭和前期の思想家たちを巻き込み、総無責任化、無思想化へと雪崩を打って向かってゆく、近代日本思想極北への歩みを描く。
[本書の内容]
●「超―国家主義」と「超国家―主義」
●万世一系と「永遠の今」
●動と静の逆ユートピア
●「口舌の徒」安岡正篤
●西田幾多郎の「慰安の途」
●アンポンタン・ポカン君の思想
●現人神

「弱い父」ヨセフ キリスト教における父権と父性
講談社選書メチエ
父は弱い だが父は強い
父の「原型」から21世紀の父親像を考える
受け入れ、養う。それが父親の役割だ。望まずしてイエス・キリストの父となった聖ヨセフ。聖書にはほとんど言及のなかった1人の「父」が、すべての「父」のモデルになったのはなぜか。ヨセフ像の変遷をたどりながら、現代に必要とされている真の父の「ありかた」を考える。
【目次】
はじめに
序章 可能性のヨセフ
第一章 ヨセフの生涯
第二章 観想のヨセフ 聖フランチェスコの馬小屋
第三章 政治のヨセフ
第四章 ヨセフが父になったわけ
第五章 不思議のヨセフ
第六章 ヨセフの二一世紀
終章 「強い父」と聖ヨセフ
おわりに
主要参考文献
索引

空の実践 ブッディスト・セオロジー(4)
講談社選書メチエ
宗教の実践の意味とは何か
世界的碩学による大好評講義シリーズ第4弾
仏教の中核思想「空」とは何か。自己否定とそれを通してのよみがえりという「空」の実践のプロセスから、実践行為としての仏教の本質を考究する、碩学渾身の思考。
【目次】
はじめに
第一章 空の実践
第二章 空と縁起
第三章 空性と自性
第四章 行く人は行くか
第五章 言葉を超える
第六章 『般若心経』における空
第七章 空の実践と真言
第八章 空の実践と三身仏
第九章 実践の行程──井上円了のパラダイム
第一〇章 よみがえる世界──空海におけるマンダラ
第一一章 空の実践の二方向
索引

古代メソアメリカ文明 マヤ・テオティワカン・アステカ
講談社選書メチエ
知られざる「石器の都市文明」の全貌
世界は四大文明だけではなかった
ゼロの概念を発明し、文字や天文学を発達させたマヤ文明。山上都市モンテ・アルバン。ローマに匹敵する国際都市テオティワカン。メソアメリカ最大の王国アステカ。世界は四大文明だけではなかった。日本人にはなじみの薄い「石器の都市文明」の全貌を明らかにし、文明とは何かを考察する。知られざる「石器の都市文明」がわかる決定版!
【目次】
序章 世界六大文明としてのメソアメリカ文明
1 「最初のアメリカ人」と世界の食文化革命
2 「世界四大文明」から「世界六大文明」へ
第一章 世界六大文明のなかの「石器の都市文明」
1 もっとも洗練された「石器の都市文明」
2 四大文明史観を覆す
3 「新石器革命」はなかった
第二章 メソアメリカ最初の文明=オルメカ文明
1 オルメカ文明の起源
2 遠距離交換網とオルメカ美術様式
3 オルメカ文明と文字
第三章 究極の石器の都市文明=マヤ文明
1 ゼロを発明した文明
2 マヤ文明の起源 先古典期マヤ文明
3 古典期マヤ文明と初期国家群の発達
4 古典期マヤ都市の盛衰 戦争と権力闘争
第四章 メソアメリカ最古の都市を生んだサポテカ文明
1 メソアメリカ最古の都市 モンテ・アルバンの起源
2 サポテカ国家の発達
3 サポテカ文明の黄金時代
第五章 古典期最大の国際都市=テオティワカン文明
1 テオティワカンの起源
2 国際都市テオティワカンと古典期メソアメリカ
第六章 群雄割拠のなかのトルテカ文明
1 トルテカ文明とメキシコ中央高地
2 発達するメソアメリカ遠距離交換網 古典期後期・終末期と後古典期前期
第七章 アステカ文明と後古典期後期メソアメリカ
1 アステカ王国と首都テノチティトラン
2 後古典期後期のメソアメリカ
終章 メソアメリカ文明とは何か
1 「未完の征服」と現在進行系の文化
2 文明とは何か
参考文献
あとがき
索引

日中戦争下の日本
講談社選書メチエ
自由主義から全体主義へ。国際協調から地域主義へ。1930年代、社会システムの不調から生じた日中戦争。なぜ政党への期待が大政翼賛会を生んだのか? 労働者や農民たちは戦争に何を託したのか? 戦時下日本の知られざる「自画像」を明かす。(講談社選書メチエ)
デモクラシーとしての大政翼賛会誕生の真実。日中戦争とは何だったのか。戦争景気で潤う銃後経済。社会平準化を志向する兵士たち。当時の社会システム不調の原因を探りつつ、戦前日本の自画像を捉え直す一冊。

誓いの精神史 中世ヨーロッパの<ことば>と<こころ>
講談社選書メチエ
言われた言葉には魔が宿る
誓いに込められた中世人の世界観を読み解く
誓いの言葉はなぜ間違えてはいけないのか。なぜ文書よりも言葉が重視されたのか。決闘の勝ち負けによって真偽が定まり、目撃していなくても事件の証人になることができる、その根拠はどこにあるのか。西洋中世の特異な習俗から、中世人の「こころ」に迫る。
【目次】
序
第一章 ことばの射程
ことばと文化/文字の文化と声の文化/証しのかたち/この証書が目に入らぬか/記憶に対する疑い/記憶から記録へ?/声の権威/正義はつくられるもの?/ことばと身振り/「誓い」はからだを介して行なわれる/ことばと意図のせめぎあい/いまなぜ「誓い」なのか
第二章 「誓い」の場
人を試す「誓い」/神明裁判/証明手段としての「誓い」/決闘/よろめき夫人!?
第三章 人を信じる「誓い」
信頼を基盤とする社会/雪冤宣誓/「誓い」だけで犯罪は立証可能になる/宣誓補助人と証人──名誉にかけて誓う/合意形成の場/讒訴に対する不信感/『狐物語』/勝敗より和解を/「誓い」から証言へ/なくならない決闘/『最後の決闘』/正義は決闘では決められない
第四章 人を縛る「誓い」
言葉の呪縛力/『黄金伝説』/偽誓──意図はどこに?/ブルヒャルトの『教令集』/「誓い」の解除をめぐる争い──叙任権闘争/中世の秩序をゆるがす大問題/形式から意図へ/「誓い」の「内面化」/異端審問──裁かれた乙女、ジャンヌ・ダルクの断罪/「誓い」の変容を象徴する事件
第五章 「誓い」の位相
「誓い」の本質は何か/封建制の「誓い」/「誓い」の絆/『帝国年代記』/強化される「誓い」の力/「誓い」と教会/「誓い」の禁止/二種類の「誓い」/相互盟約/ザクセン戦争/神の平和/誓われた平和/ラントフリーデ/平和令の変質/「誓い」の義務/「誓い」のかたち/臣従の誓い/「誓い」からの脱却/「誓い」の拒絶・回避/「誓い」のヒエラルヒー/代行宣誓──王の不可侵性の構築/変化のきざし/戴冠式の「誓い」/テ・デウム賛歌
結び
註
あとがき
索引

ホワイトヘッドの哲学
講談社選書メチエ
超難解な思考をあざやかに解説! ホワイトヘッドの世紀は来るか!?
本書は、ホワイトヘッドという哲学者のひじょうに偏った入門書である。読者の方々が、ホワイトヘッド自身の本を手にとってみようか、という気になられることだけを目指した。他意(?)はない。わかりやすさを重視したので、かなり強引なところもあると思う。特に入門篇は、こちらの興味にぐっとひきつけて書いた。淡々と説明だけをするというのは、どうしても性にあわない。それぞれが、1話完結のエッセイとしても読めるように工夫したつもりだ。上手くいったかどうかは、保証の限りではない。もちろん全体として一貫した流れはある。いってみれば、本書全体が、ホワイトヘッドが考えたこの宇宙とおなじあり方、つまり【非連続の連続】になっているといえ・・・といいのだが。<[まえがき]より>
【目次】
まえがき
第1章 入門以前 ホワイトヘッド哲学の見取り図
1 ホワイトヘッドの世紀
2 出会い
3 なぜかくも難解なのか
4 哲学は詩である
5 【こと】と【もの】
6 ひとつの出来事とはなにか
7 電磁気的な時代
8 相対論と量子論
9 生きいきとした自然
10 具体的なもの
第2章 入門篇 ホワイトヘッド哲学そのもの
1 唯一無二のそれ(actual entity)
2 〈わたし〉ということ
3 非連続の連続
4 かかわり方(prehension)
5 知るための手がかり(eternal object)
6 フィーリングの海
7 物質と記憶
8 象徴によるつながり(symbolic reference)
9 自己超越体(superject)
10 一元、二元、多元
11 神と世界
第3章 応用篇 エポック的時間とはなにか
1 エポックとはなにか
2 純粋持続
3 刹那滅
4 エポック的時間
あとがき

トクヴィル 平等と不平等の理論家
講談社選書メチエ
「デモクラシーこそは歴史の未来である」。誕生間もないアメリカ社会にトクヴィルが見いだしたのは、合衆国という特殊性を超えた、歴史の「必然」としての平等化だった。「平等化」をキーワードに、その思想の今日的意義を甦らせる。第29回サントリー学芸賞〈思想・歴史部門〉受賞。(講談社選書メチエ)
デモクラシーの理論家の新たな可能性を探るデモクラシーこそは歴史の未来である。誕生間もないアメリカ社会にトクヴィルが見いだしたものは何か。平等化をキーワードにその思想の今日性を浮き彫りにする。
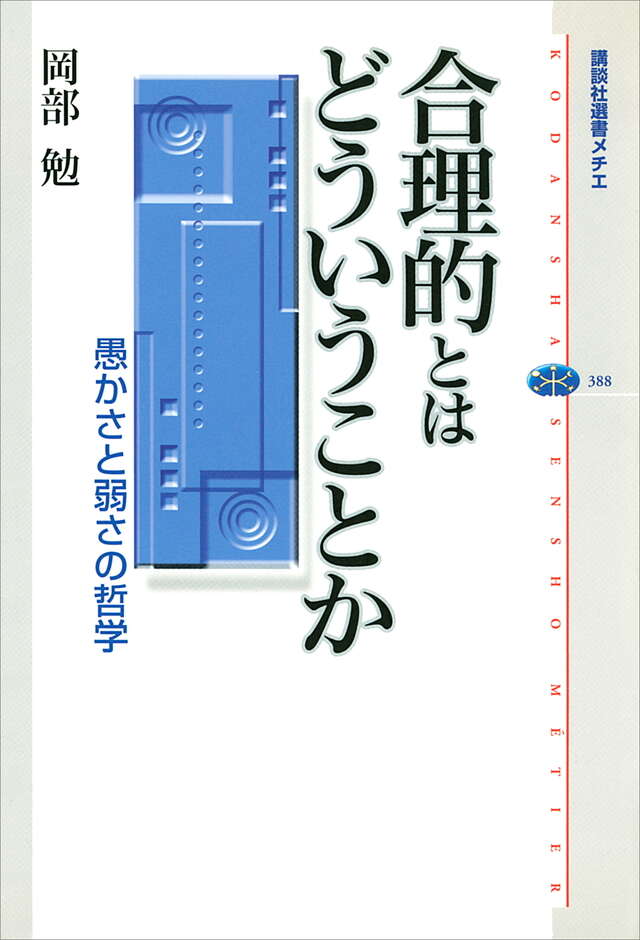
合理的とはどういうことか 愚かさと弱さの哲学
講談社選書メチエ
私たちは本当に“理性的存在”か?
なぜ私たちは、不合理な行動をしたり、意志の弱さや愚かさを見せたりしてしまうのか。それらの行為は「理性」に反したものなのだろうか。この問いから、人間であるという、そのあり方の本質が見えてくる。進化の歴史から日常的な問題まで幅広いスケールで繰り広げる「合理的である」ことをめぐる思考の冒険!
【目次】
序章 不合理な存在
日常の合理・不合理という問題/社会性と計画性/犯罪と推理/人間の愚かさと弱さ/人間性の表現/用語の説明
第一章 人間の不合理・愚かさ・弱さ
1 意志の弱さと行為の選択
自己決定という問題/意志の弱さと規範性/合理性の要求/人のあり方/基礎的合理性と規範的合理性/合理性の能力の喪失/可能性と現実性
2 こころの仕組み
価値と目的の生成/意識の必要性/行為の選択装置/感情と理性の対立図式/感情と欲求のシステム/感情の役割と儀式/感情と象徴能力
3 人間性の成熟
理性の起源/目的の実現/意志の弱さと選択された行為/成熟の三つの段階
第二章 人間だけが不合理であり得る理由
1 人間性の起源
遺伝子的な仕組み/人間になる仕組み/人間と動物の連続と不連続/理性的存在/言語と理性
2 不合理性の源泉
BBQとサバンナの風景/自然発生的な小集団社会/言語の役割/集団維持システム/言語の発達/連帯と協力
第三章 不合理・愚かさ・弱さと常識の不寛容
1 私たちが求める合理性
合理的な根拠/公正さの要求/ソクラテスの問題/意見の収斂/ソクラテスのジレンマ
2 プロフェッショナリズム
専門家モデル/認知主義者/道徳的葛藤/合理的解決/自発的能力/技術的知識と合理性
3 アマチュアリズム
自然の制約/自然言語/洗練された形而上学者/秘密を解く鍵/変更を可能にする仕組み/規則に従う/推論の一般性/日常の推論
第四章 人間の自然・不自然と不合理
1 自然・不自然・不合理
人間の自然/自然主義/第二の自然/活動・行動・行為/人間に固有の活動/身体的条件/行為の記述と評価と説明
2 自然的世界と価値の世界
反自然主義/構成主義の考え方/複数の自然言語/言語使用の正しさ/外的制約/幸福の追求/反実在論/実在論の可能性/愚かな生
註
参考文献
あとがき
索引

未完のレーニン 〈力〉の思想を読む
講談社選書メチエ
中沢新一氏推薦!
この輝くような若い日本の知性は、死せるレーニンを灰の中から立ち上がらせようと試みたのだった。ゾンビではない。失敗に帰した自らの企ての廃墟に佇みながら、ここに創造された21世紀のレーニンは、永遠に続く闘争への道を、ふたたび歩みだそうとしているかのように見える。素っ気ない手つきで差し出されたこの本が、世界へのまたとない贈り物であったことにみんなが気づくまで、そんなに時間はかかるまい。
資本主義の「外部」とは? 革命観のコペルニクス的転回とは? 『国家と革命』、『何をなすべきか?』という2つのテクストから立ち現れる、「リアルなもの」の探求者の思考の軌跡。資本主義の純粋化が進む現在、レーニンという思想史上の事件を捉え直す。

東大駒場連続講義 知の遠近法(Perspectiva)
講談社選書メチエ
「ものの見方」を考える 人気講義録第4弾
<東京大学比較日本文化論テーマ講義>
●ペルスペクティーヴァの誕生(ヘルマン・ゴチェフスキ)
●宇宙の地図づくり(船渡陽子)
●遠近法の作図理論の発展・応用・克服(加藤道夫)
●西洋近代絵画におけるパースペクティヴの変容――フランス印象派のパラダイム転換(三浦篤)
●都市写真におけるニュー・ヴィジョン――モイ・ヴェール『パリ』をめぐって(今橋映子)
●音を見る――音楽への視覚的ペルスペクティーヴァ(ヘルマン・ゴチェフスキ)
●音楽についてのペルスペクティーヴァ(徳丸吉彦)
●小説のパースペクティヴ(菅原克也)
●ドイツ・ロマン派が切り開いた世界――多様なる遠近法(池田信雄)
●文芸批評とパースペクティヴ(井上健)
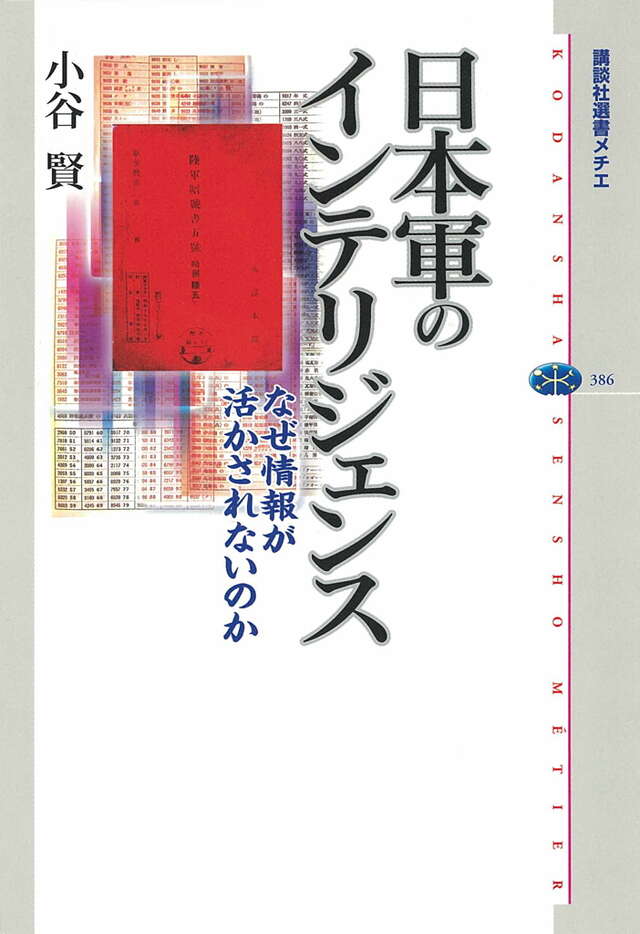
日本軍のインテリジェンス なぜ情報が活かされないのか
講談社選書メチエ
暗号解読など優れたインフォメーション解読能力を持ちながら、なぜ日本軍は情報戦に敗れたか。「作戦重視、情報軽視」「長期的視野の欠如」「セクショナリズム」。日本軍最大の弱点はインテリジェンス意識の欠如にあった。インテリジェンスをキーワードに日本的風土の宿痾に迫る。第16回山本七平賞奨励賞受賞作。(講談社選書メチエ)
日本はなぜ負けたのか。必敗の原理を探る。「作戦重視、情報軽視」「長期的視野の欠如」「セクショナリズム」。日本軍最大の弱点は情報戦にあった。インテリジェンスをキーワードに日本的風土の宿痾に迫る。

戦場に舞ったビラ 伝単で読み直す太平洋戦争
講談社選書メチエ
「君達の指導者は嘘つきだ!」
「馬鹿共眼ヲ醒マセ」
兵たちの太平洋戦争
「死戦を越えて誤戦となり」、「日海空軍は何処へ行つたのだらうか」、「日本降伏せり」――。太平洋戦争で撒かれた無数の伝単=宣伝ビラ。ビルマで、フィリピンで、沖縄で兵士は伝単に何を思ったか? 日米「情報戦」の実態を分析しつつ、兵それぞれにとっての「戦争」を明らかにする。
【目次】
はじめに
第一章 「蒋介石最後的運命到了」 日中戦争
第二章 「馬鹿共眼ヲ醒マセ」 日本の進撃と米軍の反攻
第三章 “ISLAND OF DECEIT” ニューギニアの戦い
第四章 「身ヲモッテ太平洋ノ防波堤タラン」 マリアナ諸島の失陥
第五章 「死戦を越えて誤戦となる」 ビルマ
第六章 「来る日の悶へ」 フィリピン戦1
第七章 「砲弾悪魔の如く将君達を見出して殺す」フィリピン戦2
第八章 「日本が老人と女子供ばかりの国となってもよいか」 本土空襲・沖縄
第九章 「大東亜戦争は遂に終了致しました」 敗戦の諸相
おわりに
図版一覧
参考文献一覧
あとがき

仏とは何か ブッディスト・セオロジー(3)
講談社選書メチエ
宗教の本質を問う
世界的碩学による大好評講義シリーズ第3弾
あらゆる宗教の根源存在である「聖なるもの」は、仏教においてどのような姿でイメージされたのか。儀礼をキーワードに、仏・菩薩と人間との関わりかたの具体的なプロセスを通じて、いよいよ仏の本質へと迫る。
【目次】
はじめに
第一章 仏のすがた
第二章 仏への行為
第三章 ヴェーダ祭式ホーマ
第四章 ブッダの涅槃
第五章 仏塔の意味
第六章 プージャー│宗教行為の基本型
第七章 ジャータカ物語と仏の三身
第八章 大乗の仏たち│阿弥陀と大日
第九章 護摩│儀礼の内化
第一〇章 浄土とマンダラ
索引

聖徳太子の歴史学 記憶と創造の一四〇〇年
講談社選書メチエ
「聖徳太子」はいかにつくられ、変容してきたか?
「日の本のかやうにあしくなりたるも、皆上宮太子の愚よりはしまれり」――。遺物信仰の対象として熟成した「聖徳太子」に攻撃を加える江戸の知識人。フェノロサ、岡倉天心らの古美術調査がもたらした近代の転回。『日本書紀』の原像にはじまり、現在のコンテクストが成立するまでを描く記憶と創造の物語。
【目次】
序章 「聖徳太子」か「厩戸皇子」か
第一章 「聖徳太子」の原像
1 『日本書紀』のなかの「皇太子」
2 多くの名をもつ「皇太子」
3 聖は聖を知る
4 日本国の尸解仙
第二章 「聖」はめぐる
1 「聖徳」は、やはり「聖」
2 「上宮太子」と申す聖
3 生けるが如し
第三章 攻撃される「聖徳太子」
1 「上宮太子」の愚
2 林羅山、「春秋の法」を説く
3 檄を飛ばす荻生徂徠
4 タブーに挑む片山蟠桃
5 「笑語」する平田篤胤
第四章 法隆寺の「聖徳太子」
1 奈良博覧会
2 七種の宝物
3 梵網経に随喜の涙
4 聖霊奉還と宝物献納
5 宝物献納その後
第五章 「古美術」調査から生まれた「聖徳太子」
1 美術取調
2 仏教のコンスタンティヌス大帝
3 不世出の英傑厩戸皇子
4 近代の「聖者」
第六章 子どもたちの「聖徳太子」
1 天皇の年代記
2 小さな「聖徳太子」伝の出現
3 小さな「聖徳太子」伝の完成
4 「国民の覚悟」を担う
5 ゆるんだ政治の立て直し
終章 「聖徳太子」とは何か
参考文献
あとがき
主要人名・書名索引

中国現代アート 自由を希求する表現
講談社選書メチエ
激動する歴史の中で人はいかに表現したか
文化大革命、毛沢東崇拝の嵐から「社会主義市場経済」へと、激動する現代史の中で、中国のアーティストたちはいかにして自由な表現を実現させてきたのか。いまや世界でもっとも注目される中国現代アートの展開をたどり、作品の数々を紹介。政治や経済の文脈からは決して知ることのできない、現代中国のエネルギーの根源を体感する!
【目次】
はじめに
第一章 中華伝統と革命伝統 中国現代アート史概観
1 二重の「負の遺産」と二つの衝撃
2 毛沢東様式の成立まで
3 文革打破 自由への宣言
4 試行錯誤の現代アート
第二章 解放を希求する表現 中国のパフォーマンス・アート
1 北京東村のパフォーマンス・アート
2 パフォーマンスと当局の介入
3 桎梏からの解放
第三章 「社会主義市場経済」下のアート
1 中華伝統と革命伝統の客体化
2 中国キッチュ
3 行為としての革命の記憶
4 大資本主義の行く末
第四章 描く女性、描かれる女性 「鉄の娘」からイノセントへ
1 プレモダンからモダンへ 商品化される女性と女性像
2 毛様式の女性たち
3 鉄の娘、アートの死滅
4 「星星」の女たち
5 イノセントからの女性アート
第五章 変革と保守 二〇〇〇年代の「前衛」アート
1 「前衛」の変容
2 アート工場の誕生、そしてミニマリズムへ
3 紅い激情への誘惑 「左手と右手」展
4 アートの異化効果
5 脳の中の自由 上海ビエンナーレ2004
6 新たな思想
終章 「世界」に参入する中国現代アート
1 救済としてのアート
2 「世界」と交わる
3 アートと自由
あとがき
主な参考文献・美術展
索引