講談社選書メチエ作品一覧

大江戸調査網
講談社選書メチエ
江戸の世界にアクセスしよう!
単位に貨幣に衣・食・住……。江戸の世界のあれこれを調べるための現代の諸書と江戸時代に書かれた江戸随筆を“江戸レファレンスブック”として紹介。読んで楽しく、自分で調査してなお楽しい、画期的「ツール本」の誕生!
江戸を知る手がかりが、すべてここにある! 衣食住、時間、空間、職業、言葉……。江戸の生活を知るには、どんな資料にあたればよいか。江戸随筆から現代の膨大な関連書籍の海を探索するための、読む「調査本」。
【目次】
序章 江戸レファレンスブック・江戸随筆へようこそ
レファレンスの意味
質問者と図書館の関係
ツールとルーツ
江戸レファレンスブック
江戸随筆
江戸随筆の集成本
日本十進分類法(NDC)
江戸レファレンスブックの分類
第一章 単位
度量衡
長さの単位
かさの単位
重さの単位
尺貫法
置きかえてみる
距離・面積の単位
第二章 貨幣
種類と単位
両替(交換比)
一両・一文の価値
第三章 暦・時
太陰と太陽
大・小の月、閏月
年中行事
十干・十二支
時刻
不定時法
時計・時の鐘
第四章 衣
左衽と右衽
武士の衣
町人の衣
化粧
髪形
かぶりもの
はきもの
第五章 食
外食(屋台)
蕎麦
うなぎ
すし
天ぷら
けんどん
初鰹
調味料
菓子
嗜好品
食の辞(事)典
第六章 住
明暦の大火前と大火後
人口比と面積比
武士の住
町人の住(裏長屋)
上水道
燃料
照明道具
冬の生活道具
夏の生活道具
図版・写真入りの道具本
第七章 生業
多種多様な生業
物売り・職人の絵
おもしろい物売り
看板
第八章 言葉
聞かない言葉・聞く言葉
言い方
歌舞伎用語
第九章 地図・絵図
現在との比較
江戸図
切絵図
目録
第一〇章 辞(事)典・年表
江戸の辞(事)典
全巻ものの日本史辞(事)典
一冊ものの日本史辞(事)典
人名辞(事)典
年表
終章 新世紀~江戸開府四〇〇年の江戸レファレンスブック
かたちを変えたもの
辞(事)典・年表
あとがき

楊貴妃になりたかった男たち <衣服の妖怪>の文化誌
講談社選書メチエ
男は女に 女は男に
中国人の奇妙な情熱
ヘンテコな服装は妖怪である。世が乱れ礼が失われた証拠である。だが周恩来も女装した。美少年もむくつけき大男も、中国の歴史は女装に身も心も捧げた男たちで満ちている。悠久の大陸を横断する奇妙な妖怪=服妖に見る、知られざる中国の素顔。
【目次】
第一章 楊貴妃になった男たち
第二章 服妖 衣服のモンスター
第三章 麗人たちは男装する
第四章 男まさりを恐れる系譜
第五章 女装者たちの系譜
第六章 陰陽転倒の諸相 生物学的性転換の記録
第七章 男扮女装の諸事情
第八章 同性愛文学と女装趣味
第九章 近代中国の木蘭たち 清末男装事件図絵
第一〇章 女装者たちの事情 清末女装事件図絵 I
第一一章 趣味の女装者たちと性転換 清末女装事件図絵 II
第一二章 女装とパフォーマンス 反串・演劇・映画
第一三章 このごろ流行りの男扮女装
注
参考文献
図版出典
あとがき
索引

文学の誕生 藤村から漱石へ
講談社選書メチエ
漱石は軽文学の王だった!
日露戦争は、日本の近代文学が成立するうえで、大きなターニングポイントになった。「日露戦後」文学とは、どのようにつくり出され、社会に定着していったのか。島崎藤村、国木田独歩、田山花袋、小栗風葉、夏目漱石という、当時を代表する5人の作家に焦点を当て、それぞれの評価の転変を詳細に跡づけながら、近代日本の歴史の中で、文学が文学となった時を考証する、俊秀の鮮烈なデビュー作。
【目次】
序章 文学の新紀元 日露戦後新文学の勃興
一 文学の新紀元
二 新文学と旧文学
三 新しい文学評価の座標軸
第一章 技術批評を超えて 島崎藤村『破戒』の表層と深層
一 「鬱勃たる精神」
二 技術批評 テーマ・素材・人物造型・構成・文章
三 作家への期待と作品への失望
四 作家の真面目な態度 技術批評を超えて
五 『破戒』の受難と復活
第二章 〈自己表現〉の時代 〈国木田独歩〉を読む〈私〉
一 「僕は魔法使ひではない」
二 悪文と主観の突出 「小説との命名さへ、頗る疑はしきもの」
三 作品から作者へ 「小説以上の作物」
四 作品から読者へ 〈国木田独歩〉を読む〈私〉
五 「独歩は独歩である」
第三章 読むことの規制 田山花袋『蒲団』と作者をめぐる思考の磁場
一 「空想に耽つて立尽した時雄」
二 〈告白小説〉としての『蒲団』 「大胆なる懺悔録」
三 〈客観小説〉としての『蒲団』 「客観の描写」
四 作者をめぐる思考の磁場 「自意識的な現代性格の見本」
五 『蒲団』と私小説論争
第四章 文学の〈裏切り〉 小栗風葉をめぐる・文学をめぐる物語
一 「従来の写実派では飽足らない」
二 内面の作品 活躍する「主観的」風葉
三 表面の作品 没落する「客観的」風葉
四 文学の〈裏切り〉 風葉と代作
五 「アアチスト」と「アリチザン」
第五章 軽文学の王・夏目漱石 あるいは明治四十年、文学の自己同一化
一 「美しい感じ」
二 軽文学の王・夏目漱石
三 茶番作家・夏目漱石
四 争奪戦の舞台裏 「作家と作物を混同する勿れ」
五 「近眼鏡」を掛けられて
終章 文学のための物語 文学概念・文学史
一 文学概念の規定
二 文学史の記述
三 文学のための物語
典拠・引用について
注
あとがき
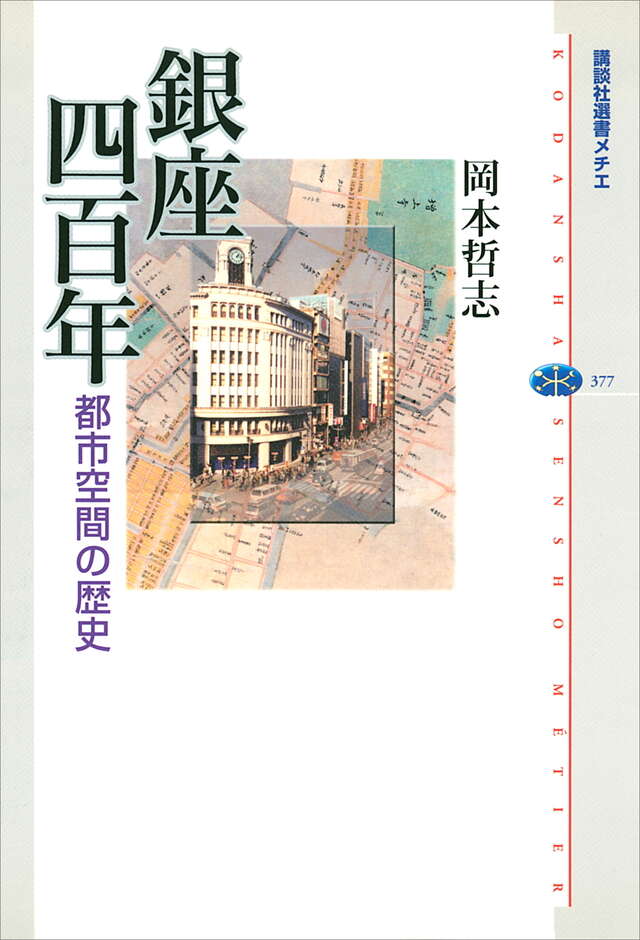
銀座四百年 都市空間の歴史
講談社選書メチエ
「銀座の空気」はこうして作られた
江戸の誕生から町人地としての発展、明治の煉瓦街建設からモダン都市成立、そして戦後の変容。魅力あふれる銀座という街の空気は、幾重にも重ねられた、都市の歴史が作り出したものだった。都市研究者が自身の足で街を歩きつくし、資料を丹念に読み込み、銀座の構造と進化の過程を鮮やかに描き出す。
<本書の内容>
はじめに
第一章 現代の基層を読み解く(江戸初期)
1 江戸城下町の空間演出の手法
2 空間をつくりだす知恵
3 寛永期に表現された江戸
第二章 明暦大火後の街づくり
1 変化する町人地、変化しない町人地
2 変容した街区構成を読み解く
3 町屋敷内の空間変容プロセス
4 江戸時代の銀座の空間表現
第三章 江戸と融合した煉瓦街建設の試み(明治初期)
1 西洋風街並みの出現に向けて
2 日本初の西洋風街並みの出現
3 明治初期の社会変化と土地動向
4 近代における銀座の選択
5 江戸の街区構造を活かした煉瓦街
第四章 人の和が育てた街の厚み(明治後期)
1 江戸の骨格を近代に継承する構図
2 煉瓦街建設後の街の変化
3 モダン都市空間への予感
4 空間の多様性と街のコントロール・システム
第五章 歴史の文脈に裏付けられたモダン都市の創造(昭和初期)
1 近代の主役が集まる場所
2 街並みのモダンと銀座フィルター
3 産業から脱皮する三十間堀川沿い
4 街と建築がつくりだす空間の緊張感
第六章 戦後から現在に至る銀座
1 戦後における土地と建物の変容動向
2 都市空間の仕組みと路地構造
3 期待される新たな銀座像(外堀通りとみゆき通り)
おわりに
注
参考文献
索引

身体の哲学 精神医学からのアプローチ
講談社選書メチエ
人は皆やっかいな身体を生きている
心と体は別ものではない。互いに交差し合い、しかも他者のからだへと開かれている。拒食症、解離症、境界例などの心-身に関わる病例に依りながら、「こころ」と「からだ」の問題を根底から問い直す。
【目次】
はじめに
第一部 身体という原点
第一章〈エス〉から始めよう
1 心身問題
2 グロデックの思想
3 生命的主体としての〈エス〉
4 十字架を背にしたキリスト
第二章 身体の精神病理学
1 基礎学問としての精神病理学
2 人間学的実存論
3 精神疾患をどう名づけるか
第二部 身体の諸相
第三章 疎外する身体 拒食/過食症
1 女子高生の症例
2 「拒食/過食症」
3 ボディイメージと自己の成立
4 被投性と「私」
5 自己肯定感の希求
第四章 乖離する身体 解離症
1 男子専門学校生の症例
2 歴史から見た解離
3 「解離症」
4 主体性の欠如と解離感
5 解離の症候論
6 過剰身体の乖離
7 ハイマート
第五章 癒合する身体 境界例
1 女子大生の症例
2 境界例の歴史
3 陳述のもつ身体性
4 境界例感と投影同一化
5 間身体性における非人称の主体
6 自己存在の問い
第三部 身体の構造
第六章 生のキアスム
1 二重の身体とノスタルジー
2 ハイマートと一次愛
3 関係としてのキアスム
4 「私」という存在
第七章 時間としての身体
1 身体の声を聞く
2 身体のセクシュアリティ
3 キアスムと癒し
4 それぞれのキアスム
5 ハイマートから未来へ
おわりに
参考文献
索引

政治診断学への招待
講談社選書メチエ
「失政」という病を治療する政治学へ
政治権力の「あやまち」をどう見極めるか? 人々はなぜ政治、権力の暴走をゆるしてしまうのか? 気鋭の政治学研究者が、「政治を診る」理論を確立するべく、古今東西の政治思想史を、大胆かつ精緻に読み直す!
【目次】
はじめに
第一章 政治危機の把握はなぜ難しいのか
1 ナチ・ドイツとフルトヴェングラー
2 大日本帝国と矢内原忠雄
3 政治診断学
4 医学と政治思想の知られざる関係
第二章 政治理論の医学的モデル
1 政治体の解剖学
2 四体液説 政治体の生理学
3 政治体にとっての診療医
4 検視官としての歴史家?
第三章 政治診断学の構想
1 統治術から政治監視術へ
2 診断学の思考様式
3 トマス・シデナムの方法論革命
4 診療体制の構想
5 政治診断学の射程と課題
第四章 政治体の治療学へ
1 東西の治療メタファーの違いとは
2 西洋における治療メタファー
3 徳川期日本の治療メタファー
4 治療法における東西の差異
5 政治体の自己治癒能力
6 政治体の死
終章 現代政治を診断する視角
1 政治症候学としての暴政理論
2 政治診断学の懐胎
あとがき
注
参考文献
索引

満鉄全史 「国策会社」の全貌
講談社選書メチエ
国策という名の無策に翻弄され続けた40年。「陽に鉄道経営を装い、陰に百般の施設を実行する」満洲支配の尖兵。だが政・官・軍の対立と場当たり的政策に翻弄された「国策会社」は、必然的に破綻する運命にあった。創立100周年を機に、近代日本を体現する矛盾と迷走の全歴史をたどりなおす。(講談社選書メチエ)
国策という名の無策に翻弄され続けた40年
「陽に鉄道経営を装い、陰に百般の施設を実行する」満洲支配の尖兵。だが政・官・軍の対立と場当たり的政策に翻弄された「国策会社」は、必然的に破綻する運命にあった。創立100周年を機に、近代日本を体現する矛盾と迷走の全歴史をたどりなおす。
<本書の内容>
●満鉄とは何だったのか
●松岡洋右と国家改造
●日本の「満洲」・中国の「東北」
●満洲事変と満鉄の転換
●蜜月の終わり
●国策会社の凋落
●現代日本にとっての満鉄
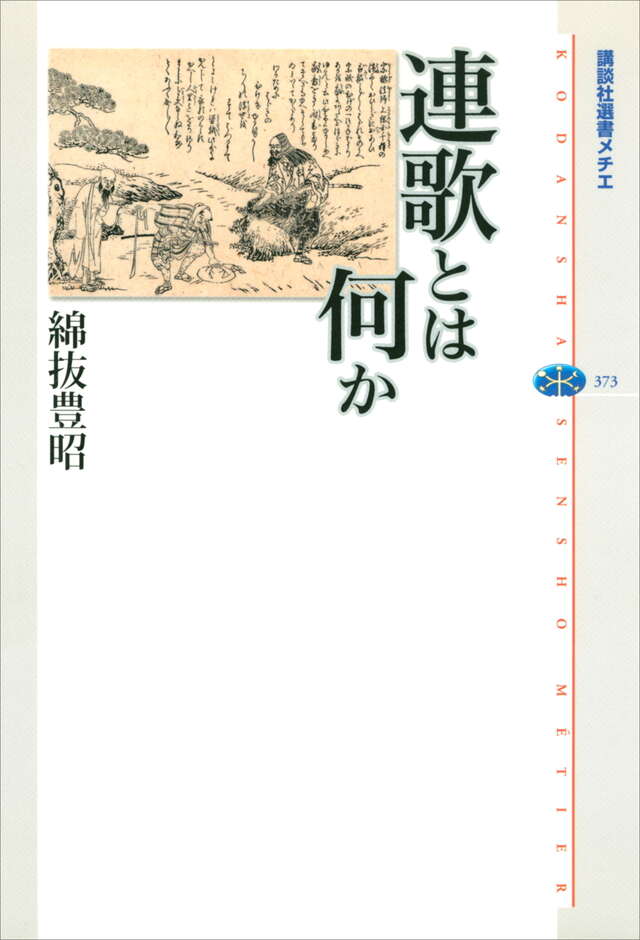
連歌とは何か
講談社選書メチエ
中世人がもっとも愛した文芸の全貌
創作しつつ味わい、味わいつつ創作する、機知と友愛のアート。二条良基・一条兼良・宗祗ら天才の仕事を軸に、能・茶・花をしのぐほどの人気を誇りながら、近代とともに忘れられた文芸の全歴史をたどる。
[本書の内容]
はじめに
第一章 連歌の世界
1 「連歌」とは何か
2 短連歌の世界
3 長連歌の世界
4 連歌会の空間
第二章 連歌の式目
1 式目の世界
2 「水無瀬三吟百韻」を読む
第三章 連歌の歴史──起源から安土桃山時代まで
1 日本武尊から鎌倉時代まで
2 二条良基と本格的連歌の始まり──南北朝時代
3 連歌七賢──室町時代その一
4 天才宗祇とその弟子たち──室町時代その二
第四章 連歌その後
1 地方への広がり──中世から近世へ
2 安定と停滞──近世の連歌
3 明治以後のこと
註
おわりに
索引

イエズス会の世界戦略
講談社選書メチエ
宗教的情熱の下に隠された、宣教師たちのもう1つの顔
イエズス会はなぜ非ヨーロッパ世界の布教に成功したのか? 彼らが日本やインドなどで採用した適応主義政策とは? 布教活動のために貿易や不動産経営で生計をたて、信者と資産保護のため軍事活動も行った宣教師たち。「神の意志」実現のために世界を巡った「イエスの同志」の聖と俗に迫る。
【目次】
プロローグ
第一章 キリスト教とインド世界 イエズス会進出の前史
第二章 イエズス会 創立とその組織
第三章 地上の王と神の使者 俗と聖の饗宴
第四章 「情報」の収集・解析とイエズス会
第五章 「異文化」への処方箋
第六章 神の使者たちの「錬金術」
第七章 聖衣をまとった戦士たち
エピローグ
注
あとがき

階級社会 現代日本の格差を問う
講談社選書メチエ
格差大国日本。その衝撃的現実をレポート。今や日本は、世界的に見ても不平等度が高く、貧困者の多い国である。しかも階級格差は確実に拡大し続けている。客観的データに基づいて現代日本に警鐘を鳴らす。
一握りの富裕層が富を独占する一方で、職のない若者たちはアンダークラス化し、貧困層は増大し続ける。日本は今や階級格差の超大国であり、階級格差は今もなお拡大し続けている。衝撃的現実を客観的データに基づいてレポートし、現代日本に警鐘を鳴らす。
【目次】
はじめに
第一章 階級の死と再生
1 「階級」が死語だったころ
2 よみがえる「階級社会」
3 経済的格差の拡大
4 政治的な言葉としての「階級」と普通の言葉としての「階級」
5 階級とは何か
6 現代社会の階級構造
第二章 階級へのまなざし──近代都市東京と「階級」
1 社会史の中の「階級」
2 「みえる」存在としての階級
第三章 庶民とヒーローの階級闘争──『下町の太陽』と梶原一騎
1 戦後青春映画の中の階級
2 梶原一騎の階級意識
3 ヒーローたちの階級闘争
4 階級構造への適応と不可能な階級闘争
第四章 拡大する階級格差
1 格差拡大の意味
2 四つの階級のプロフィール
3 引き裂かれる被雇用者
4 搾取・疎外・階級闘争
第五章 アンダークラス化する若者たち
1 フリーターと都市下層
2 増加するフリーター・無業者層
3 フリーター・無業者層の階級的性格
4 アンダークラスとしてのフリーター・無業者層
第六章 女たちの階級選択
1 女性の階級所属を考える
2 配偶者選択と女性の格差
3 階級格差の中の主婦たち
4 ゆらぐ家族と貧困化する女性たち
第七章 「格差社会」のゆくえ
1 「格差社会」とは何か?
2 格差拡大と機会の不平等
3 「機会不平等」論の陥穽
4 教育学的誤謬
5 格差拡大はなぜいけないのか
6 「格差社会」を超えて
註
主要参考文献
あとがき
索引

項羽と劉邦の時代 秦漢帝国興亡史
講談社選書メチエ
鴻門の会、四面楚歌――
『史記』の虚実を読み解く
「秦を滅ぼすものは必ずや楚ならん」――。中国を最初に統一した秦帝国は、なぜ短期間で滅んだのか。なぜ農民出身の劉邦が項羽に勝利したのか。秦と楚、2つのシステムという観点から「鴻門(こうもん)の会」「四面楚歌」に代表される『史記』史観をとらえ直し、漢王朝成立までのドラマを描き出す。
【目次】
はじめに もう一つの項羽と劉邦
竹簡や木簡が語ること/秦と楚の社会システム
序 章 始皇帝と秦の統一
始皇帝陵と兵馬俑/秦国の興起/秦の富国強兵──商鞅の変法/法制と軍事編成/統一の理念/なぜ短期間で滅んだのか
第一章 南方の大国・楚
楚文化のイメージ/懐王の時代/長江流域の統合──鄂君啓節/楚の社会と習俗──包山楚簡/楚都の陥落/東方の楚国へ
第二章 秦帝国の地方社会
秦代の郡県制/地方行政と労役/沛県の官府と社会/劉邦と周辺の人びと/王族たちの怨み/東方社会の人びと/項梁と櫟陽の獄掾
第三章 陳渉・呉広の叛乱──楚国の復興
二世皇帝と扶蘇/辺境への徴発/秦の制度と戍卒/扶蘇と項燕を称す/陳王となる/楚国の復興をめざして/陳王の死
第四章 項羽と劉邦の蜂起──楚のもとで
秦と東方の異なる原理/始皇帝の巡行と江南社会/項梁・項羽の蜂起/楚の国家体制/沛県の蜂起/沛公の社会基盤/項梁の死/鉅鹿の戦い
第五章 秦帝国の滅亡──「鴻門の会」の謎
関中に王とする約束/項羽と章邯の会盟/沛公の行軍/覇上に駐屯する/鴻門の会/樊〓の自慢話/咸陽城の焼失
第六章 西楚覇王の体制──二つの社会システム
十八王の分封/漢中へ──分封への不満/関中の掌握/漢の社稷を立つ/義帝の死と諸侯/彭城の戦い
第七章 楚と漢の戦い──戦略と外交
戦いに敗れて/人質からみた楚国/韓信の戦略と兵法/斉をめざす韓信/生産と軍事補給/広武山の対面/外交の知恵を学ぶ/漢覇二王城での会見
第八章 項羽の敗北──第三の男、淮陰侯韓信
東方への進軍/垓下の戦い──四面楚歌/烏江での最期/項羽をめぐる伝え/楚王韓信の処遇/楚の体制の終わり/地域を再編する試み
終 章 漢王朝の成立──地域社会の統合
項羽と劉邦の評価/両陣営のブレーン/長安と地方社会/功臣から劉氏の封建/高祖の死と呂后/武帝と司馬遷/東アジアのなかで
あとがき
参考文献
戦国・秦漢時代の年表
人名索引

東京裁判への道(下)
講談社選書メチエ
残虐行為はなぜ裁かれなかったか?
尋問調書に残る、生々しい戦争責任の諸相。十五年戦争史の死角にまで迫る発言を残したのに次々と釈放される「訴追されなかった容疑者」。激化する冷戦に対応するために、恣意的に無視された証言や証拠は、大量にアメリカに残されていた。様々な新事実を開示することで、多角的に東京裁判の諸相を解明する「裁判開廷史」ついに完結!

近代日本の陽明学
講談社選書メチエ
近代日本が堕ちた「善意」の闇。善意が起こす「革命」はタチが悪い! 我々が創出した「近代」の問題の本質は、陽明学と水戸学の系譜が交差するとき明らかになる。陽明学の新たな解釈史にして、日本近代思想史の驚くべき読み直し。(講談社選書メチエ)
近代日本が堕ちた「善意」の闇
善意が起こす「革命」はタチが悪い! 我々が創出した「近代」の問題の本質は、陽明学と水戸学の系譜が交差するとき明らかになる。陽明学の新たな解釈史にして、日本近代思想史の驚くべき読み直し。

東京裁判への道(上)
講談社選書メチエ
「天皇不訴追」はなぜ実現したか?
「A級戦犯」28人はいかにして選ばれたのか?近衛文麿の死、木戸幸一の長大な弁明、陸軍の大物・田中隆吉の謎の変節。そして昭和天皇「不訴追」決定の真実――。膨大な尋問調書が語る、濃密な人間ドラマの開幕!

儒教と近代国家 「人倫」の日本、「道徳」の韓国
講談社選書メチエ
忠孝、人倫、理想道徳……
日韓それぞれの近代思想史!
同じく儒教を政治思想の基盤としながら、日本と韓国はなぜ、異なる近代化の道をたどったのだろうか。伊藤仁斎に代表される近世儒学の人倫論と、水戸学、明治憲法、教育勅語の関係とは。朱子学を柱とする韓国は、いかにして文明開化から戦後の朴正煕大統領の維新憲法にまで至ったか――。両国の近代と政治思想を問い直す画期的論考。
【目次】
はじめに
第一章 近代国家の基盤思想としての近世儒教
1 伊藤仁斎と人倫
2 性は気質である
3 韓国における普遍価値の追求
4 道徳理想主義への希求
第二章 西洋文明の登場とその受け入れ方
1 啓蒙思想としての文明開化論
2 西欧中心の文明開化──福沢諭吉
3 儒教中心の文明開化──兪吉濬
第三章 日本の近代国家への移行
1 国家理念の形成
2 万世一系の皇統
第四章 日本の近代国家の思想的組み立て
1 明治憲法
2 水戸学の「正名論」と「忠恕」
3 教育勅語と国民道徳
4 忠と孝、そして人倫
第五章 韓国の近代思想の諸相
1 近代意識の始まり
2 世界観の変化
3 朝鮮における近代意識の挫折
第六章 韓国の維新憲法と国民教育憲章
1 思想史からみた植民地時代
2 近代国家の樹立への構想
3 国民意識の高揚
4 近代国家への経験
おわりに
註
あとがき
索引

南の思想
講談社選書メチエ
世界の行きづまりを解きほぐす柔らかな思想
南イタリアから贈る哲学的エセー
遅さ、矛盾、自由。「南」には近代が忘れた富がある。力ではなく弱さを。所有の自閉のかわりにフロンティアの開放を。ブレーキの壊れた資本主義のかわりにゆったりとした「適度」を。「南=貧困」のステレオタイプを打ち破る、近代合理主義への「南」=地中海からの回答。

名匠と名品の陶芸史
講談社選書メチエ
荒川豊蔵から北大路魯山人まで
大作家たちの秘話で明かす「陶芸」の真実!
備前、萩、唐津、瀬戸、志野、織部…… 山中を踏破し、掘り出した古陶片から歴史の謎を解き、「やきもの」の伝統を復活させ、創意を盛り込み、それらを世界的な芸術へ昇華させた巨人たち13人。荒川豊蔵から北大路魯山人まで、波乱の群像劇を、豊富な秘話・逸話で綴る。
【目次】
序 現代陶芸の礎を築いた近代陶芸巨匠
第一章 荒川豊蔵(1894-1985)
第二章 三輪休和(十代 三輪休雪)(1895-1981)
第三章 石黒宗麿(1893-1968)
第四章 加藤唐九郎(1898-1985)
第五章 板谷波山(1872-1963)
第六章 富本憲吉(1886-1963)
第七章 金重陶陽(1896-1967)
第八章 河井寛次郎(1890-1966)
第九章 加藤土師萌(1900-1968)
第一〇章 濱田庄司(1894-1978)
第一一章 小山冨士夫(1900-1975)
第一二章 川喜田半泥子(1878-1963)
第一三章 北大路魯山人(1883-1959)
あとがき
参考文献
関連年表
索引

色で読む中世ヨーロッパ
講談社選書メチエ
色に込められたメッセージを読む
黄色に付随する負のイメージ。権力と護符の色としての赤。美しくも不気味な緑。15世紀に大流行する黒――。当時の人々は色にどのようなメッセージを込めたのか?色彩に満ちた時代はどのようにして始まり、そして終焉を迎えたのか?さまざまな色から中世ヨーロッパ人の感情生活を捉え直す。
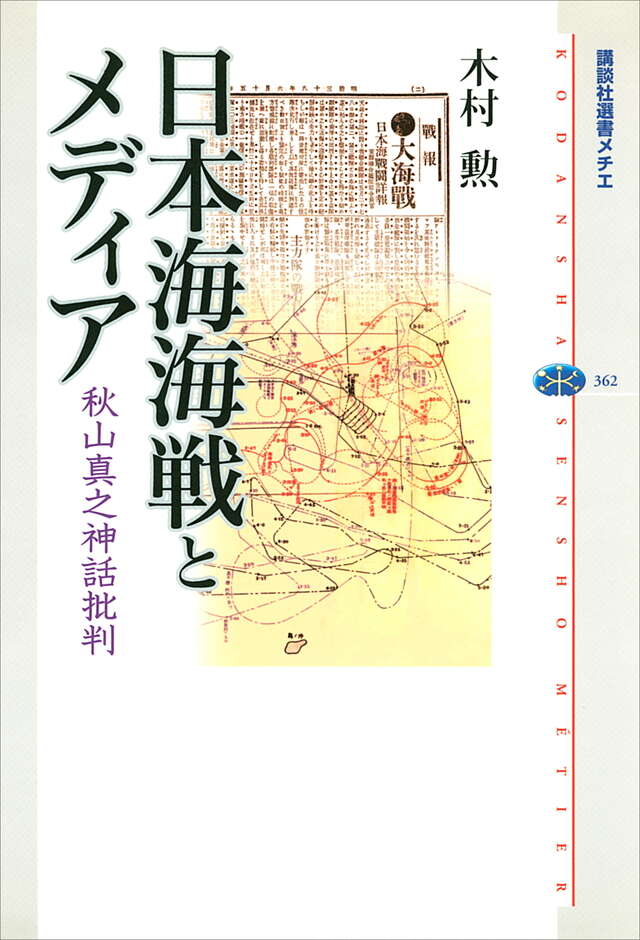
日本海海戦とメディア 秋山真之神話批判
講談社選書メチエ
極秘海戦史でわかった語られざる真実
連合艦隊司令長官・東郷平八郎とその参謀・秋山真之。この軍神と天才によって敢行された丁字戦法によって、連合艦隊はロシアのバルチック艦隊を撃破――。日本海海戦の勝利は胸のすく快挙として昭和の軍国主義イデオロギーの核心を形成していく。その伝説の影響は今日にも及ぶといって過言ではない。これまで明らかにされることのなかった史実を、第一級史料『極秘明治三十七八年海戦史』を丹念に読み解き、浮き彫りにするとともに、神話を作りあげていったメディアの側をも批判的に検証する。
【目次】
はじめに
序章 日本海海戦イメージの変遷
「天気晴朗なれども波高し」は暗号か/日露戦争への道/史料について
第1章 「敵前大回頭」とは何か 21
一八〇度ターンは当然のこと/軍関係者は「大転舵」/「大回頭」の出自/無線通信のトラブル/円運動は遭遇予定地点のズレから始まった/艦隊編成について
第2章 軍神の誕生
緒戦の旅順口攻め/夜襲作戦の実際/山本五十六の批判/三度の閉塞作戦/秋山の「高ぶり」/副官電に登場した「軍神」/「成功」と報じたのは新聞/マカロフ提督戦死
第3章 ウラジオ艦隊、潰滅せず
戦艦「八島」沈没の隠蔽/輸送船被害キャンペーン/上村艦隊の苦渋/「報道の自由」時代か/体面をとりつくろう体質/八月十日、決まらなかった丁字戦法/八月十四日、ウルサン沖海戦
第4章 秋山作戦の迷走 109
「四月十二日」戦策/「四月二十一日」改訂追加戦策/「五月十七日」追加戦策/「五月二十一日」改訂戦策/藤井証言「艦隊戦策変更の真相」/藤井証言「奇
襲隊取止めの真相」/藤井証言「津軽海峡転位についての会議の真相」/島村速雄の遅参/東郷は気配り調整型
第5章 「開戦後三十分で勝利」したか
二時四十五分決着とした「戦闘詳報」/秋山が強調した「三十分」/第二戦隊「独断専行」のはじまり/第一戦隊と別れた第二戦隊/公刊戦史の奇妙な記述/検証されなかった「独断専行」/ロシア側が評価する上村の行動/「主将は口喧しき号令者にあらず」/ロシア戦史のロジェストウェンスキー評価
第6章 メデイアはどう報じたか 185
丁字戦法と明治三十七年「一月九日戦策」/海軍PR文と七段構え/事実を秋山の「論」に押し込む作為/PR文は特ダネか/丁字戦法成立の経緯/抜擢された
秋山の才/丁字戦法の明治三十七年、同航戦の三十八年/島村速雄の気質と秋山真之の傷
終章 その日とそれ以後
あとがき
資料 1 戦闘詳報 2 海軍PR文 3 連合艦隊解散之辞
索引

人物を読む 日本中世史
講談社選書メチエ
源頼朝は善人だった?
足利尊氏が天皇家を再興させた?
武士が興隆し「統治」が生まれた中世に、大きな足跡を残した8人の真実とは。明快な視座のもと、続々と明かされる仰天の新事実、そして立ちのぼる“王権”のダイナミックな姿――。人物史から読み替える、分かり易く新しい中世史!