講談社選書メチエ作品一覧

起請文の精神史
講談社選書メチエ
小さな紙片に蔵された、広大なる精神宇宙
なぜ天照大神に誓いを立ててはならないのか。神と仏はどちらが上位か。本地垂迹の本質とは何か。中世日本の巨大なコスモロジーは、一片の起請文の中にある。神仏習合から新仏教まで、中世人の豊饒なる精神世界の全貌に迫る。
【目次】
序 章 方法としての起請文
第一章 起請文を読む
1 神文への着目
2 神仏の序列
3 日本の仏
4 弥陀と閻魔
5 死霊の系譜
第二章 神と死霊のあいだ
1 古代の神観念
2 〈命ずる神〉と〈応える神〉
3 御霊とモノノケ
4 〈応える神〉としての疫神
第三章 垂迹する仏たち
1 あの世の仏とこの世の神仏
2 中世人にとっての本地垂迹
3 浄土信仰と垂迹の役割
4 生身仏の時代
第四章 神を拒否する人々
1 コスモロジー論の検証
2 神を拒否する人々
3 神祇不拝の根拠
4 なぜ垂迹を排除するのか
5 法然の決断
終 章 パラダイムに挑む
引用参照文献一覧
あとがき
索引

東大駒場連続講義 歴史をどう書くか
講談社選書メチエ
歴史研究の最前線がわかる!
東京大学比較日本文化論テーマ講義
●日常生活をとおして見る歴史の再構成――衣服を中心に 義江彰夫
●天皇の即位儀礼――孝明・明治・大正三天皇の比較 三谷 博
●ヨーロッパ史における「王権」の表象――教皇の即位儀礼 甚野尚志
●モノで語る歴史――考古学と博物館 折茂克哉
●古代国家と稲――1200年前の品種札の発見から 平川南
●≪オランピア≫の変貌――美術史学と歴史記述 三浦 篤
●写真史が生まれる瞬間(とき)――ウジェーヌ・アジェと仏・米現代写真の言説 今橋映子
●植民地期インドにおける歴史記述――パールシーの書く「自分たち」の歴史 井坂理穂
●文学は歴史をどう書くか――日系アメリカ文学の場合 瀧田佳子
●歴史の多声性――歴史観の人類学的考察 伊藤亜人
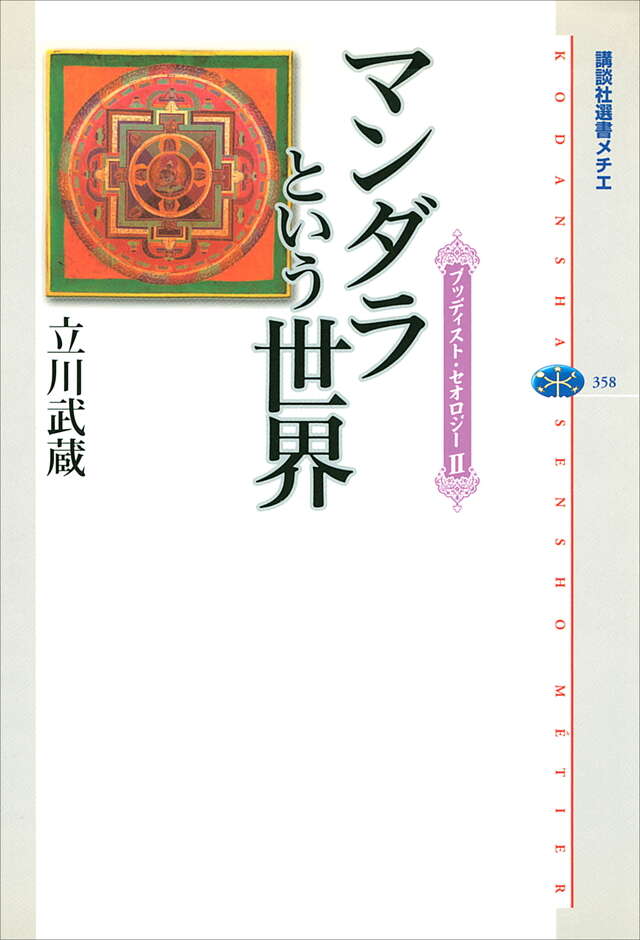
マンダラという世界 ブッディスト・セオロジー(2)
講談社選書メチエ
聖書、インド思想、近代哲学、そして仏教
明快に語りおろす「世界」の本質
いま、社会の急激な変化に対して、仏教のうたう「普遍的な悟り」は有効なのか? 死すべき自分が「他者」の存在を理解できるのか? 各宗教の「世界」把握の方法論をたどり、現代日本に求められる世界観の体系を解明する。
【目次】
はじめに
第一章 世界に対する態度
第二章 自己空間と他者
第三章 世界の中にあること
第四章 縁起と世界
第五章 自然と神
第六章 行為と存在の弁証法
第七章 『旧約聖書』における世界
第八章 『新約聖書』における世界
第九章 インド思想における世界
第一〇章 仏教の世界観
第一一章 世界としてのマンダラ
索引
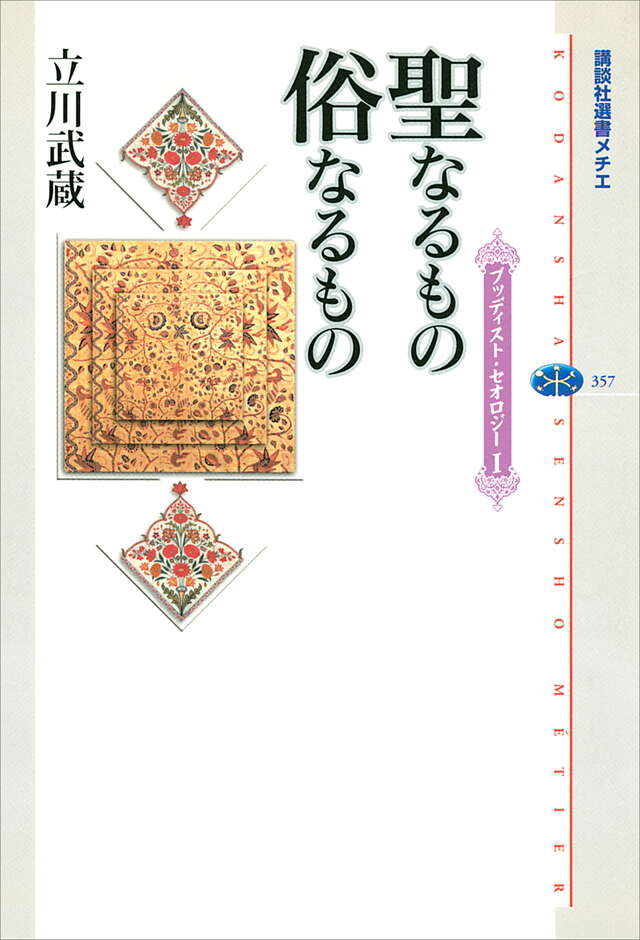
聖なるもの 俗なるもの ブッディスト・セオロジー(1)
講談社選書メチエ
諸宗教の多元的共存は可能か?
「仏教の神学」に挑む連続講義、開幕!
宗教という営みは何を目標としているのか? キリスト教、イスラム教、ヒンドゥー教、そして仏教。異なる世界を出発点としながらも、その上に伝達可能で整合的な知の体系を構築することは、神学的方法論によって可能になる。「聖なるもの」を問う、仏教学第一人者の野心的な講義がはじまる!

信長とは何か
講談社選書メチエ
天下統一は必要だったか?
「武」の人信長。「力」のみを信じ、戦国大名でただ1人、天下統一をめざした男。だが、「力」に拠るものがいずれ「力」に倒れるのは必然であった。天下統一は必要だったのか? その日本史上の意義とは何か? 「信長」を根本から問い直す画期的論考。
【目次】
はじめに
第一章 「大うつけ」 若き日の信長
第二章 桶狭間
第三章 天下布武
第四章 岐阜城の信長
第五章 岐阜城下と楽市令
第六章 上洛
第七章 信長の敵 戦国時代とは何か
第八章 合戦と講和
第九章 公家になった信長
第一〇章 安土城下町(1) 城と家臣
第一一章 安土城下町(2) 町と楽市令
第一二章 本能寺の変 信長を殺したもの
あとがき
年表
参考文献
索引

会社のカミ・ホトケ 経営と宗教の人類学
講談社選書メチエ
入社式、社葬に隠された意味とは?
日本的経営の秘密をさぐる
ビルの屋上に祠をかまえ、物故社員慰霊の法要を営む。日本の会社=社縁共同体はなぜ神仏をまつるのか? 入社式や社葬の知られざる意味とは? 経営人類学の観点から日本的経営の本質を解き明かす1冊。
【目次】
プロローグ 経営人類学と会社
第1章 会社宗教とは何か
1 会社宗教のルーツ
2 カミとホトケの不均等二分
3 平等原理と不平等原理
4 カミとホトケの五行説
第2章 会社神社と社縁共同体
1 会社神をまつる神社
2 神々の合戦を制しヱビスビール
3 恵比寿の再開発と恵比寿神社
4 会社はなぜ神をまつるのか
第3章 会社墓と日本的経営
1 高野山と比叡山
2 供養塔建立の歴史
3 供養塔建立史を読む
4 追悼儀礼
5 会社はなぜ物故者を供養するのか
第4章 会社への加入儀礼=入社式
1 同期の桜
2 ソニーの入社式
3 ダスキンの入社式
4 入社時研究とイニシエーション
第5章 会社の不滅と再生の儀式=社葬
1 創業者の社葬
2 松下電器とソニー
3 ドーム社葬
4 社葬の意義
第6章 会社の神聖化装置=企業博物館
1 会社の神殿としての企業博物館
2 展示にみるカミとホトケの相克
3 スーパーと教会建築
第7章 経営者と宗教
1 経営者はなぜ宗教にひかれるのか
2 松下幸之助の経営宗教
3 船井幸雄の経営宗教
4 創世神話や終末論をこえて
エピローグ 宗教からみた経営
注
あとがき
索引

手塚治虫=ストーリーマンガの起源
講談社選書メチエ
ベストセラー『人は見た目が9割』著者による日本初の本格漫画評論!
手塚治虫の何が具体的に新しかったのか?なぜ戦後日本という時・場所に生まれ、かくも洗練された表現技法を手にするに至ったのか?「手塚治虫」という天才の膨大な発明群を1コマ1コマ精査し、ストーリーマンガの起源に遡行する。日本のマンガ研究はここから始まる!
第28回サントリー学芸賞【芸術・文化部門】受賞
【目次】
はじめに
第一章 手塚以前の漫画と戦後の漫画状況
1 手塚以前の漫画
2 先行する児童文化
3 手塚治虫、登場
第二章 アニメ、映画、SFと手塚マンガ
1 アニメの影響
2 映画の影響
3 SFの影響
第三章 手塚はマンガの何を新しくしたのか
1 演劇の影響
2 手塚の斬新さ
第四章 ストーリーマンガの方向性
1 『漫画少年』
2 劇画との葛藤
3 ストーリーマンガとは何か
註
あとがき
索引

喧嘩両成敗の誕生
講談社選書メチエ
中世、日本人はキレやすかった!大名から庶民まで刃傷沙汰は日常茶飯、人命は鴻毛のごとく軽かった。双方の言い分を足して二で割る「折中の法」、殺人者の身代わりに「死の代理人」を差しだす「解死人の制」、そして喧嘩両成敗法。荒ぶる中世が究極のトラブル解決法を生みだすまでのドラマ。
【目次】
プロローグ 現代に生きる喧嘩両成敗法
第一章 室町人の面目
笑われるとキレる中世人
殺気みなぎる路上
反逆の心性
第二章 復習の正当性
室町人の陰湿さ
「親敵討」の正当性
復讐としての切腹
第三章 室町社会の個と集団
アジールとしての屋形
武装する諸身分
復讐の輪廻
第四章 室町のオキテ--失脚舎の末路をめぐる法慣習
公認された「落ち武者」狩り
失脚者に群がる人々
「流罪」の真実
第五章 喧嘩両成敗のルーツを探る--室町人の衡平感覚と相殺主義
「二つの正義」の行方
「目には目を」--中世社会の衡平感覚と相殺主義
「折中の法」
中人制と解死人制
第六章 復讐の衝動--もうひとつの紛争解決策
能「正儀世守」を読む
室町幕府の本人切腹制
室町幕府の苦悩
第七章 自力救済から裁判へ--喧嘩両成敗の行方
分国法のなかの喧嘩両成敗法
統一政権と喧嘩両成敗法
赤穂事件--喧嘩両成敗法への憧憬
エピローグ 「柔和で穏やかな日本人」?
註
あとがき
索引

江戸の英吉利熱 ロンドン橋とロンドン時計
講談社選書メチエ
ベストセラー『春画』に続く第2弾!
鎖国下の知られざる日英視覚(ビジュアル)交流史
「この町はどういうわけかロンドンを思い出させる」鎖国期、江戸とロンドンはつながっていた――。将軍が愛したイギリス製時計、ロンドン橋を模写した旗本。イギリス発の科学技術に心奪われる文人。知られざる日英視覚交流を明らかにする「想像の交易」の物語。
【目次】
はじめに 想像の交易
第一章 平戸商館にて
第二章 布、鎧、ポルノグラフィ モノの交易をとりまく逸話
第三章 時計に憑かれた江戸っ子
第四章 江戸のロンドン
第五章 海を渡った美術品 屏風と遠眼鏡
第六章 絵の国イギリス
第七章 帝国主義イギリスの登場 憧憬から恐怖へ
結び 二重の歴史の物語
参考文献
注

帝国論
講談社選書メチエ
新たな闘いが始まっている
「帝国化」する世界を読み解くための全7章
21世紀、グローバル化する世界。<帝国>は脱領土化し、「言説空間」に闘争の場を移す。ネグリ/ハート『帝国』の問題提起を受け、「言説的権力としての帝国」によるヘゲモニー闘争として世界を読む画期的論考。

稲作の起源 イネ学から考古学への挑戦
講談社選書メチエ
縄文稲作はなかった
稲作のルーツは焼き畑農業ではない。サトイモなど水辺の根菜栽培に起源を持つ、「株分け」栽培から生まれた。イネ学最先端の知見から水田稲作という世界の農業上、最もユニークな農耕発生のメカニズムを解明し、照葉樹林農耕論をはじめとする定説の書き直しを迫る。
【目次】
序 章 イネに秘められた私たちの歴史
第一章 栽培イネの起源──通説への疑問
1 照葉樹林農耕論とは
2 「原農耕圏」の考え方
3 ヒマラヤ南麓起源説
4 これまでの稲作起源論の再検討
第二章 それは根栽から始まった──イネ栽培のルーツを探る
1 照葉樹林農耕論の問題点
2 根栽農耕の再説──サウアー説の紹介と再評価
第三章 根栽農耕への旅──雲南から東南アジアに痕跡をたどる
1 なぜサトイモを見るのか
2 今も残る根栽農耕を見る
第四章 どのようにしてイネは栽培化されたか
1 栽培化への前段階
2 野生イネから栽培イネへ
3 イネの変化が農耕を教えた
4 水田稲作は奇跡であった
第五章 水田稲作と「越」人──タイ語系人のアジア展開
1 最古の稲作遺跡は古代の「越」の都と重なる
2 稲作民の拡大と湛水水田農耕の発展
3 タイ語系の人々の生業と集落
4 イネはインドで独立に栽培化されたか
第六章 人間の歴史が刻まれたイネの多様性
1 インド型と日本型の差は何によるのか
2 東アジアにおけるインド型イネの起源
第七章 だれがどのように稲作を日本に
1 古代人の植物利用と帰化植物
2 「縄文農耕の証拠」をどう見るか
3 水田稲作の日本への伝来の背景
4 稲作伝来と弥生時代の幕開け
5 弥生中期と日本古代の稲作
終 章 水田稲作社会とは何か
1 雑穀農耕と稲作を基盤とする社会の違い
2 水田農耕という鋳型がつくった農民像
3 東アジアの水田農耕がもたらした社会
各章の事項への註
引用文献および引用註
あとがき
索引

江戸美人の化粧術
講談社選書メチエ
膨大な「化粧絵」に残されたメイク術、そして大宣伝合戦!
浮世絵に描かれたよく似た顔の女性、どう区別する? その女性の、未婚・既婚、子なし・子あり、さらには美人・不美人を一目で見分ける方法とは? 美人はいかにして美人となり、化粧品はいかにして宣伝されヒットし流通していたのか。膨大な「化粧絵」の向こうに見える江戸女性の真実。
【目次】
発端
第一章 江戸の美人を考える
1 三美人と七剣呑女
2 目を見つめると
第二章 化粧行為の描かれ方
1 「化粧絵」の向こう側
2 一目でわかる既婚者判別法
第三章 化粧の法則
1 江戸美人を洗ってみよう
2 剃る、切る、結う
3 白粉の秘密
第四章 江戸のマルチ広告 美艶仙女香
1 「どこにでも面を出す仙女香」
2 タイアップ広告と歌舞伎役者
注および参考文献
終局
索引
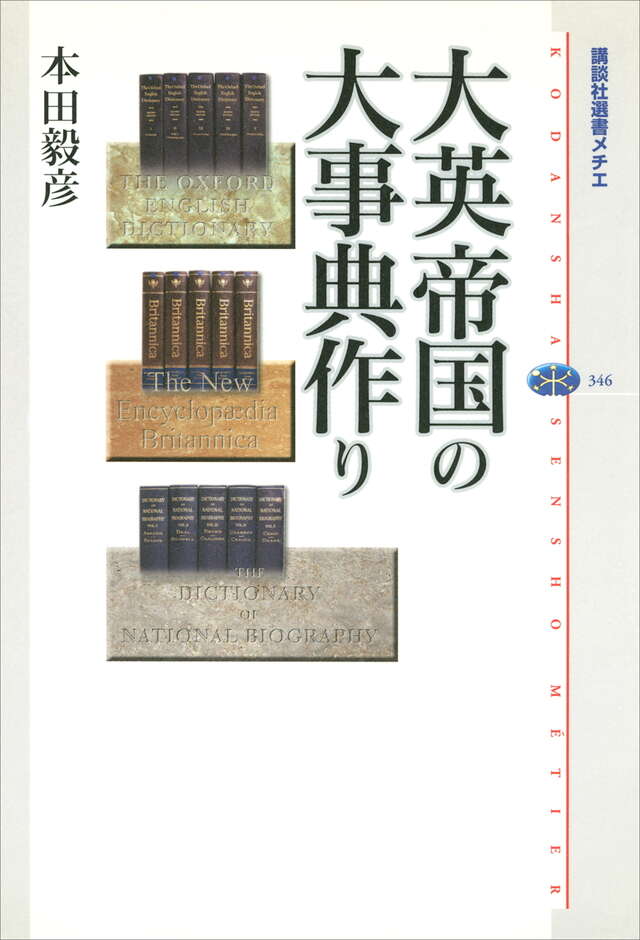
大英帝国の大事典作り
講談社選書メチエ
ブリタニカ、OED、DNB 大辞書、大事典プロジェクトにとり組んだ巨人たちの物語!
『ブリタニカ百科事典』Encyclopaedia Britannica 『オックスフォード英語辞典』Oxford English Dictionary 『イギリス国民伝記辞典』Dictionary of National Biography……。18世紀後半から19世紀後半にかけて、イギリス人はこの3つの大辞書、大事典を編纂した。世界をリードする気概にあふれた当時のイギリス社会は、なぜ、このような大事業を敢行したのか。それらは、どのように利用され、効果を発揮したのか。近代の知のインフラを整備した人々と歴史を検証する。
【目次】
序章 イギリス社会における「知」のインフラ──辞書・事典作りの伝統
第一章 『ブリタニカ百科事典』の歴史
第一節 一八世紀という時代
第二節 『サイクロピーディア』から『百科全書』へ
第三節 『ブリタニカ』
第二章 『オックスフォード英語辞典』の歴史
第一節 イギリスにおける辞書編纂の歴史
第二節 グリム兄弟と『ドイツ語辞典』
第三節 ジェイムズ・マリーと『OED』
第四節 『OED』に対する、現在の視点からの評価・批判
第三章 『イギリス国民伝記辞典』の歴史
第一節 イギリス人と伝記──ジョン・オーブリーからレズリー・スティーヴンへ
第二節 レズリー・スティーヴンの生涯
第三節 スティーヴンと『DNB』
第四章 三つの辞書・事典の現状と将来
あとがき
注
人名索引
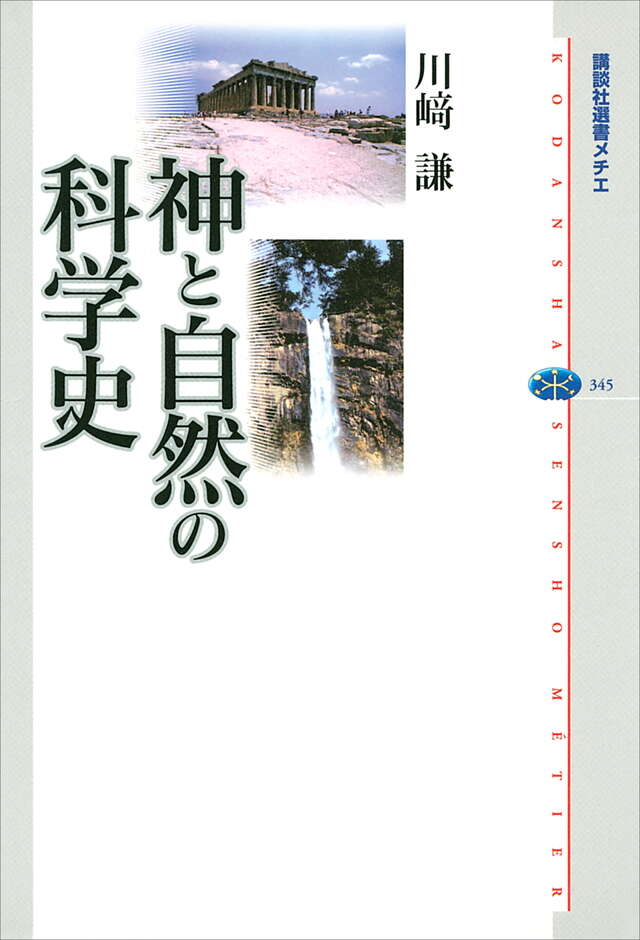
神と自然の科学史
講談社選書メチエ
「自然」と“nature”はどう違うか?
比較科学論への招待
先人が工業化のために受け入れた西欧自然科学は、私たちが母語で思考する力を奪ってしまった?西欧の“nature”と私たちの「自然」。彼我の自然観を互いに相対化することで初めて見えてくる、本当の「科学」の歴史。
【目次】
まえがき
ことばでは表せない自然のすばらしさ/同じではない「自然」と“nature”/普遍から個別へ、絶対から相対へ/異文化相互理解のために
序章 鏡としての西欧自然科学
本書の構成/西欧自然科学について学ぶ/異文化との不適切な遭遇/アヒル―ウサギ図のたとえ/歴史的眺望/鏡を用いた非西欧世界の自己発見
―第1部―
第一章 普遍性の正体
「技術」の普遍性/科学と技術の峻別/認識に優劣はない/認識とは・技術とは/技術と認識の相互往来/ガリレオの離れ業/【略】
第二章 ギリシア人の方法
言語相対性原理/西欧語の世界観/創造主の内なる「イデア」/実在しないイデア/物質界との峻別/幾何学的特性/ピュタゴラス→プラトン→聖アウグスティヌス/【略】
第三章 西欧自然科学の世界観
ひらめきの瞬間/ゴールを知らないマラソンランナー/ロゴスによって捉えられるもの/神の存在証明/初めに“Logos”があった/【略】
―第2部―
第四章 日本語の秩序に従う自然
翻訳の成功の陰に/枠組みが違えば/自然の誕生/漱石の自然/“Nature”ではない「自然」/察慮・量測スルコト能ハザル/【略】
第五章 諸法実相の枠組み
哲学―自分の枠組みを知る/「諸法」と「実相」の矛盾対立/道元の解釈/実相は諸法なり/日本的変容/神道的心情―諸法と実相を諸法に統一/【略】
第六章 実際の体験
誰の方法で考えるのか/諸法―物尽くしによる世界把握/量の問題/儒学・国学・和算/理科の実験の物尽くし/現象の救済/【略】
終章 比較科学論への招待
「それ自体は無意味の世界」から/透明な言語記号?/精神の不自由/さらに奇妙な牢獄/【略】
あとがきと謝辞
参考文献
索引

武器としての<言葉政治>
講談社選書メチエ
<小泉>圧勝の謎!歴代首相の政治術、「言葉」から完全査定!
利益分配が不可能な現代、民主主義を動かす要因は「議員の数」から「国民の支持率」へ劇的に変わった。その変化を前に、首相たちはいかにして「言葉」で国民の意識を変え、支持を動員してきたのか。言葉によって新たな政治的現実を創出し、不人気政策にすら国民的支持を動員する新・政治モデル〈小泉型政治手法〉。戦後歴代首相の「言葉の力」との比較から、この新しい政治手法の可能性と限界をダイナミックに考察する。
【目次】
序 〈言葉政治〉とは何か
第一部 〈言葉政治〉能力から見た歴代首相の評価
第一章 〈言葉政治〉の諸類型
1 言葉とはどういう武器なのか
2 政治を振りまわす言葉
第二章 〈言葉政治〉の時代区分
1 民主主義のレトリックの時代
2 国家建設のレトリックの時代
3 課題解決のレトリックの時代
第三章 稚拙・未熟な〈言葉政治〉
1 〈言葉政治〉から見た首相のタイプ
2 稚拙な〈言葉政治〉 竹下登、森喜朗、村山富市
3 理屈者の〈言葉政治〉 橋本龍太郎、宮澤喜一
4 未熟な〈言葉政治〉 細川護熙、海部俊樹、小渕恵三
第四章 〈言葉政治〉の衝撃
1 〈言葉政治〉の本格化 中曽根康弘
2 〈言葉政治〉の真骨頂 小泉純一郎
第二部 不利益分配時代を動かす〈小泉型政治手法〉
第五章 〈小泉型政治手法〉の有効性
1 議会の支持より国民の支持
2 利益分配政治から不利益分配政治へ
3 首相使い捨てvs. プチカリスマ
4 シニカルなニュースショーへの対応
第六章 〈小泉型政治手法〉の陥穽
1 ポピュリズム批判の是非
2 政治のパーソナル化の過剰
3 期待はずれの恐怖
あとがき 還暦を迎えた戦後政治
参考文献
索引
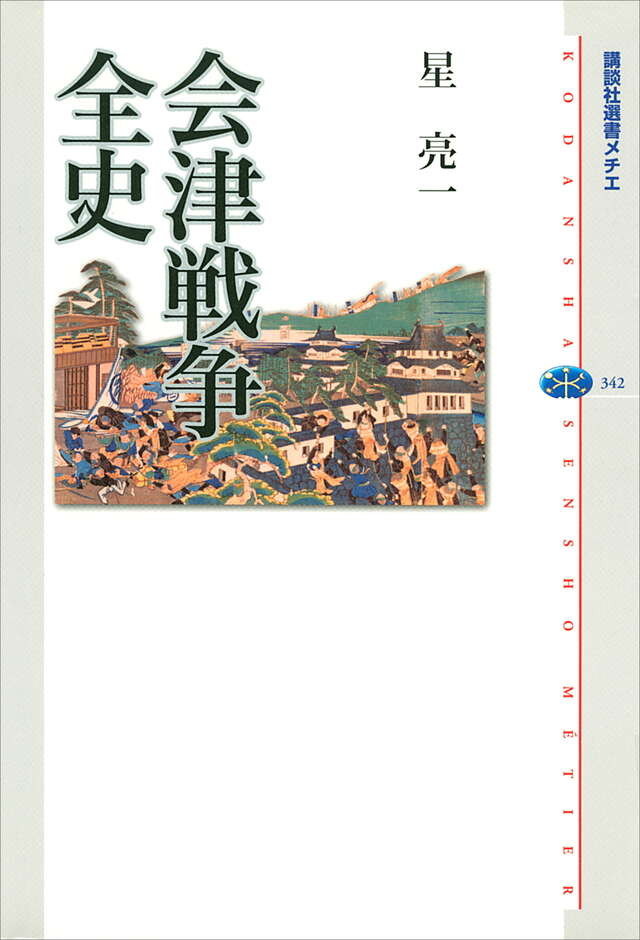
会津戦争全史
講談社選書メチエ
日本を割った大戦争、なぜ虐殺で終わったか?
会津戦争は「新政府軍と旧幕府軍の戦い」ではない。非寛容の精神で残虐行為に走る薩長軍に対して、奥羽越列藩同盟は新生国家のグランドデザインを突きつけ、正面から戦闘を挑んだのだ。しかし、戦略なき会津軍は「武士道」のもと非戦闘員をも動員し、悲劇へと突き進む――。幕末の会津藩を追い続けた著者が描く一大戦記。
【目次】
はじめに
長州兵の証言/会津戦争の盲点/薩長とどう向き合うべきか
第一章 鳥羽伏見の戦い
喜の独断専行/激しい動揺/「身死すとも癘鬼となる」/激怒する会津兵/戦争起こらず/【略】
第二章 戦火東北に迫る
慶応四年春の情勢/抜擢される若手実力者/都落ち/会津藩大改革/旧幕府軍からの挙兵/新潟が生命線/【略】
第三章 奥羽鎮撫総督
松島の海/決断を迫られる仙台藩/会津へ使者/容保との対面/仙台藩の決断/八百長戦争/中山口の談判/同志千二百人連中【略】
第四章 白河大戦争
白河城奪還/第一次白河戦争/官軍、大敗北/同盟軍の無策/第二次白河戦争/薩長軍奇襲、同盟軍壊滅/七〇〇人の兵に敗れた二五〇〇余人の軍団/地元民と兵士たちの証言/白河城奪還ならず/仙台に厭戦気分
第五章 越後、磐城に戦火拡大
越後に乗り込む佐川官兵衛/河井と佐川の衝突/河井継之助という人物/朝日山の決戦/長岡城の攻防/【略】
第六章 会津国境破れる
会津か、仙台か/母成峠の激闘1──薩長軍の証言/母成峠の激闘2──会津軍の証言/城中、色を失う/会津盆地にやすやすと侵入/無策/【略】
第七章 会津鶴ヶ城攻防戦
山川大蔵の彼岸獅子入城/若手抜擢の大改革/八月二九日、槍で銃弾に総攻撃/物量に勝る薩長軍/懐に忍ばされた遺書/【略】
第八章 白旗をかかげて降参
籠城婦女子の証言/降参の白旗/降伏交渉開始/降伏使を手綱で縛って連行/土佐の記述/最後の一ヵ月は立派だった容保/【略】
終章 会津戦争の意味
犠牲者の数/「人皆、悽愴せざるはなし」/北方政権構想/江戸の庶民は会津びいき/もし榎本が参戦していたら/【略】
あとがき
参考文献
索引

共視論
講談社選書メチエ
浮世絵に描かれた母子像は何を語るか
蛍、花火、しゃぼん玉。輝いて、そして消えていく対象を眺める母子。象徴を共有し、言語を使用するための基盤となるこの構図を日本人はなぜ好むのか?「共視」する母子を取り囲む「場」の文化とは?精神分析学をはじめ、さまざまな分野の新しい知見をもとに考察する、視線をめぐる人間論。

知の教科書 論理の哲学
講談社選書メチエ
論理学と哲学の最前線
20世紀、論理学と哲学を横断して起きた「知の革命」。パラドクス・無限・不完全性と完全性・言語と論理・計算機科学と論理学などをキーワードに、論理をめぐる哲学探究の刺激に満ちた現在を、気鋭の著者陣が解説する。
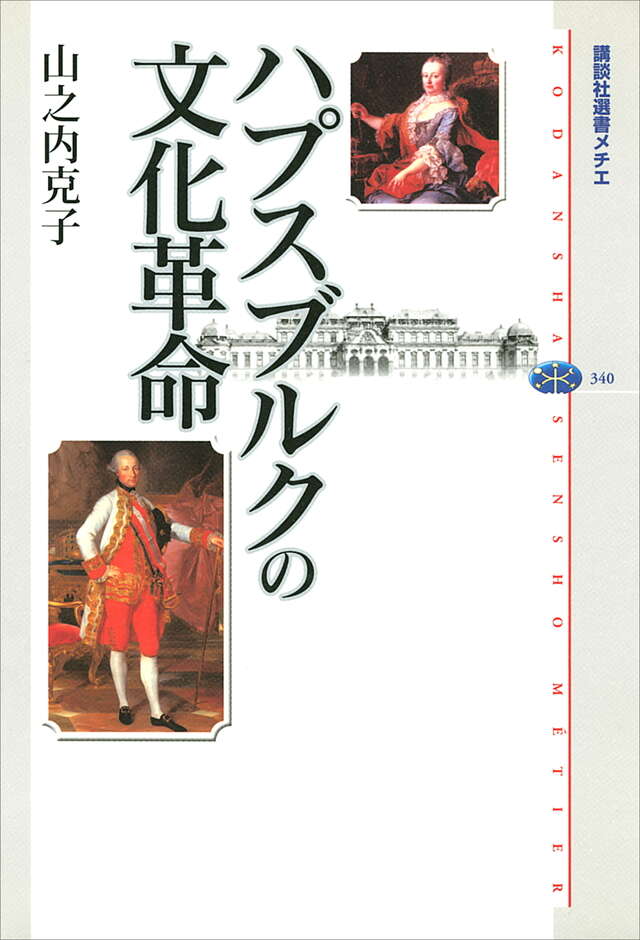
ハプスブルクの文化革命
講談社選書メチエ
全市民に娯楽と余暇が開放された、ウィーンの「文化革命」とは何か?
豪華な儀式と祝祭でスペクタクルを演出し、視聴覚から臣民を従えたマリア・テレジア。庭園も舞踏会も一般公開する一方で、自分は宮廷に引きこもるヨーゼフ2世。同時代の記録に残された膨大な都市民の肉声から、啓蒙専制君主に再編される市民生活の相貌を活写する。
【目次】
関連地図
はじめに
第一章 北方からのまなざし──ドイツ啓蒙主義者がみたウィーン
1 「啓蒙の聖地」ウィーン
2 「パイアケス人の国」──旅行記が描く十八世紀ウィーン
3 「カトリック宮廷都市」における啓蒙主義
第二章 マリア・テレジアとウィーンの宮廷文化
1 ハプスブルク帝国の中央集権化と宮廷社会
2 「スペクタクルは君主の務め」──マリア・テレジアと宮廷行事
3 ウィーンの謝肉祭
第三章 都市の時空を画すもの──宗教行事・伝統的スペクタクル・演劇文化
1 伝統的娯楽のかたち
2 啓蒙専制主義と余暇の管理
第四章 ヨーゼフ二世── ハプスブルクの「革命児」
1 啓蒙君主の教会改革と娯楽観
2 新しい娯楽習慣とヨーゼフ主義の実現過程
第五章 緑地へ向かう都市民──近代的余暇習慣のステージ
1 ウィーンの庭園──世界支配の象徴から至福の園へ
2 公共緑地と散策習慣
3 日曜日の散策者たち──娯楽の諸要素の再統合
第六章 「中心の喪失」 ヨーゼフ二世の宮廷改革
1 儀式なき宮廷、「私」としての皇帝
2 宮廷儀式の「親密化」
終 章 バロック的宮廷都市から市民的近代都市へ
1 メトロポリス・ウィーンと新しい都市文化
2 啓蒙主義の「再発見」
ハプスブルク家略系図
注
あとがき
索引

ミシシッピ=アメリカを生んだ大河
講談社選書メチエ
「偉大なる褐色の神」を旅する
ミシシッピはアメリカという林檎を貫く「芯」である。
この川を知らなければアメリカは語れない! ニューオーリンズの情熱的なクレオール文化。デルタの苛酷な環境が生んだブルース。公民権運動の舞台メンフィス……なぜジャズはニューオーリンズで生まれたのか。先住アメリカ人が辿った涙の旅路とは? NYや西海岸を見てもわからない、アメリカの本質を探る4千キロ縦断の旅。
【目次】
プロローグ アメリカのなかのミシシッピ
第一章 ミシシッピ七つの道
1 探検の道
2 輸送の道
3 人が変えた道
4 移住と入植と政治の道
5 自然の道
6 文化の道
7 国家の精神的な中心としての道
第二章 川がはぐくんだ文化 河口からニューオーリンズへ
1 河口の「発見」
2 ニューオーリンズの町と住人
3 ジャンバラヤとガンボの国 ケイジャン・カントリー
4 プランテーション王国
第三章 デルタをゆく
1 オールド・リヴァー・コントロール
2 ナチェズに魅せられた人びと
3 ヴィクスバーグと南北戦争
4 デルタ地帯 綿花・ブルース・ナマズ
5 メンフィス 公民権運動と音楽の史跡
6 ミシシッピを往来する木・船・人
第四章 ミシシッピとマーク・トウェイン セントルイスからハンニバルへ
1 セントルイスが生んだ人びと
2 ハンニバル=マーク・トウェインのふるさと
第五章 ミシシッピから歴史が見える ノーヴーから四つ子都市まで
1 ノーヴーとモルモン教
2 「川の町」としての四つ子都市
第六章 源流へ
1 双子都市 ミネアポリスとセントポール
2 源流の探索者たち
エピローグ ミシシッピとは何か
参考文献