講談社選書メチエ作品一覧

芭蕉歳時記 竪題季語はかく味わうべし
講談社選書メチエ
移ろいゆく日本の四季の、息をのむ美しさ。その繊細なイメージを、和歌以来の伝統にたたえる「竪題季語」。芭蕉はこの伝統の上に、いかに新たな美を生みだしたのか。「鶯」「春雨」「蛍」「紅葉」など代表的季語60で味わう、俳聖の豊饒な宇宙。
【目次】
季語入門
●春
立春/鶯/梅/春雨/雲雀/花/蛙/山吹/藤
●夏
更衣/卯花/郭公/菖蒲/蛍/夕顔/蝉/納涼
●秋
七夕/萩/薄/女郎花/野分/鹿/雁/月/菊
●冬
時雨/落葉/枯野/霜/千鳥/雪/埋火/歳暮
竪題季語一覧
あとがき

能に憑かれた権力者 秀吉能楽愛好記
講談社選書メチエ
「のふにひまなく候」。晩年、能に取り憑かれた秀吉は、前代未聞の禁中能を催す。宮中に、秀吉、家康、利家が舞い、輝元の小鼓が響きわたる。自らの生涯を「10番の能」に新作させ、能楽史を変えた権力者の凄まじい熱狂に迫る。
【目次】
はじめに
序章 武将の能楽愛好 秀吉まで
第一章 名護屋以前
1 周辺の能役者
2 天正十年代概観
3 先達としての秀次と秀長
第二章 文禄2年肥前名護屋
1 『甫庵太閤記』から
2 熱中のはじまり
3 名護屋での熱狂
4 熱中のなごり
第三章 文禄二年禁中能
1 文禄二年禁中能の概要
2 文禄二年禁中能の諸相
3 その後の禁中能
第四章 能楽三昧の日々
1 のふにひまなく候
2 吉野・高野での能
3 能を楽しむ日々
4 秀吉の能舞台
第五章 豊公能の新作
1 豊公能と大村由己
2 豊公能を読む
第六章 秀吉の能楽保護
1 南都両神事能の復興
2 猿楽配当米
終章 秀吉以後
注
秀吉能楽愛好関連年表
あとがき
索引

アメリカン・ファシズム ロングとローズヴェルト
講談社選書メチエ
デモクラシーの行きつくところ、ファシズムの影がしのびよる! 1930年代ルイジアナ州。不正選挙により史上空前の独裁を打ち立て、大統領の座をも狙った稀代のデマゴーグ、ヒューイ・ロング。ローズヴェルトがもっとも恐れた彼の軌跡をたどり、民主主義社会の陥穽を検証する。
【目次】
序章――アメリカにファシズムはあったのか
第一章 〈見える支配〉と〈見えない支配〉
1 ヒューイ・ロングの三大要素
2 〈見えない〉支配
3 顕在化する〈見えない支配〉
第二章 ロングVS.ローズヴェルト
1 呪われたアメリカとロングの夢
2 ローズヴェルトの憂鬱と怒り
3 「クローフィッシュ」ヒューイ・ロング
4 連邦/反対派の「響きと怒り」
5 FDR政治のロング化
第三章 ルイジアナ独裁
1 課税による検閲
2 司法権の強奪
3 もっとも恐ろしい男の反撃
4 血みどろのペリカン州
第五章 だれがロングを殺したのか
1 一九三八年九月八日
2 カール・オースチン・ワイスは犯人なのか
3 殉教と陰謀のはざまに
4 ひとつの仮説
5 なにがロングを殺したのか
終章――キングフィッシュの影の下に
註
あとがき
年表
索引

ユダヤ教の誕生
講談社選書メチエ
放浪、奴隷、捕囚――1000年もの民族的苦難のなかで、遊牧民の神は成長し、ついには全宇宙を創造・支配する唯一神ヤハウェに変貌する。キリスト教、イスラームを生み、歴史の果てにイスラエル国家をも造り上げた「奇跡の宗教」誕生の謎に、「聖書」を精緻に読み解きつつ、決定的に迫る。

ドイツ「素人医師」団 人に優しい西洋民間療法
講談社選書メチエ
18世紀ドイツが生んだ、「西洋の漢方」としてのホメオパティー。自然治癒力を重視する独自の療法は、フランス、オーストリア、アメリカへと広まっていく。19世紀、その信奉者たちが提唱し、ヨーロッパ医学界を震撼させた「素人医師」運動を軸に、近代医学の相克と、再び見直される現代の意義とを明らかにする。
【目次】
プロローグ 「西洋の漢方」ホメオパティー
第一章 ホメオパティー理論の誕生
1 近代医学はどのようにして成立したか
2 ハーネマンの修業時代
3 新らしい治療原則の発見
4 ホメオパティー理論の確立
5 戦うハーネマン
6 ホメオパティー、医学界を騒がす
7 晩年のハーネマン
第二章 近代医学の歩み
1 近代医学の夜明け
2 医学教育の改革
3 医学生の出自の特色
4 医師の「経済闘争」
5 偉くなった医師
第三章 近代医学へのアンチテーゼ
1 ホメオパティーは近代医学より効く
2 素人医協会設立さる
3 素人医協会の活動
第四章 素人医たちの反種痘運動
1 種痘は安全ではなかった
2 反種痘キャンペーン
3 近代医学批判としての反種痘運動
第五章 ホメオパティー運動の「転向」
1 素人医(ハーネマニア)協会の変質
2 ホメオパティー講座設置運動
3 奨学金財団の設立
4 ホメオパティー病院建設運動
5 素人医とホメオパティー医の対立
6 素人医運動の意義
エピローグ 現代によみがえるホメオパティー
あとがき
註
索引

北の十字軍
講談社選書メチエ
時は中世、ヨーロッパ北方をめざす「もう1つの十字軍」があった。教皇の名の下、「異教徒を根絶」すべく残虐の限りを尽くすドイツ騎士団。それを正当化した「思想」とは何か?大殺戮批判が生んだ「人権思想」とは?3世紀に及ぶゲルマン・スラブの相克から「大航海期」までをも展望し、ヨーロッパ拡大の理念とその矛盾を抉りだす。
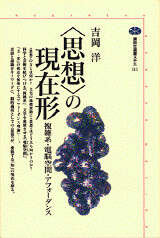
<思想>の現在形 複雑系・電脳空間・アフォーダンス
講談社選書メチエ
〈思想〉の力とは何か?文化の地殻変動に〈思想〉はどう立ち向かうのか?科学と芸術を結びつける「複雑系」、文学を変質させる「電脳空間(サイバースペース)」、「主―客」の視点を無効にする「アフォーダンス理論」……。言語と認識をキーワードに、動的過程としての〈思想〉が、変貌する「知」の現在を探る。
●〈知〉の境界への出発
●人工自然としての言語――もうひとつの電脳空間(サイバースペース)論
●進化としての〈脱構築〉――ポストモダン再考
●〈複雑系〉の哲学――認識の新たな形
●環境と判断――アフォーダンスのラディカリズム
●インターフェイスとしての思想
●第三の文化へ
【目次】
序章 〈知〉の境界への出発
第一章 人工自然としての言語 もうひとつの電脳空間(サイバースペース)論
1 サイバースペースの本質
2 爆発する情報空間
3 言語状況への視座
第二章 進化としての〈脱構築〉 ポストモダン再考
1 ポストモダンの射程
2 言語の混沌(カオス)
3 生成としてのポストモダン
第三章 〈複雑系〉の哲学 認識の新たな形
1 近代思想の舞台
2 知覚システムとしての〈近代〉
3 認識のダイナミズム
第四章 環境と判断 アフォーダンスのラディカリズム
1 判断の反射
2 生態学的転回=アフォーダンス
3 反省的判断力の原理
終章 インターフェイスとしての思想
1 〈思想〉のダイナミクス
2 第三の文化へ
注および参考文献
あとがき
索引

大英帝国の<死の商人>
講談社選書メチエ
軍艦、大砲を世界にあふれさせたアームストロング、ヴィッカーズ……。動乱の影には、つねに巨大な「死の商人」たちの姿があった。7つの海を支配した帝国の覇権のもと、彼らはどう行動したのか?近代の宿痾「武器輸出」――その構造を歴史的に抉りだす。
●幕末維新を武器からよむ
●アフリカの悲劇
●イギリス銃産業の興亡
●海軍恐怖・虚偽情報・賄賂
●巨大企業、アームストロング社
●軍縮と武器輸出
●兵器産業国有化論争
【目次】
序章 「死の商人」とは何か
第一章 幕末維新を武器から読む
1 薩長、イギリスに完敗す
2 佐賀藩、大砲を作る
3 洋銃、日本に流入す
第二章 アフリカの悲劇
1 銃と奴隷と
2 列強の思惑
第三章 イギリス銃産業の興亡
1 ロンドン万国博覧会
2 産業革命なき産業
3 バーミンガムの黄昏
第四章 海軍恐怖・虚偽情報・賄賂
1 「帝国」を防衛せよ
2 マリナー・パニック
3 シーメンス事件
第五章 巨大企業、アームストロング社
1 アームストロング社と日本海軍
2 兵器ひとすじに生きた男
3 軍艦製造への進出
第六章 軍縮と武器輸出
1 兵器産業の「危機の二〇年」
2 方針転換
3 アメリカからの逆風
第七章 兵器産業国有化論争
1 王立調査委員会
2 白熱するやりとり
3 「死の商人」の裏切り
註
あとがき
関連年表
索引

「隔離」という病い
講談社選書メチエ
強制収容、恐怖の宣伝、終身隔離。
なぜ、ハンセン病患者への過酷な差別は、現代まで続いたのか?
なぜ、近代の医療空間は、これほど歪められたのか?
O-157、エイズを含め、日本社会の「病い」観を問いなおす。
〔本書の内容〕
●文明国という盛装
●見えない病棟
●フーコーの図式
●「死と再生」のドラマ
●「かい」と「生きがい」のあいだに
●最小国家
●冷たい義理

戦国城下町の考古学 一乗谷からのメッセージ
講談社選書メチエ
政治の中心「朝倉館」、庶民の生活の跡をとどめる「町並」、人の盛衰を記す石仏、「かわらけ」の山……。まるごと発掘された越前一乗谷は、中世考古学の絶好の素材となった。
発掘資料と歴史史料を駆使し、中世の空間を立体的に再現する力作。
〔本書の内容〕
●一乗谷からのメッセージ
●一乗谷と戦国城下町の景観
●中世人の空間意識
●町屋と人びとの生活
●都市を支えた商品──生産と流通
●越前の中の一乗谷
【目次】
序章
第一章 一乗谷と戦国城下町の景観
1 一乗谷のイメージ
2 城戸の内と外 ふたつの町
3 城下町と権力のモデル
4 町割 一乗谷の都市計画
5 城戸の外はもうひとつの町
6 一乗谷はいつでき、いつ滅んだか
第二章 中世人の空間意識
1 朝倉館の空間構成
2 館の系譜と規範
3 富と権力を映す陶磁器
第三章 町屋の人びとのの生活
1 一乗谷の町屋
2 町屋の構造
第四章 都市を支えた商品 生産と流通
1 一乗谷アセンブレッジ
2 消費をどんぶり勘定する
3 生産地の対応
4 町と村の陶磁器消費
5 中国陶磁の果たした役割
6 消費財の考古学
7 日本列島、東と西・表と裏
第五章 越前の中の一乗谷
1 領国支配と経済ブロック
2 一乗谷の位置づけ
注・引用文献
年表
あとがき
索引

裂ける大地 アフリカ大地溝帯の謎
講談社選書メチエ
サバンナは1億年後、海になる!
6000キロにおよぶ大地溝帯で、今も大陸地殻が分裂しているのだ。そしてこの地で数々のドラマが展開した。人類の発生、カーボナタイトの噴出、ダイヤモンドの誕生、滝の移動……。アフリカ地質学研究の成果によって、様々な興味あふれる現象を解読する。
【目次】
序章
第一章 東アフリカ大地溝帯
1 グレゴリーとランボオ
2 陸が海になる
3 引き裂かれる東アフリカ 紅海地溝帯とアデン湾地溝帯
4 大地溝帯の形成
5 大地溝帯を造った力
6 初期人類化石の宝庫
第二章 大地溝帯を読む
1 ホットプルーム
2 オルドイニョ・レンガイ火山の驚異
3 カーボナタイトの探究
4 地形の逆転 ヤッタ台地
5 鉱物粒界の謎
6 大地溝帯の底になにがあるか
第三章 もうひとつの大地溝帯
1 一億年前の大地溝帯
2 大陸の分裂
3 ダイヤモンドの母岩 キンバレー岩
4 セイシェル諸島の大移動
5 不思議なヴィクトリア滝
6 砂漠化とは
7 砂漠の砂
第四章 アフリカ大陸をゆく
1 地質学徒の眼
2 アフリカこぼれ話
3 アフリカを往く 立松和平氏との対談
参考文献
あとがき
索引

視線の物語・写真の哲学
講談社選書メチエ
写真という「自然の鉛筆」。そこに、潜在する数多の未知の物語。「撮る」「撮られる」「見る」――三つの視線は決して収斂しない。宙づりの視線たちが紡ぎだす多義的な物語とは?カメラ・アイに潜む「匿名の視線」とは?
「写真行為の哲学」が、あらたな視線の倫理(エートス)を要請する。
【目次】
はじめに 新たな視覚体験
第一章 写真という物語
1 「イコン=インデックス」
2 〈おわった〉構造
3 物語化する装置
第二章 アイデンティティーのゆらぎ 肖像写真
1 自己像の物語
2 肖像写真の修辞学
3 カルト・ド・ヴィジット
第三章 イメージ・デモクラシー
1 名士の写真
2 イメージ・デモクラシーの逆説
3 自己像の分裂と修復
第四章 外貌の解釈学 顔写真
1 他者経験の変容
2 「平均的人間」の理想
3 窃視の体系
4 権力の官能化
第五章 欲望のファンタジー ポルノ写真
1 脚のフェティシズム
2 ポルノ写真のイコノグラフィー
3 フェティッシュ化のメディア
4 性的身体の肖像
第六章 写真行為のエートス 報道写真
1 「カメラをもつ人間」という存在
2 写真とことば
3 まなざしの回復
主要参考文献
あとがき
索引

現代思想で読むフランケンシュタイン
講談社選書メチエ
1816年、夏の夜が生んだ「現代の神話」――「人はその被造物に復讐される」。啓蒙の限界、革命の矛盾、自然科学の将来…。そのテクストは驚くほど予見的だった。
メアリー・シェリーの原作と、それを変容させていった映画の意味を、神話学、人類学、精神分析の成果を駆使して精緻に読み解く。

住宅道楽 自分の家は自分で建てる
講談社選書メチエ
陳腐で奇妙で高価格。地球上最悪の住宅の現実が、日本にある。無の境地をめざす「究極の家」、アライグマと暮らす家、棺桶を模した「ドラキュラの家」、そして「村」と名づけたみずからの住居(シェルター)。
「住宅設計戦線」に挑む建築家が、提示する自由な住宅像の数々。「自分の家を自分で建てる」ことの意味と楽しみを、熱く説く。
【目次】
はじめに
第一章 住宅建築家宣言
1 住宅を設計するというのはどういうことか
2 敗者復活戦
第二章 小住宅の可能性
1 ドラキュラの家
2 崩壊を待つ風景
3 アクシデントとしての小住宅
第三章 究極の家へむかう
1 井上さんの家を東京に建てた
2 究極の家
第四章 新しい依頼者の登場
1 変テコリンな依頼主
2 アライグマ・ギンの家
3 ギンの独白
第五章 自分の家は自分で建てる
1 住宅設計の受け皿づくり
2 「左官の家」計画
3 住宅価格の根本問題
第六章 「世田谷村」計画
1 住宅像の極北をめざす
2 夜の裸電球
あとがき

大名庭園
講談社選書メチエ
江戸の大名達が競って造った大庭園─―後楽園、六義園、浴恩園……。それらは京の庭園をしのぐ造形をもった「社交」と「儀礼」の装置であった。初めて「大名庭園」の真実の姿に迫り、京都一辺倒の日本庭園史をくつがえす。

ヒトラー暗殺計画と抵抗運動
講談社選書メチエ
「七月二十日事件」、白バラ、赤い楽団、告白教会……。反ヒトラー、反ナチズムの運動はどこまで有効だったのか? 抵抗の様々な形を掘りおこし、ドイツ現代史の中に位置づける力作。
【目次】
第一章 帝国議事堂炎上
1 帝国議事堂放火事件
2 強制的同一化
3 最初の抵抗者
4 抵抗者はなにに抵抗したか
第二章 国防軍
1 国家防衛軍から国防軍へ
2 忠誠の誓い
第三章 教会の苦闘
1 ドイツ・キリスト者と帝国教会
2 コンコルダートと回勅『燃える如き憂慮をもって』
第四章 抵抗者たち
1 共産党
2 社会民主党とその周辺
3 国防軍内の抵抗勢力
4 文民エリート
5 赤い楽隊
6 若者たち
7 孤立と分断の中で
第五章 ヒトラー暗殺未遂事件
1 一九四四年七月二十日
2 「七月二十日の反逆者」逮捕と裁判
第六章 抵抗をめぐって
参考文献
あとがき

フーコーの系譜学 フランス哲学〈覇権〉の変遷
講談社選書メチエ
危機の20世紀はフランスの〈知〉をいかに変えたか? 「ニヒリズム」に抗し、生命の躍動を歌うベルクソンと、意識の自由を掲げるサルトルを経て、「理性」と「権力」の実像を暴くフーコーへ。時代と格闘し、哲学を深化させた三巨匠を、鮮やかに読み解く意欲作。
【目次】
まえがき
プロローグ 哲学の現実化の道
第一章 ベルクソン 生命の躍動
1 『時間と自由』 自分の心をとらえる
2 『物質と記憶』 心と身体の関係
3 『創造的進化』 生命進化と知性
4 『道徳と宗教の二源泉』 人類愛への飛躍
第二章 サルトル 実存の不安
1 『存在と無』 意識の自由
2 『方法の問題』 実存と知
3 『弁証法的理性批判』 実存主義と弁証法
第三章 フーコー 悲劇と権力
1 『狂気の歴史』 理性という暴力
2 『言葉と物』 人間の有限性
3 『監獄の誕生』『性の歴史』 権力から倫理へ
エピローグ 三角形の問題空間=ベルクソン・サルトル・フーコー
あとがき
参考文献
索引
あとがき
参考文献
索引

裏切り者の中国史
講談社選書メチエ
王朝に背き、夷狄に国を売った稀代の「悪漢」たち。権力・復讐・女を求めて疾駆した彼らの得たものは?漢の王莽、唐の安禄山、南宋の秦檜……。興亡絶えざる中華世界に暗く輝く反逆者列伝。

オペラ座 「黄金時代」の幻影劇場
講談社選書メチエ
時はルネサンス。君主翼賛の祝祭を種に、古代憧憬を養分に肥大する宮廷の文化装置。失われた牧歌風景(アルカディア)を求め、冥界=洞窟(グロッタ)をも抱え込む迷宮の舞台……。下って19世紀、巨大オペラ座=「メロドラマの殿堂」をへて、孤独な「電気城」へと到達する。ヨーロッパの過剰なる観念が跳梁する官能の劇場……。それがオペラ座。
【目次】
はじめの口上
第一章 パリ・オペラ座に棲む怪人 メロドラマの殿堂
1 コンプレクスの形
2 享楽のファンタスマゴリア
3 人工楽園
第二章 牧歌への憧憬 よみがえる古代ギリシア
1 失われた「黄金時代」をもとめて
2 鄙の夢・官能の庭
第三章 跳梁する運命の女神 ルネサンスの寓意像
1 運命の女神フォルトゥーナ
2 幻惑の魔女
第四章 古代牧歌の戦士 模擬戦としてのカルチョ
1 廷臣の鑑
2 根拠をプレイする
第五章 冥界のオルフェウス 洞窟と豊饒の音楽
1 岩塊風景
2 豊饒儀礼
3 人工洞窟のオルフェウス
第六章 脳髄の劇場 電気牧歌の世紀末
1 ガラス越しに見る
2 伝染病
3 ひとり用オペラ
おしまいに
主要参考文献
あとがき
索引

<清潔>の近代 「衛生唱歌」から「抗菌グッズ」ヘ
講談社選書メチエ
欧米列強に対抗し、病原菌ゼロをめざして、国家衛生システムを張りめぐらせた明治日本。「衛生唱歌」「衛生博覧会」など精力的な啓蒙は、軍国の強健・健康美志向へと変容していく。そして現代。「抗菌グッズ」=異常潔癖ブームの彼方に、「清潔空間」のグロテスクな未来を透視する。
【目次】
プロローグ 清潔な国ニッポン
第一章 江戸時代の健康維持システム
1 近代医学以前
2 養生書の時代
3 常在薬というシステム
4 神仏の力
第二章 「清潔」の発見
1 都市という不潔
2 風呂好き日本人
3 西欧の巨大清潔装置
第三章 コレラ侵襲の衝撃
1 「衛生の母」としてのコレラ
2 細菌学革命
3 コレラ騒動
第四章 衛生国家への道
1 環境大国日本
2 明治衛生システムをつくった人々
3 長与専斎 衛生行政の先駆者
4 後藤新平 衛生システムの構築者
5 国家衛生の成立
第五章 衛生博覧会という装置
1 博覧会の世紀の中で
2 流行語としての「衛生」
3 恐怖と好奇のメディア
第六章 「衛生」の変貌 健康美へ、強健へ
1 明治・大正の養生書
2 健康美人の賞揚
3 国家のための強健な身体
第七章 「清潔空間」の完成
1 衛生ランド
2 ネオ養生の世界
3 漠とした不安
エピローグ あとがきにかえて
索引