講談社選書メチエ作品一覧

英国式庭園 自然は直線を好まない
講談社選書メチエ
なだらかな草原、ゆるやかにうねる小川。18世紀英国が生み出した「西欧庭園の革命」──風景式庭園。ささやかな敷地に色とりどりの花が咲き乱れる「なつかしい庭」──コティジ・ガーデン。緑なすイングランドを舞台に、「楽園の夢」実現にかけた英国人の飽くなき情熱をたどる。
【目次】
はじめに
序章 英国式庭園の謎と魅力
第一章 ローマ時代から中世まで
1 ローマ占領時代
2 中世の庭園
第二章 ルネッサンス 宮廷から海外へ
第三章 一七世紀 内乱の時代から名誉革命へ
1 火薬、反逆、陰謀事件
2 イタリア・フランス様式の導入
3 オランダの影響
第四章 英国式庭園の誕生
1 「自然な庭」の誕生
2 過渡期 庭の囲いをはずす
3 風景式庭園の確立
4 ピクチャレスクとゴシック
第五章 楽園を求めて
1 より豊かな庭に
2 楽園の夢
3 プラント・ハンターの時代
第六章 ヴィクトリア朝の庭
1 ガードネスク 庭らしい庭を求めて
2 コティジ・ガーデン 「ありふれた庭」の魅力
3 失われる庭
終章 小さなコティジ・ガーデンと公共庭園 二〇世紀から未来へ
1 二〇世紀の庭
2 庭園の未来 公共の公園へ
註
あとがき
参考文献
索引

漱石の記号学
講談社選書メチエ
明治という時代。激変する社会にあって、「次男坊」や「主婦」は、いかなる存在だったのか?また「神経衰弱」という病はどんな意味を持ちえたのか?小説中の、一見小さな事柄を「文化記号」をしてとらえたとき、代助、三千代ら揺れ動く人びとの「生」は、鮮やかにその姿を現す。漱石の豊饒なテクストを横断して示す、犀利な「読みの方法」。

江戸の市場経済 歴史制度分析からみた株仲間
講談社選書メチエ
最先進国イギリスに匹敵する経済成長をとげた「江戸日本」。巨大市場の成立は、安定政権、貨幣制度の整備、農商工分離だけでは説明できない。〈株仲間〉こそが、全国市場の形成・発展の立役者だった。歴史制度分析という最新の方法を駆使し、株仲間のポジティブな役割に光をあてる。
【目次】
はじめに
第一章 経済史の新しい見方
1 新古典派経済学 市場の経済史
2 マルクス経済学 市場と分配の経済史
3 新制度学派経済学 制度と所有権の経済史
4 歴史制度分析 ゲーム理論からみた制度と契約の経済史
第二章 近世の市場経済
1 経済発展の展開と市場の機能
2 社会的分業の展開と市場の機能
第三章 行政・司法制度と法
1 徳川政権と制度の整備
2 法と裁判制度
3 相対済令
第四章 株仲間の歴史
1 株仲間の成立
2 天保の株仲間停止令と嘉永の問屋再興令
第五章 株仲間と市場経済
1 株仲間停止と取引秩序の混乱
2 経済成長率の低下と市場機構の機能低下
第六章 取引制度としての株仲間
1 中世地中海の取引制度 グライフの分析
2 株仲間による商取引契約の履行
3 生産活動の組織
おわりに 市場経済と制度

ビザンツ 幻影の世界帝国
講談社選書メチエ
12世紀。戦わずして勝つをモットーに、「世界の富の3分の2」を駆使し、世界帝国として君臨したビザンツ。目眩めく祝祭、膨大な多民族軍、老獪な外交。ローマ1千年の智恵を結集し、地中海の盟主の座を守り続けた老大国の華麗なるサバイバル戦略。
【目次】
プロローグ 大ローマ帝国の幻影
第一章 血族と混血児の宮廷
1 コムネノス朝の成立 コムネノス・ドゥーカス家門同盟の政権
2 爵位制度の改革
3 閉鎖的支配集団の形成
4 近親間の暗闘
第二章 微笑と歓待による「戦争」
1 マヌエル帝の造営事業
2 高貴な来訪者の歓待
第三章 コンスタンティノープルという名の「快楽」
1 世界の首都、異邦人の楽園
2 祝祭空間の政治性
3 広場の風景、庶民の暮らし
第四章 多民族軍団の世界制覇事業
1 異邦人に守られた帝国
2 宝玉の軍団
3 王者の戦い
第五章 白日夢の終焉
1 ヴェネツィア人との軋轢
2 ミュリオケファロン 虚構の帝国の崩壊
3 打算的なコスモポリタンの孤独
エピローグ 皇帝の死
註
あとがき
参考文献
人名索引

ヘ-ゲル『精神現象学』入門
講談社選書メチエ
1807年。哲学界に未曾有の書が現れる。〈無限の運動〉の相のもと、およそ人類がもつ、知の全貌をとらえる究極の書。目前の木の認識に始まり、世界全体を知りつくす「絶対知」にいたるまで。文明の始原から近代ヨーロッパの壮大な知まで──。人間精神のあらゆる領域を踏破する、哲学史上最難解の書を、「ヘーゲル翻訳革命」の著者が、明快に読みつくす。

江戸のアウトロ- 無宿と博徒
講談社選書メチエ
膨張する百万都市、江戸。
農民たちがその底辺に吸い込まれてゆく。博打に身を持ち崩す者は、商品経済の荒波に呑まれた単なる窮民なのか?それとも身分制の桎梏(しっこく)を脱して己の夢に生きようとした果てなのか? 国定忠治、鼠小僧次郎吉、そして無数の無宿(アウトロー)たち……。
史料の向こうにかれらの生死を見つめ、等身大の近世社会史を構想する。
【目次】
はじめに 無宿のイメージ
第一章 無宿横行
1 大戸の関所の捨て札 国定忠治
2 笹川の貸元の大いちょう 万歳村勢力一件
3 世間広く縦横自在なり 武陽隠士の嘆き
4 島に送られ屋根を葺く
第二章 発生のメカニズム
1 頼る術なく食べるに窮し
2 おくゆかしき人と存ぜられ候
3 江戸の口入れ、店借層
4 無罪の無宿の片付け
第三章 「有宿」と「無宿」の境界
1 野非人と非人制道
2 追放制限と佐渡の水替え
3 欠落と帳外れ
4 箱根の山は天下の険か
第四章 世直しの足音
1 村を出る者、残る者
2 寄場人足の世界
3 仕切り契約する用心棒
4 在々商人の分限
第五章 無宿が精彩を放つ時
1 「義賊」の正体 鼠小僧
2 飯売女は公卿の息女
3 「隠れ無宿」という行為
4 世直しを裏切る者
むすびに 拒否と共感
引用史料と参考文献
あとがき
関連年表
索引(人名・事項・文献)

世界大恐慌
講談社選書メチエ
1929年10月24日、暗黒の木曜日。ニューヨーク株式市場は突如大暴落をはじめる。株価は7分の1、銀行倒産6000、失業者1000万。人びとは放浪し、空腹のあまり卒倒する。全世界をのみこんだ70年前の大恐慌を丹念に追い、いま、日本のとるべき経済政策を考察する。

芸術と策謀のパリ ナポレオン三世時代の怪しい男たち
講談社選書メチエ
バブル熱沸き立つ第二帝政下。「貧乏芸術家」を指す〈ボエーム〉があらゆる「ろくでなし」を意味するとき、これこそ時代の寓意(アレゴリー)となる。山師実業家、御用ジャーナリスト、職業陰謀家、そしてその頭領、ナポレオン三世。怪しげな群像から浮かび上がる、無節操時代の精神。
【目次】
プロローグ
第一章 [画家のアトリエ]の秘密
第二章 ボヘミアン芸術家
第三章 無節操の帝国 ボエームという精神風土
第四章 産業ボエーム 山師・詐欺師・実業家
第五章 ボエーム体制からブルジョワ体制へ
エピローグ
ブックガイド
あとがき
索引

富国強馬 ウマからみた近代日本
講談社選書メチエ
より速く、より強く、より逞しく! ウマの改良は、新興日本が総力を挙げた国家的大事業だった。欧米列強に負けぬ軍馬をつくるべく、筆舌につくしがたい努力を重ねた人びと。種馬の輸入から今日の競馬の繁栄に至る、人馬一体、100年の夢の軌跡。
【目次】
はじめに 競馬ブームの裏に
第一章 維新以前
1 世界の戦争と馬匹改良
2 江戸時代の馬
3 外国種の輸入
第二章 帝国陸軍の誕生と馬
1 軍馬補充の苦闘
2 明治天皇の存在
3 日清戦争と馬匹調査会
4 北清事変の衝撃的な教訓
第三章 日露戦争と第一次世界大戦
1 日露戦争と本邦馬匹
2 輜重兵の悲哀
3 馬政計画の策定
4 第一次世界大戦における軍馬
第四章 優駿の夢
1 高さから幅へ
2 さらなる十二年
3 欧米に伍して
第五章 日本競馬事始
1 馬券黙許時代
2 禁止に抗して
3 競馬法の制定
4 日本ダービーの誕生 小岩井vs.下総
5 統制強化期の競馬
第六章 戦時体制下の馬
1 日中戦争と軍馬
2 国防馬政へ
3 イデオロギーとしての馬
第七章 馬への愛は生きつづける
1 安田記念と有馬記念
2 陸軍少将・遊佐幸平の「戦後」
3 夢の途中
あとがき
参考文献
写真図版出典一覧
巻末史料
近代の馬に関する諸統計・本文関連血統表
馬に関する用語

中国人郵便配達問題=コンピュータサイエンス最大の難関
講談社選書メチエ
身の回りに潜む、コンピュータもお手上げの超難問の数々。なぜ、中国人郵便配達問題など「NP完全問題」を解くのに、何千年という計算時間が必要なのか? なぜ、言語理解など、簡単なことがうまくできないのか?「ニューロイダルネット」「量子コンピュータ」が切り開くコンピュータの新地平。より柔軟で、より速い「夢のマシン」の実現にむけ、格闘を続ける計算機科学の最前線。
【目次】
プロローグ 中国人郵便配達問題への挑戦
第一章 計算とは何か?
1 理論計算機科学とは
2 計算の定義
3 コンピュータ開発の歴史
第二章 計算時間の爆発
1 計算時間の測り方
2 R=NP?問題
3 アルゴリズム論におけるブレークスルー
第三章 学習するコンピュータ
1 脳は学習する回路である
2 知能の複雑さ
3 学習するコンピュータの実現に向けて
第四章 量子コンピュータ
1 未来のコンピュータ
2 量子コンピュータのモデル
3 量子コンピュータの実現に向けて
第五章 計算機科学の未来
1 理論計算機科学の発想
2 情報科学技術立国に向けて
エピローグ 計算量理論とコンピュータの未来
ブックガイド
あとがき
索引

宝塚
講談社選書メチエ
まばゆい光、絢爛たるレビュー、視覚にもたらされる快楽。20世紀初頭、博覧会の残照=〈まなざし〉が生んだ「宝塚」は、社会の感性を先取りする。モダニズム、ノスタルジア、ジェンダー──感性の変容から読む〈宝塚〉というシステム。

「撃ちてし止まむ」 太平洋戦争と広告の技術者たち
講談社選書メチエ
「戦意昂揚」「銃後の節倹」「増産体制確立」……。戦時体制下、国策プロパガンダを担ったプロダクションが存在した。報道技術研究会――広告界の錚々たるメンバーが集い、革新的な技術とシステムを生み出した。この仕事師集団の全貌を解明し、戦前から戦後を貫く広告技術の潮流を探る。
【目次】
はじめに
第一章 広告の1920~30年代
1 デザイナーたちの系譜
2 コピーライターたちの系譜
3 プロパガンダの系譜
第二章 「報道」と報研の胎動
1 時局と広告
2 広告から「報道」へ
3 報研誕生への軌跡
第三章 太平洋報道展をめぐって
1 プロパガンダと展覧会
2 太平洋報道展の成功
3 太平洋報道展移行
第四章 太平洋戦争下の報研
1 プロパガンダ制作者集団の簇生
2 「報道」のニューメディア
3 敗戦までの日々
第五章 「報道」の戦後
1 広告への復員
2 戦後の広告界と報研人脈
3 戦前と戦後を貫くもの
おわりに
注
参考・引用文献
あとがき
索引

最澄と空海
講談社選書メチエ
804年、遣唐使船で、ともに超大国唐を目指した二学僧。運命は2人を、協力者からライバルへと変える。天台の「正統」理論を学び、日本仏教千年の礎を築いた最澄。勃興する「新思想」密教を学び、独創的な世界構造論を樹立した空海。二巨人が思索を重ねた「一念三千の哲学」「マンダラ理論」等を読み解き、「日本仏教」誕生の瞬間に迫る。

<ものづくり>と複雑系 アポロ13号はなぜ帰還できたか
講談社選書メチエ
「知ること」と「すること」を架橋する知とは?
理論を超える複雑な現実に対処する工学の知を探り、全知全能ではない人間が世界を作り変える「現場の思想」に迫る。
宇宙空間から奇跡の生還を遂げたアポロ13号。それを支えたものはなにか?事故をも想定した設計、地上での丹念なシミュレーション、巨大システムの掌握術……。複雑すぎる現実に対処する工学に潜むしなやかな知を探り、人間が世界を作り変えるための「限定合理性の思想」に迫る。
【目次】
はじめに 成功に満ちた失敗=アポロ13号
第1章 複雑系から工学へ
1 複雑系とはな何か
2 複雑系と工学の位置づけ
第2章 限定された合理性
1 限定された合理性への移行
2 人工知能の場合
第3章 工学の自己理解
1 工学者の論点
2 エンジニアリング・サイエンスの成立
第4章 実験の意味
1 実験の位置づけ
2 工学的実験
第5章 設計の概念
1 設計の全体像
2 設計の考え方
第6章 安全性という思想
1 安全性に関する事例
2 安全性のキーワード
第7章 工学の合理性
1 限定された合理性の射程
2 思想が工学から学ぶこと
注および参考文献
あとがき
索引

頼朝の精神史
講談社選書メチエ
古代から中世への扉を開いた男、源頼朝。冷徹酷薄な政治家。人情あつき信仰家。2つの像に引き裂かれた「心の闇」は深い。本書は、その分身ともいうべき梶原景時や側近集団の役割に注目しつつ、一介の流人から、徒手空拳で鎌倉殿へと駆け登った、稀代の政治的人間の真実に迫る。
【目次】
はじめに 頼朝の死
第一章 平治の敗戦と配流
1 捕縛
2 池禅尼の助命
3 頼盛一党との関係
4 報恩
第二章 旗挙げ
1 以仁王の呼びかけ
2 挙兵
3 源三位頼政の謀略
4 相少納言宗綱
第三章 神話復活の時代
1 石橋山
2 地方豪族の神話
3 三種の神器
第四章 政権掌握への途
1 流人という経験
2 一門への態度
3 兄弟たち
4 公平の原則
5 情報管理
第五章 梶原景時と頼朝の雑色
1 陰湿なイメージ
2 武者の狡智
3 景時の事跡
4 走狗としての雑色
第六章 頼朝の死と景時
1 族滅の悲劇
2 景時の出自
3 正史の蔭に
第七章 鎮魂の宮――鶴岡八幡宮
1 篤い信仰心
2 ”若宮”の謎
3 大庭・梶原一族の影
4 御霊信仰と鶴岡
あとがき
註
参照・参考文献
索引

骨から見た日本人
講談社選書メチエ
骨は情報の宝庫である。「平和の民」縄文人に残る戦闘の証。古墳時代の結核大流行。娼婦の8割を襲った江戸の梅毒。骨に刻まれた病気を読みとき、日本の社会構造を明らかにする。

法然対明恵
講談社選書メチエ
救いとは何か。濁世を生きる二人が問う。他力か自力か、易行か難行か。鎌倉時代の新旧仏教界を代表する思想家の対決を通して、人はいかにすれば救われるのかという、宗教における究極のテーマに迫る。
人はいかにすれば救われるか。法然と明恵――鎌倉新旧仏教を代表する両者の思想対決は、私たちを根源的な問いへと誘う。現実か理想か。他力か自力か。そして、生と死の究極の姿とは。最新の宗教学の成果を踏まえ、2人の対決の彼方に宗教のアクチュアルな「力」の再生の可能性を探る、宗教のポストモダン。
【目次】
プロローグ なぜ「法然対明恵」なのか
第一章 浮かび上がる二つの軌跡
1 相似形の生い立ち
2 乖離していく2人の軌跡
3 両極に立った改革思想
第二章 明恵――「生の座標軸」
1 実践哲学としての華厳思想
2 ひたすらに愛する人
3 世界はありのままで美しい
4 末法思想の超克
第三章 法然――「死の座標軸」
1 絶望の時代に投げこまれて
2 救いの発見
3 濁世の革命家
第四章 交錯する座標軸
1 対決の構図
2 身体化する思想
3 重なり合う座標軸
4 日本仏教の再生へ
註
あとがき
索引

「出世」のメカニズム 「ジフ構造」で読む競争社会
講談社選書メチエ
「出る杭」は打たれる。「出ない杭」は腐る。しかし、「出すぎた杭」は打たれない。実績と潜在能力のあいだに潜む不思議なメカニズム。評価が評価を生む〈ジフ構造〉に作用する「正のフィードバック」を探り、生存競争モデルでは見えない、競争のもうひとつの現実を浮き彫りにする。
【目次】
はじめに 負けるも勝ちを作り込む
第一章 社会原理としての競争――能力とは何か
1 生存競争と社会における競争
2 企業内競争の変遷
第二章 能力主義競争――能力測定はどう可能なのか
1 試験と昇進における能力
2 能力の分布
第三章 ジフ分布とジフ構造――正のフィードバック効果
1 ジフ分布とは何か
2 ジフ分布からジフ構造へ
第四章 出る杭は打たれる――同調圧力と特異性信用の関係
1 集団内のジフ構造
2 メンバーの能力分布
第五章 出すぎた杭は打たれない――トップと不良社員の使い方
1 能力増幅過程
2 裏のジフ構造
第六章 出ない杭は腐る――サブノーマルと平均的メンバー
1 平均的な「良い子」
2 サブノーマルの存在
第七章 ジフ構造のダイナミクス――競争の戦略
1 学校歴の構造
2 ジフ構造下での競争戦術
第八章 競争の設計――組織活性化の方法
1 二つの競争タイプ
2 集団の活性化
あとがき
索引
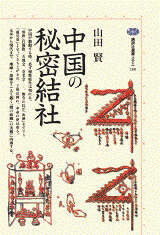
中国の秘密結社
講談社選書メチエ
中国が激動する時、必ず秘密結社は現れる。「邪教」白蓮教、天地会、哥老会……。無告の民が「血酒」をすすり、「義兄弟」となって立ち上がる日、王朝は倒れ、革命の夢は成る。元末から現代まで、地縁・血縁をこえて蠢(うごめ)く「謎の組織」の実態に肉薄する。
【目次】
はじめに
第一章 世界の終わりと虚構の「家」
1 紅巾の乱
2 「母」の幻想
3 メシアへの憧憬
4 「邪教」の社会的機能
第二章 洪門の幻
1 『品革命党及秘密結社』
2 符号と隠語
3 「起源」のヴェール
第三章 「反清復明」の神話
1 「辺境」の秩序
2 李姓と朱姓
3 結社の実像
4 人口増の行方
第四章 革命前夜
1 清末という時代
2 はじめの一撃
3 三つの舞台
第五章 「民国」の思想
1 龍華会章程
2 〈全体〉との一体化
3 日中のズレ
第六章 秘密結社としての中国共産党
1 任侠道的共産主義
2 紅い「大爺」たち
3 基層社会における中国革命
おわりに
補論 白蓮教系宗教結社の思惟構造
1 奇妙な呪文
2 白き異装の謎
3 天上回帰の夢
参考文献
あとがき
写真図版一覧
事項・書名索引
人名索引

現代思想としての西田幾多郎
講談社選書メチエ
〈近代の知〉最大のアポリア、「二元論」。その難関を西田は、判断以前、主観――客観以前、「色を見、音を聞く刹那」を摘出することで、ラディカルに乗り越える。「善の研究」が創出し、生涯のキータームとなった「純粋経験」を中心に、西洋哲学の〈脱構築〉を目指した、西田「ポストモダン」哲学の全貌に迫る。
【目次】
プロローグ
序章 西田幾多郎の世界へ その生涯を追って
第一章 純粋経験とは何か
1 『善の研究』の誕生
2 なぜ純粋経験なのか
3 純粋経験の理解のために
第二章 二元論批判としての純粋経験論
1 主客二元論のアポリア
2 知情合一の経験
3 流動性の論理
第三章 経験とことば
1 経験とことばの間
2 日本語と哲学
3 経験を考えなおす
第四章 〈もの〉と〈こと〉
1 共生する〈もの〉と〈こと〉
2 〈こと〉と日本語
3 〈こと〉を表現することば
第五章 西田の芸術論
1 純粋経験としての芸術的直観
2 芸術観の深まり
第六章 自己への問い
1 真の自己
2 自己への問いとしての宗教
終章 その後の西田へ
エピローグ
注
あとがき
索引
●その後の西田へ