講談社学術文庫作品一覧

スミス・ヘ-ゲル・マルクス
講談社学術文庫
近代市民社会を考察して、アダム・スミスは土台である経済が「見えざる手」に支配されると考えた。後にヘーゲルは経済の自律的体系は不可能で、市民社会は国家に包摂されることで存立し得ると批判し、マルクスは経済の中の宥和なき矛盾のため市民社会は社会主義に移行すると説いた。本書は、西欧三大思想家が主張した自由主義、国家主義、社会主義の生い立ちと体系を独自の視点から考察した名著である。

新しき短歌の規定
講談社学術文庫
新しい歌とは何か、なぜ歌を作るのか。本書は、まさに戦後の歴史的局面のさまざまな変貌と混乱を振り払うように、沈滞し腐敗しかかった戦後短歌に指針と光明をあたえ歌論集として、多くの短歌実作者の記憶に長くとどめられてきた。実作者は己を賭けた生の追究をせよと説く34篇の歌論には、いずれも著者の意気込みと責任の強さがみなぎっている。時流を超えて新たな光芒を放つ現代短歌の原典。

レトリックの記号論
講談社学術文庫
われわれを取り囲む文化とは、巨大な記号の体系に他ならない。言語においても単語はそれぞれの意味をそなえた記号であり、それらが集まってできる文は複合的な記号となる。想像力ないし創造力を駆使して微妙な言語現象を分析・解読するレトリックの認識こそ、記号論のもっとも重要な主題なのである。言語学を越えた〈記号論としてのレトリック〉の領野を呈示した著者のレトリック研究の集大成の書。

近世日本国民史 維新への胎動(上)寺田屋事件
講談社学術文庫
文久元年五月、長藩長井雅楽は航海遠略を公武合体の楔子とすべき旨趣の口上書を朝廷に提出、朝幕間を周旋するも同二年正月十五日、坂下門外に於て閣老安藤対馬守が水戸浪士らに要撃される事件出来で頓挫。天下の大勢は長井流の公武合体策の実現すべからざるを見、薩藩島津久光は大兵を率いて上洛、朝主幕従公武合体を主唱、同年四月二十三日、尊攘派有馬新七ら薩藩士同士の乱闘、寺田屋事件起る。

現代の社会科学者 現代社会科学における実証主義と理念主義
講談社学術文庫
18世紀から現代にかけて、社会科学は実証主義と理念主義の2大潮流を形成した。前者はコント、ミルに始まり、ワルラスの均衡理論はミクロ経済学の礎となり、パーソンズの機能理論は社会学発展に寄与した。一方、ヘーゲルに発する理念主義はディルタイの歴史主義、フッサールの現象学、そしてマルクス主義を生んだ。本書はこの社会科学の大河に分け入り、源流から現代に至るまでを克明に論述する。

茂吉秀歌『あらたま』百首
講談社学術文庫
痍となっても彼はしたたかに歌ひやまず、また歌ひおほせた。『あらたま』は作者の旺盛な創作慾とストイックな写生探究が周期的に交替しつつ、つひに一途に堅実平明な境地に行きつかうとするところで巻末を迎へる興味津津の歌集である。私は『赤光』以上に殊更に辛辣な舌鋒を弄した。それがこの作家への畏敬の念の私流の発露である。(著者・跋より)

ユートピアの幻想
講談社学術文庫
ギリシア語で〈どこにもない理想郷〉を意味するトマス・モアの造語〈ユートピア〉。プラトンの「国家(ポリティア)」に始まるその古典的淵源から説き起こし、19世紀の社会主義的ユートピア志向を経て、現代のSF化された未来論に至るユートピア思想の変遷を辿る。さまざまな楽園伝説や終末論、諷刺、幻想文学などの隣接領域と対比しながら、比較文化学の視点からユートピア像の多面的な姿を考察した画期的力作。

近世日本の科学思想
講談社学術文庫
江戸時代の天文暦学・医学・和算学を通観し、わが国の科学思想の特質が空間的法則よりも時間的変化を重視するものであることを著者は具体的に説く。すなわち幕府天文方・渋川春海は西洋流の永久的天体法則は幻想であり、万物は流転すると観じたし、『解体新書』以前の医者は解剖による局所の分析を排して動態的・全体的な治療を旨とした。功利主義に傾きがちな日本人の科学観に歴史的反省を促す好著。

群衆心理
講談社学術文庫
民主主義が進展し、「群衆」が歴史をうごかす時代となった19世紀末、フランスの社会心理学者ギュスターヴ・ル・ボンは、心理学の視点に立って群衆の心理を解明しようと試みた。
フランス革命やナポレオンの出現などの史実に基づいて「群衆心理」の特徴とその功罪を鋭く分析し、付和雷同など未熟な精神に伴う群集の非合理的な行動に警告を発るに至ったのである。
社会心理学の研究発展への道を開いた古典的名著にして、「ポピュリズム」を考えるための必読書!

アウグスチヌス『告白』講義
講談社学術文庫
ローマ帝国崩壊期に、教父アウグスチヌスが著した『告白』は、結婚と世俗的栄達の道を捨ててキリストの教えに帰依し、光明を見出すまでの激しい内面の葛藤、母と子の物語を赤裸々に描いて名高い。本書は、その告白文学の最高傑作を、内村鑑三に師事し、軍国主義批判のため東大を追われた筆者が、自宅に開いた私塾で講義し、まとめたものである。1600年前の魂の叫びが、今いきいきとよみがえる名著。

日本文学史
講談社学術文庫
文藝作品の内なる表現理念=「雅・俗」の交錯によって時代を区分したところに本書の不滅の独創がある。健康で溌溂とした「俗」を本性とする古代文藝、端正・繊細な「雅」を重んずる中世、また古代とは別種の新奇な「俗」を本質とする近代。加えて著者は、日本文学を「世界」の場に引き出し、比較文学の視点からも全体的理解に努める。長く盛名のみ高く入手困難だった「幻の名著」の待望の復刊。(解説=ドナルド・キーン)

アルチュセ-ルの思想
講談社学術文庫
唯物論的発展段階説、人間疎外論、社会主義革命論──マルクス主義は硬直した言説(イデオロギー)に覆い尽されている。それら矮小なレッテルを退け、アルチュセールは、マルクスの思想をその可能性の中心において読み解く。歴史と社会に関する科学的認識の理論として。空前の哲学革命・科学革命の理論としてのマルクス主義を未来へ向けて再生し、構造主義=ポスト構造主義への地平を拓いた現代思想の巨人の全体像を描く。

経済学の実際知識
講談社学術文庫
バブル崩壊後の大正末期の日本経済を分析し、「銀行と信用」の章では、中央銀行がその目的を完遂するには政府の干渉から独立した執行機関が必要と指摘した。さらに、資本家の貯蓄にかわって政府が財政収入を公共事業に投資し、富の管理者になったとする「富の保存および増殖」など、秀れた先見性と今も通用する経済の原則を展開する。在野の経済学者・高橋亀吉の処女作にして洛陽の紙価を高めた名著。
日本の神秘思想
講談社学術文庫
インドに発した神秘思想の日本的な展開とは現実と実在の一如を考える密教的世界観は長い時間をかけて東アジア一帯に根づいた。日本および日本人という条件が仏教的神秘思想にいかに働いたかを考察する好著

シルクロ-ド
講談社学術文庫
荒涼たる砂漠の西域を貫き、東西文化の架け橋であったシルクロード。本書は、この国際交易路研究の第一人者が、最新の成果をもとに西域における国家と民族の歴史の興亡をたどり、また、法顕や玄奘、マルコ・ポーロらの中央アジア紀行の足跡を振り返る。さらに、絹や青銅やガラスなど、東西の文物交流の軌跡を明らかにする。シルクロードをめぐる東西交渉史学の決定版。必読の文庫オリジナル!
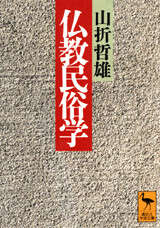
仏教民俗学
講談社学術文庫
民衆に育まれてきた日本仏教の真の姿をとらえるためには、従来の仏教学はあまりにも民俗学による発見を無視して自己を主張し、民俗学もまた仏教学の蓄積を白眼視してひとり歩きをしているのではないか、と著者は危惧する。仏教に根ざした日本人の生活習慣や年中行事や民間信仰などを考察し、また外国人の信仰行動などとの比較検討を重ねて、仏教学と民俗学との緊密な関係の確立が今こと急務と説く。

江戸ことば・東京ことば辞典
講談社学術文庫
あかぬけ・ごますり・しみったれ・とんちき・はすっぱ・はったり・へっぽこ・やぼてん……。人々の口から口へ伝えられたイキでイナセな庶民のことばの数々。現代人の毎日の暮らしの中でいまも使われているクチコミ語822の語源・意味・用例を明快に解説する。江戸から東京へ。国語学界の第一人者が多年にわたる近代日本語の変遷の研究のなかからまとめた「江戸ことば・東京ことば」おもしろ小辞典。

ルネサンス
講談社学術文庫
中世の野蛮と暗黒の束縛から人間精神が新しく解放され、近代文化の基盤を開いたといわれるルネサンス。本署では、これまで異口同音に語られてきた単調で理想化されすぎるルネサンス像を退け、もっと人間くさい歴史像を「現代」というフィルターを通して考察、その華やかな時代の光の部分のみならず陰の部分にも焦点をあてて、総合的にルネサンスを捉えた。最新の知見に基づく待望のルネサンス論。

明治大正史 世相篇 新装版
講談社学術文庫
毎日われわれの眼前に出ては消える事実のみによって、立派に歴史は書けるものだという著者が、明治大正の日本人の暮し方、生き方を、民俗学的方法によって描き出した画期的な世相史。著者は故意に固有名詞を掲げることを避け、国に遍満する常人という人々が眼を開き耳を傾ければ視聴しうるもののかぎり、そうしてただ少しく心を潜めるならば、必ず思い至るであろうところの意見だけを述べたという。

言葉と悲劇
講談社学術文庫
『マクベス』やギリシア悲劇を例に、「悲劇は言葉の両義性にかかわる」と指摘した「言葉と悲劇」、小説『こころ』を分析し、夏目漱石の深層心理に迫った「漱石の多様性」など、柄谷行人の代表的講演を収録。文学、思想から経済学、数学にも言及する15編は、作者の知的世界の広大さを示す。『探究1・2』執筆と並行する思想の軌跡は、現代人にとって刺激にあふれた〈柄谷理論〉への格好の入門書である。