講談社選書メチエ作品一覧

イタリア的 「南」の魅力
講談社選書メチエ
時代はイタリア
イタリア人が日本語で書いた最新イタリア案内
明るく暗く、貧しく豊か、悲観的な楽観主義者。矛盾するものが矛盾なく同居する不思議な国。「不信の文化」「カーニバルとユートピア」「南型の思想」をキーワードに、日本人の知らないイタリア人の素顔を、食・宗教・音楽・政治に探る。イタリア人が日本語で書いたイタリア案内!
【目次】
序章 「mangiare(食べる)、cantare(歌う)、amore(恋愛)」ってなに? イタリア人は「陽気」で「気楽」か
第一章 食にみるイタリア それは貧しさから始まった
第二章 イタリア人の宗教観 「常識」としてのカトリック
第三章 歌うイタリア 「イタリアン・ポップス」の深く多彩な世界
第四章 イタリア政治の不思議な世界 カーニバルとユートピアのあいだ
第五章 イタリア的悲観主義 明るさは暗く、暗さは明るい
終章 イタリアから何が学べるか 新しい人間観へ
註
参考文献
あとがき

「株式会社」長崎出島
講談社選書メチエ
お奉行様から花魁まで、みんなこの街の「社員」だった
街全体が丸ごと「会社」だった不思議な都市。対外貿易のためだけに創られ、事業所長=奉行からプロフェッショナルな地役人、テクノクラート・オランダ通詞、そして長屋住まいの日雇い稼業の労働者から丸山の花魁にいたる全住民が組織化され、街をあげて貿易会社の社員のように働いていた。日本の出島=江戸時代の長崎を活写する。
【目次】
序章 「組織」としての都市
第一章 貿易と繁栄
1 貿易都市の黎明
2 キリシタン都市長崎
3 長崎をつくった人々
4 都市長崎の成長
第二章 「株式会社長崎」の誕生 出島・唐人屋敷・長崎会所
1 オランダ東インド会社
2 出島とオランダ人
3 長崎の唐人たち
4 システムとしての長崎貿易
第三章 長崎のお役人たち
1 代官一〇〇〇両奉行三〇〇〇両
2 プロフェッショナルな地役人
3 日雇い稼業
第四章 貿易都市・歓楽都市
1 歓楽都市「長崎」
2 遊女=歓楽都市の主役
第五章 都市と組織の間で
1 武士と町人の矛盾 「長崎喧嘩」の深相
2 フェートン号の衝撃
3 米不足の脅威
終章 ボーダーを越えて
1 「会社都市」の終焉
2 「異域」という生き方 新たな「出島」への可能性
参考文献
あとがき
年表
索引

ブッダ論理学五つの難問
講談社選書メチエ
論理と倫理が1つになる場所へ!
イラク戦争がなぜダメか、ブッダの答えは? ブッダはほんとうに「一切を知る者」なのか? 仏教経典に完全保存された「論理学」はそれをあざやかに証明する。合理的であることは真理であること。存在論からイラク戦争まで、現代論理学が沈黙する「難問」に、ブッダが残した明快な「答え」。論理と倫理が1つになる場所へ!
【著者からのコメント】
インドの文献は、けっして読者に媚びることはない。だから、やさしくもないしわかりやすくもない。でも、本当のことを知りたいと思う人には、求めるものが自然に心に入ってくるように、そんな風に書かれている。
わたしもそんな本を書いてみたいと思って、力いっぱいやってみましたが…うまくいったでしょうか。
【目次】
まえがき
序論 論理の語り方
第一章 現代論理学は一切を語れるわけではない……一切を知る者であるとブッダが言ったこと
第二章 ブッダ難問に答える
【難問1】なぜ西洋論理学では因果を語ることができないか……生ずる性質のものは滅する性質のものである
【難問2】ブッダはどのようにして一切を語るのか……討論を通じてともに語るにふさわしい人は
【難問3】語りえぬものには沈黙せねばならないか……ただ感受されたもの、渇愛にいたるもの、悩みもだえるだけのものである
【難問4】因果の道を行くものはなぜ愚か者であってはならないのか……自己を愛しく求めるものは他を害してはならない
【難問5】因果の理法によって生きる者には自己は語りえないか……「尊師よ、誰が識別作用という食べ物を食べるのですか」「正しい問いではない」と尊師は言った
インド哲学・仏教の一般書ならびに現代論理学関係書のご紹介
練習問題の解答
あとがき
注
索引

レヴィナス 無起源からの思考
講談社選書メチエ
倫理=政治=哲学論考 人間の起源についての真実
存在を・欲望を・責任を・正義を・国家を考え抜いたレヴィナス。「他者」の「顔」が私に到来するとき哲学が始まるとは、どういうことなのか?「砂嵐のような文体」で語られた真理に迫る渾身の書き下ろし。
【目次】
序 章 あなたに
1 倫理=政治=哲学論考
2 「無起源」あるいは「思考しえないもの」
プロフィール──レヴィナスとその時代
第一章 糧と享受
1 端的な存在──空
2 存在に走る亀裂──無
3 要素の中心化──穴
4 糧の享受──体験
第二章 欲望 あるいは愛
1 「顔」の下での覚醒
2 異邦人から異邦人へ
3 絡み合い
4 「欲望」する理性
第三章 言葉
1 接触
2 接触なき関係──「瞬間」
3 過剰な受動性──語り出すこと
4 「汝、殺すなかれ」
第四章 責任 あるいは身代わり
1 赤貧・廉直・近さ──責任
2 他者に傷つく能力──私
3 絶対的差異の下に──単独者
4 「私のために」と「他者のために」
第五章 国家と正義
1 比較不可能なものの比較
2 「欲望しえないもの」にして「望ましからざるもの」──正義
3 等しいものたちの共同体──国家
4 正義と責任──最初の暴力
あとがき

南朝全史
講談社選書メチエ
謎多き南朝。その実像は、政治・文化的実体をともなった本格政権だった。劣勢を余儀なくされながら、吉野山中になぜ長きにわたり存続できたのか。あらゆる史料を博捜し、「もう1つの朝廷」200年の全過程を明らかにする。(講談社選書メチエ)
謎多き「もう一つの宮廷」の実像に肉迫する。つねに劣勢を余儀なくされながら、なぜ南朝は存続できたのか。鎌倉時代の大覚寺統誕生から後南朝消滅まで、二百年に及ぶ南朝の歴史と実体を体系的に明らかにする。

パウロとペテロ
講談社選書メチエ
2人がいなければ今日のキリスト教はなかった! イエスの筆頭弟子にして復活後の教会指導者ペテロ。迫害者から異邦人伝道者へと回心したパウロ。古代ローマ帝国の片隅ではじまった運動を世界宗教にまで伸展させた2人の実像は? そして、彼らのユダヤ人・異邦人への宣教戦略とは? 2大伝道者の足跡を辿る1冊。
【目次】
序章 世界宗教への立役者
第一章 ペテロ イエスの筆頭弟子から最初のキリスト教伝道者へ
1 アンティオキアの出来事
2 召命以前のペテロ
3 弟子への召命の出来事
4 イエスと弟子仲間との生活
5 イエスへの信仰告白=ペテロのメシア告白
6 イエスの受難に直面して=イエスの否認
7 使徒としての宣教準備
8 筆頭使徒としての活動
9 エルサレムにおける教会の指導者として
10 ユダヤ人伝道の担い手として
第二章 パウロ 教会の迫害者からキリストの伝道者へ
1 パウロが生きた時代
2 回心以前のパウロ
3 ダマスクス途上での回心
4 ペテロとの面談
第三章 ユダヤ人の伝道者ペテロの足跡
1 ペテロの伝道活動
2 律法の重要性をめぐって
3 ペテロの伝道の特徴
4 その後のペテロ
第四章 異邦人の伝道者パウロの活動
1 伝道者としての足跡と伝道戦略
2 アンティオキア教会の新しさ
3 使徒会議
4 第一次伝道旅行 キプロスとガラテヤで
5 ガラテヤの信徒に宛てた手紙
6 再び伝道の旅へ
7 三度目の伝道の旅 小アジアのエフェソを本拠に
8 パウロの最後
終章 伝道者ペテロとパウロ
文献案内
註
あとがき

倭国神話の謎 天津神・国津神の来歴
講談社選書メチエ
復元される神々の物語!4世紀神話の原像とは?
4世紀に成立した皇室の王権が改変した「それまでの倭国の歴史」。その痕跡は、今も膨大な神話群として残されている。別説・異説として顧みられなかったそれら神話を「すべて」読み尽くすことにより、神々の系譜を解明。戦後神話研究に新局面が拓かれる。
【目次】
まえがき
第一章 〈皇室版日本神話〉の想定
1 記紀神話に先だつ古い神話
2 皇室天皇氏の歩み
第二章 天地開闢の神話物語(一~三段)
1 最初でなかった最初の神々
2 何を語る、男女五組十神
第三章 イザナキ・イザナミの物語(四・五段)
1 〈大八洲国生み〉とは何か
2 「生まれ損ね」の兄、淡路洲
3 棄てられたヒルコの正体
4 皇祖神弟にスカウトされた出雲須佐の男
5 ヨモツ国からの逃走
第四章 スサノオと天照大神の物語(六~八段)
1 天照大神は女か男か
2 スサノオと天照が交合しないわけ
3 スサノオ、天照を追い詰める
4 スサノオの処罰と呪物体〈卜〉
5 ヤマタノオロチの謎解き
6 新羅・紀伊・熊野への注目
第五章 神代紀にないQ段神話物語
1 目立つ天武天皇の加工
2 アヅミ系沼河姫神族と出雲族
3 大ナムチ・少ナヒコナの意味すること
第六章 天孫の天降りとその後の物語(九~一一段)
1 高天原の司令神の変遷
2 真床覆衾・随伴神・三種の神器の真相
3 浮かび上がる海人族の神話伝承
注
あとがき
索引

知の教科書 フロイト=ラカン
講談社選書メチエ
創造したフロイト、再創造したラカン
人間を考える一筋の思想系がわかる
フロイトの独創的な発見は、ラカンによってすべて掬い取られ、深く大きく展開された。「無意識」は「他者の語らい」として、「エディプスコンプレクス」は「シニフィアンの導入」として。人間の「現実」を追究した思想の系としてのフロイト=ラカンが本当にわかる1冊。
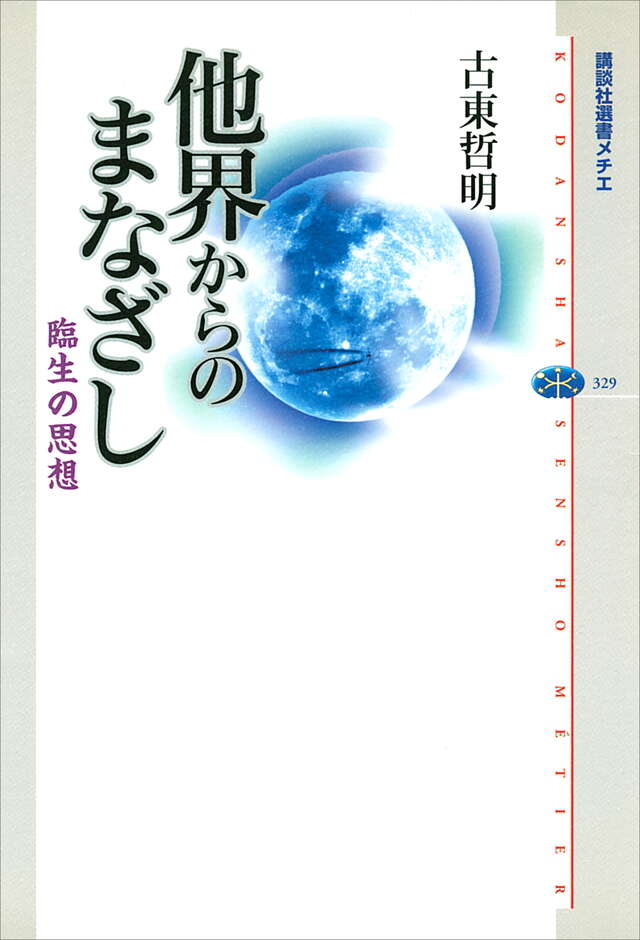
他界からのまなざし
講談社選書メチエ
生のリアルに迫るダイナミックな思考の旅!
僕らが日々漫然と消費しているこの「生」は、「向こう側」からみつめ直すことで輝き出す!生のまぎわに臨む「臨生」のたたずまいを得ることで、人生のリアルさを取り戻すことができるのだ。古今東西の他界観・芸術空間論・共同体論をふまえた渾身の哲学論考が登場!
【目次】
プロローグ 日常という奇蹟
第一章 他界の近さ──日本人の他界観
1 ダブルな世界
2 死にあらがう生
3 もうひとつの現実
4 ネクロマンシー(死界との交感)
第二章 反転する浄土──世阿彌能の秘密
1 闇の劇場
2 転位するシナリオ
3 よみがえる此岸
第三章 プレシオスの鎖──宮澤賢治の生きた場所
1 蒼白い星の群れ
2 垂直の投身
3 にんげんの壊れる時
4 『銀河鉄道の夜』の謎
5 ほんとうのしあわせ──謎の解明
第四章 空白の共同体──コミューンの現象学
1 共同体はすでにある
2 主体のパラドックス
3 〈間〉の幾何学
4 死のイニシエーション
第五章 遊体論──プラトンの変身術
1 遊園地奪還
2 身体さがし
3 身の現象学
4 遊体化の密儀
5 臨生のイデア
エピローグ バスに乗るのはもうやめよう
注
索引

<育てる経営>の戦略 ポスト成果主義への道
講談社選書メチエ
『虚妄の成果主義』の著者による新・経営論一元的な点数化。客観評価に対する違和感――。成果主義が破壊した人材育成機能。いま企業はどのようなシステムを再構築すべきか。人材育成の思想と知恵を解く。
「客観評価」「評価のフィードバック」を掲げ、給料格差と勤労意欲の連動を信じた成果主義はいちばん大切な人材育成機能を破壊した。いま、企業はどのようなシステムを再構築すべきなのか。「やり過ごし」「尻ぬぐい」など先達の知恵と経営戦略論が明かす<育てる経営>の思想。虚妄の成果主義』の著者によるこれからの経営論!
【目次】
第1章 客観評価の虚妄
第2章 貧困な発想
第3章 『虚妄の成果主義』が批判したもの
第4章 目的はモチベーション
第5章 人的資源は買えない
第6章 競争優位の源泉としての資源・能力蓄積過程
第7章 例解:発明の対価
第8章 育てる経営

日本を意識する
講談社選書メチエ
新視点
外から、内から――――ジャパン・コンシャスとは
東京大学比較日本文化論テーマ講義
●異文化体験で私は何を発見したか――日本研究の視点から 義江彰夫
●立ち現れた「日本語」のすがた 鈴木広光
●日本女性の不可解性と理想化――『お菊さん』と『蝶々夫人』 大澤吉博
●脱和入欧の心理――ロチと日本の作家たち 菅原克也
●周作人の日本――「生活の芸術」と倫理的主体 伊藤徳也
●どのようにしてこの国の名が「日本」となったか 神野志隆光
●唐土にたたずむ貴公子たち 三角洋一
●「物のあはれ」の日本 杉田昌彦
●時代観察の方法――杉田玄白と海保青陵 徳盛 誠
●明治零年代の「繁昌」 ロバート キャンベル
●旅人の自画像 齋藤希史
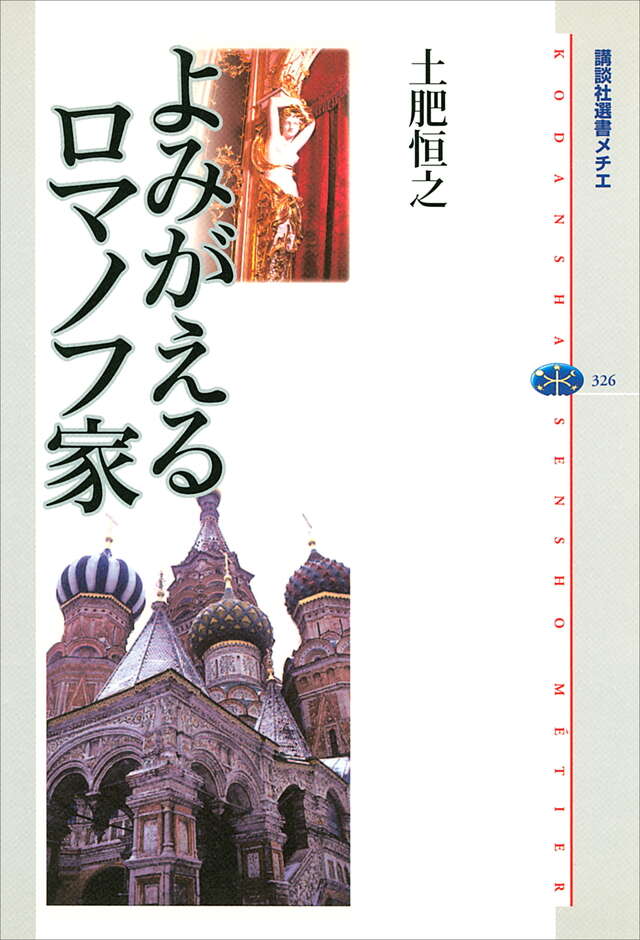
よみがえるロマノフ家
講談社選書メチエ
ピョートル大帝、アレクサンドル1世、エカテリーナ2世、ニコライ2世etc. 1613年ミハイル選出から1917年ニコライ退位に到るまで19人を数える君主の家系はいかに継がれていったのか。西欧派・ピョートル大帝やパリに入城したアレクサンドル、女帝の世紀の啓蒙君主・エカテリーナなどの事績を追い、強い君主を希求するロシアの民衆とツァーリ一族の300年を描く。(講談社選書メチエ)
強いツァーリ悲劇のツァーリとロシアの300年
ピョートル大帝、アレクサンドル1世、エカテリーナ2世、ニコライ2世etc.
1613年ミハイル選出から1917年ニコライ退位に到るまで19人を数える君主の家系はいかに継がれていったのか。西欧派・ピョートル大帝やパリに入城したアレクサンドル、女帝の世紀の啓蒙君主・エカテリーナなどの事績を追い、強い君主を希求するロシアの民衆とツァーリ一族の300年を描く。
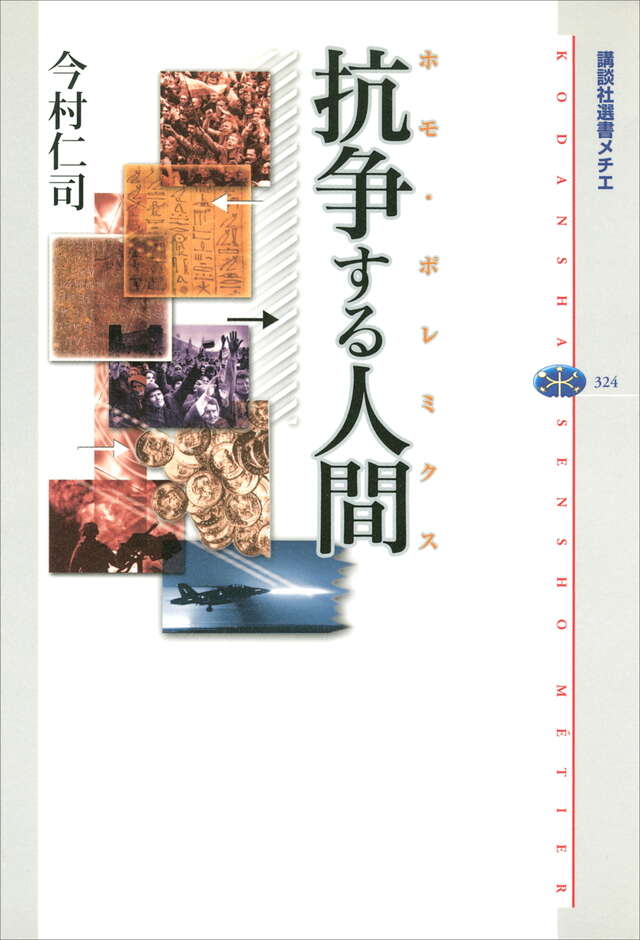
抗争する人間(ホモ・ポレミクス)
講談社選書メチエ
今村社会哲学の到達点!
暴力・闘争・排除を生む人間の本質に迫る
社会的人間が内包する暴力性とは何なのか?排除・闘争を通じて構造化される秩序とは?人間が持っている社会的欲望がどんな暴力現象となって現れどのように制御されるのかを解明し、そうした精神の構造に楔として打ち込まれる倫理の可能性を探る。
【目次】
はじめに
序 章 社会に内在する暴力
1 アルカイック社会における政治と暴力
2 「排除」から生まれる秩序
3 他者に承認を要求すること
4 暴力を生み出す精神と倫理
第一章 欲望としての人間
1 人間の欲望の三つのアスペクト
2 想像上の親殺し
第二章 社会を形成する動力
1 社会的結合(ソシアビリテ)は自然か人工か
2 欲望に貫かれた闘争の力学
第三章 欲望論の系譜
1 上位に立とうとする欲望
2 権力のイデオロギー的正当化
3 産出された現実のなかの真理
4 社会的欲望が正当化される過程
第四章 文字と貨幣と国家
1 排除する力が生む文字と貨幣
2 人間的存在者に内在する文字的なもの
3 国家とは実力(暴力)なのか
4 暴力の人間学的基礎
5 国家はすみずみまで暴力である
第五章 王権の類型
1 「未開社会」の王権
2 絶対王権の正当化論理
3 絶対君主の社会的位置
第六章 言葉と暴力
1 尋問と命令の強制力
2 存在の分割
3 権力の言説
4 言葉の暴力からの解放
5 論議的言説による法理念の実現
第七章 法から倫理へ
1 法の理念
2 覚醒倫理の可能性
参考文献
あとがき

〈学級〉の歴史学
講談社選書メチエ
理想論・タテマエ論への違和感の根源――「学級」という幻想! 我々はどうして席に座って教師の話を聞いていたのか? それは教育の普遍的システムなのか? 〈崩壊〉という事態は何なのか? 近代の発明品〈学級〉の歴史性と限界を暴き、自明視された空間で暮らす子どもと教師を救済する! (講談社選書メチエ)
理想論・タテマエ論への違和感の根源――「学級」という幻想!
我々はどうして席に座って教師の話を聞いていたのか?それは教育の普遍的システムなのか?<崩壊>という事態は何なのか?近代の発明品<学級>の歴史性と限界を暴き、自明視された空間で暮らす子どもと教師を救済する!

瀬戸内の海賊
講談社選書メチエ
<日本最大の海賊>戦国の瀬戸内を駆ける
瀬戸内の小島、能島を根城に勇名を轟かせた村上水軍の大海賊。同族間の苛烈な主導権争い、毛利方水軍としての信長との死闘、秀吉の調略、そして海賊禁止令による終焉。戦国の海を生き抜いた波乱の生涯を活写する。
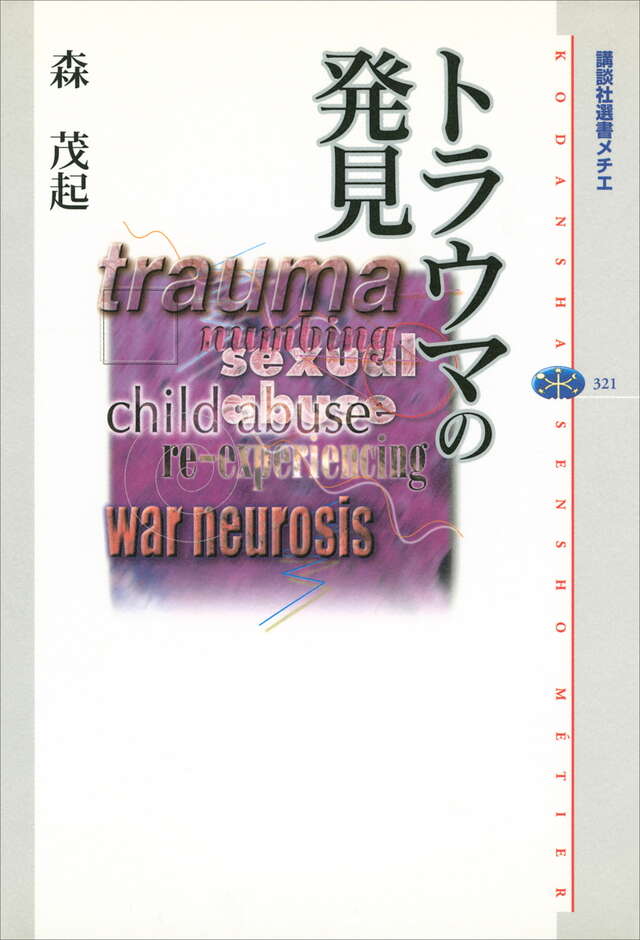
トラウマの発見
講談社選書メチエ
惨事・戦争・虐待と心的外傷
大事故・世界大戦・性暴力。大事件のたびに存在を示唆されたトラウマは、なぜ「発見」が20世紀後半まで遅れたのか?フロイト、フェレンツィらの苦闘からPTSD成立までトラウマ発見の歴史をたどり、同時に、トラウマをつねに否認しようとする社会の「秘められた欲望」を暴く。
【目次】
第一章 惨事、暴力、解離──トラウマとは何か
第二章 惨事トラウマの発見──それは鉄道事故から始まった
第三章 ヒステリーとトラウマ──フロイトの蹉跌
第四章 第一次世界大戦の衝撃──トラウマ研究の高まり
第五章 空白の時代──フェレンツィの実践
第六章 PTSDの成立──第二次世界大戦後のトラウマ研究
第七章 累積したトラウマをいかに浄化するか──現在から未来へ
註
あとがき
索引
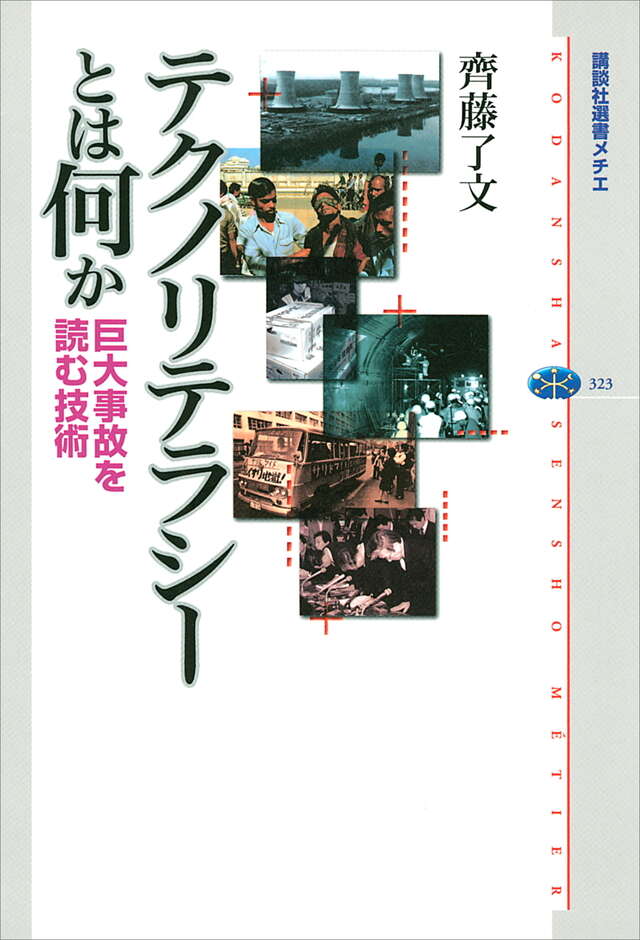
テクノリテラシーとは何か
講談社選書メチエ
技術の失敗、社会の失敗に何を読み取るか。巨大事故から学び取ることは何なのか。原発、飛行機事故から頻発する医療ミス、銀行のシステムトラブルまで。従来の哲学、法制度では解決できない「人工物」をめぐる問題群。失敗の本質を解き明かし、〈ものづくりの知〉の姿を明らかにする1冊。(講談社選書メチエ)
技術の失敗、社会の失敗に何を読み取るか
巨大事故から学び取ることは何なのか。原発、飛行機事故から頻発する医療ミス、銀行のシステムトラブルまで。従来の哲学、法制度では解決できない「人工物」をめぐる問題群。失敗の本質を解き明かし、<ものづくりの知>の姿を明らかにする1冊。

その後の慶喜
講談社選書メチエ
将軍の座を追われた後の長く平凡で充実した人生
大政奉還後、表舞台から姿を消した徳川慶喜。最高権力者の座を追われたあとの45年とは?水戸での謹慎から静岡、東京と居を移したその日常は失意のなかで営まれたのか、平穏な日々だったのか?「歴史上の人物」として静かに生きた男・慶喜の後半生。

夢の分析 生成する〈私〉の根源
講談社選書メチエ
私たちが見る夢は「神託」か「無意味」か? 仕切りのないトイレの夢、海に落ちて沈んでいく夢……。こうした夢が語る内面性と超越性の対立。古代から現代に至る人々の夢を辿りつつ、近代的な主体の誕生を読む。
【目次】
はじめに 夢を分析するということ
第一章 夢をめぐるフロイトとユング
1 反復夢とはなにか
2 精神分析と夢
3 神経症=意識と無意識の妥協形成
4 現実と幻想
5 夢を読む視点 「ごまかす」か「ごまかさない」か
6 予知夢をめぐって 換喩と隠喩
第二章 落ちる夢 超越性をめぐって
1 〈私〉という主体のあり方
2 垂直軸と水平軸
3 シャーマニズムの治療観
4 治癒夢の変遷 夢を「みる」から「つくる」へ
第三章 トイレの夢 内面性をめぐって
1 排泄 〈私〉をめぐる「せめぎあい」
2 「個人空間」としてのトイレ
3 神経症と祝祭
4 フィロバティズムとオクノフィル
5 内面性 川沿いの家の夢
6 「意味するもの」と「意味されるもの」
7 自意識としてのトイレの壁
8 対立するもののダンス
おわりに 言霊論と記号論
注

日本人の起源
講談社選書メチエ
日本列島の旧石器時代はどこまでさかのぼれるか。縄文人から弥生人への移行の真相は。遠くアフリカ大陸に誕生した人類は、どのような道のりをたどり日本列島にたどり着いたのか――。最新の知見をもとに、「日本人の起源」へのさまざまな疑問を解き明かす。(講談社選書メチエ)
ここまでわかった! 日本人のルーツに迫る。「日本人」はどこから来たか。旧石器時代はどこまでさかのぼれるか。縄文人から弥生人への移行は、渡来か自律変化か? 最新の知見をもとに列島人の起源に迫る。