新刊書籍
レーベルで絞り込む :
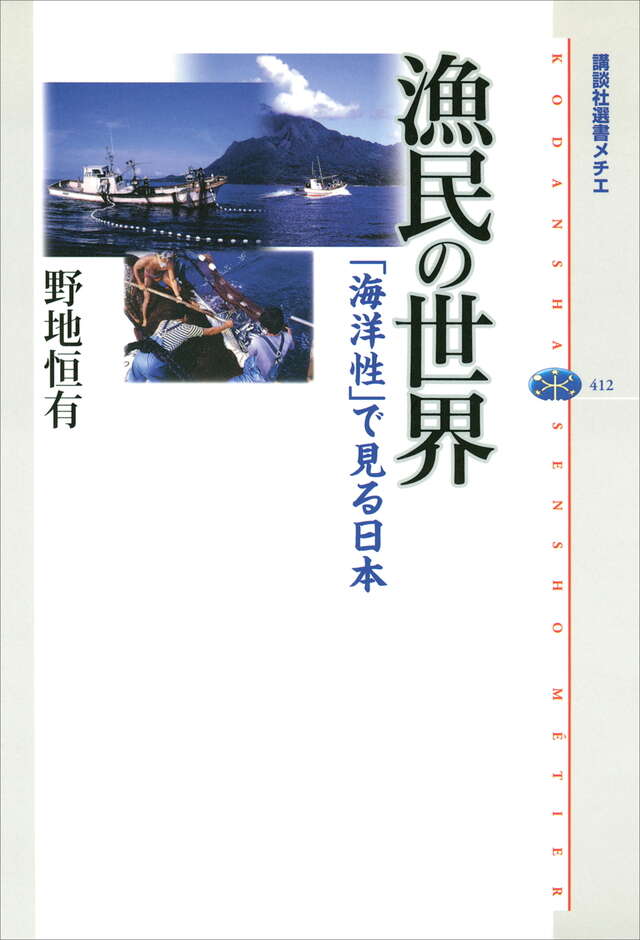
2015.07.24発売
漁民の世界 「海洋性」で見る日本
講談社選書メチエ
知られざる海の生活から見るもう一つの日本
日本人の中には「海」がある。なぜ田植えのときにイワシを食べるのか。山村でも神事の供え物には海の魚を使うのか。日本文化の基層としての海洋性。村落共同体ともノマドとも異なる漁民たちの「ゆるやかな定住」。知られざる海の生活から見えてくる「もう一つの日本」。柳田国男以来の硬直した日本観の見直しを迫る画期的論考。
【目次】
序章──「海洋性」を抱く「山島」
第一章 海洋性とは何か
1 海と日本文化
2 海洋性のボーリング──渋沢敬三と海
3 土の因縁──柳田国男と海
4 海と酒と旅と人生──桜田勝徳と海
第二章 地先沿岸漁村という世界
1 寄り魚漁に支えられた村の生活
2 半農半漁の農業
3 陸上の責任者と海上の責任者
4 地先沿岸に入り込んでくる人たち
第三章 海を求めた日本人
1 稲の祭りも海を求める
2 ハレの魚はなぜ特定の魚でなければならないか
第四章 地先沿岸漁村の交流のかたち
1 ハエツキとキタリド──寄り魚漁衰退の後に
2 屋久島とヨロンノ衆
3 隠岐と糸満漁民
4 伊豆半島下田港のイサバとトサカツ衆
5 対馬の本戸と寄留
第五章 出漁漁民の移住集落という世界
1 ロープ引き漁の一日・一ヵ月・一年
2 移住漁業の専一性
3 移動をはらんだ定住の論理
終章──日本文化の基層としての「海洋性」
あとがき
索引

2015.07.24発売
日本人の脳に主語はいらない
講談社選書メチエ
内田樹さん絶賛!! “「身体で読む」私には、たいへん腑に落ちる説明である。”
脳科学が明かす日本語の構造
英語で“I love you.”とは言っても、日本人は決して「私はあなたを愛している」などとは言わない。「雨が降る」を英語で言うと、“It rains.”のように「仮主語」が必要になる。――これはどうしてか?人工知能研究と脳科学の立場から、言語について実験と分析を重ねてきた著者が発見した新事実。それは、日本語の音声がもつ特徴と、主語を必要としない脳の構造とが、非常に密接な関係にあることだった。斬新な視点による分析と、工夫をこらした実験、先行研究への広範な検討を重ねて、主語をめぐる長年の論争に大きな一石を投じる、衝撃の書!
【目次】
はじめに
1.人は言葉をどのように理解しているか
2.仮想的身体運動としての想像
3.仮想的身体運動による言葉の理解――身体運動意味論
4.心の理解――仮想的身体運動による心の理解
5.母音の比重が大きい言語は主語や人称代名詞を省略しやすい
6.主語や人称代名詞の省略は母音で決まる――身体運動統語論
7.文法の終焉
おわりに
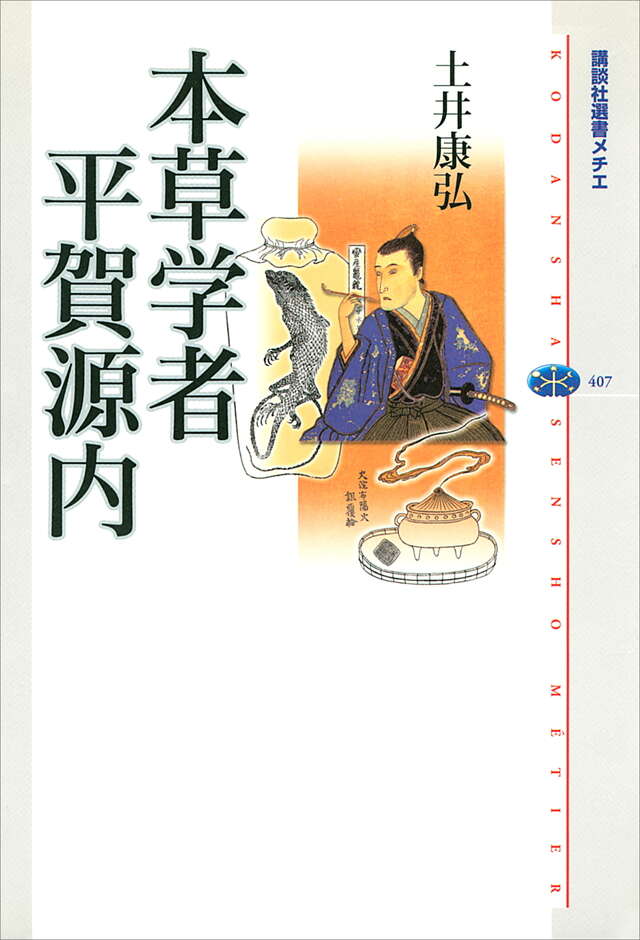
2015.07.24発売
本草学者 平賀源内
講談社選書メチエ
世間から「山師」と誹られた流行学者の知られざる生涯
「我よりおとなしく人物臭き面な奴に、却て山師ハいくらも有」――。江戸中期の大人気学者平賀源内はその華やかな活躍とは裏腹に、自らを「貧家銭内(ヒンカゼニナイ)」と嘆きながら、罪人となり生涯を終えた。エレキテルや火浣布の製作、『物類品隲』執筆など本草学への熱い思いを体現しながら、「山師」と誹られた源内。誰もが知っていそうで実は知られることの少なかった、学者としての実像に迫り、再評価を試みる。
【目次】
はじめに──我ハ山に似たるを以て芸の助けとす
第1章 本草学とは何か
1 本草学のはじまり
2 江戸初期~中期の本草学
3 吉宗の奨励政策
第2章 本草学者源内の誕生
1 江戸へ
2 高松藩への再雇用
3 「芒消」製作
4 田村一門のかかわり
第3章 『物類品隲』出版
1 東都薬品会の開催
2 「この書が人民の益となることを望む」
3 珍奇な記載物(1)水、土、石の部
4 珍奇な記載物(2)草、虫、鱗の部
5 人参と砂糖
第4章 火浣布の製作
1 火浣布の歴史
2 材料は何か
3 織り出し成功
4 前野良沢の火浣布
5 受け継がれた源内の製法
第5章 本草学への思い
1 資金調達のための文筆業
2 「阿蘭陀翻訳御用」による長崎行き
3 源内焼と綿羊の飼育
4 山師源内
5 「功ならす、名斗遂て年暮ぬ」
6 さらば非常の人
おわりに
主要参考文献と注
あとがき
平賀源内関連略年譜
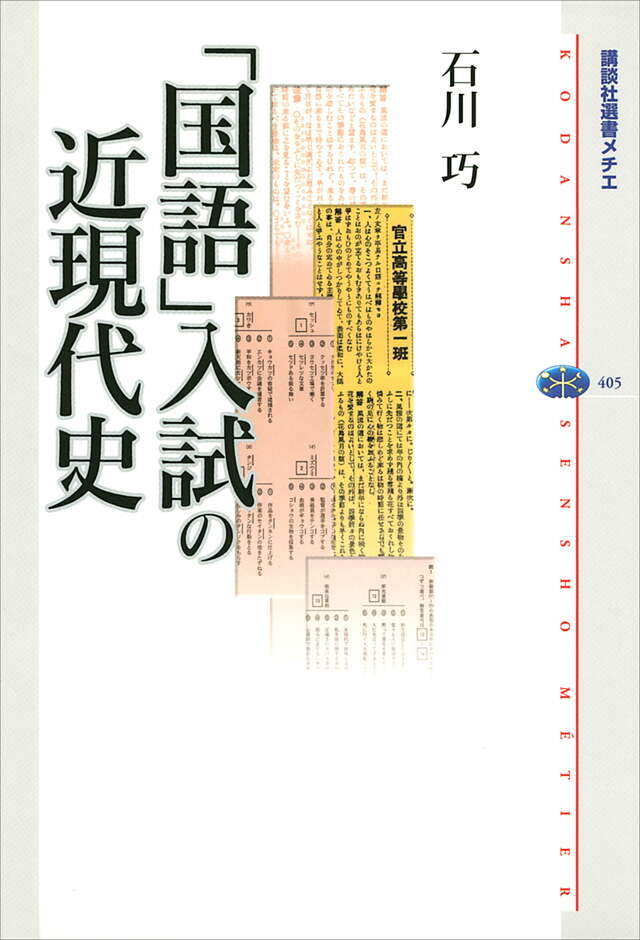
2015.07.24発売
「国語」入試の近現代史
講談社選書メチエ
現代文の読解力は客観評価できるか?
国語入試のなかでも、とりわけ「現代文」という科目は、読解力を問わねばならないため、つねに、客観性と公平性をどう実現するかという難問にさらされてきた。高等学校の共通試験に現代文が定着した大正期から、戦前期を経て、戦後民主主義、小林秀雄と天声人語のブーム、そして共通一次、マークシート化に至るまで、入試問題はどのように国民の言葉=国語を規定してきたのか。その歴史的な文脈を明らかにする力作。
【目次】
はじめに──革命防止装置としての入試現代文
第1章 入試現代文前史
第2章 入試現代文のはじまり
第3章 帝国大学の入試現代文
第4章 「読む」とはどういうことか
第5章 日本精神の発揚と国文学の急成長
第6章 戦後民主主義教育のなかの入試現代文
第7章 「傾向と対策」の登場――予備校と「蛍雪時代」
第8章 「客観」幻想の果て――マークシート化をめぐる言説
おわりに──「国語」の成立

2015.07.24発売
「漢奸」と英雄の満洲
講談社選書メチエ
「中国の歴史は一代では語れない。この書物は『中原の虹』のすばらしいテキストです。」――浅田次郎
軍閥の長の父、国共合作の立て役者の子。「傀儡国家」=満洲国総理の父、反日活動家の子。「売国奴」と「英雄」の運命を分けたものは何か。運命の地、満洲を舞台に、歴史の転変に翻弄された5組の父子の数奇な生を描く。
【目次】
はじめに
第一章 張作霖と張学良
1張学良の成育環境
2郭松齢との出会いと別れ
3爆殺事件
4満洲事変の屈辱
第二章 張景恵と張紹紀
1豆腐屋からの立身
2国務総理
3捕虜から戦犯へ
4戦犯管理所での生活
第三章 王永江と王賢〓
1剛毅な実務家
2「保境安民
3軍隊の壁
4実務官僚の系譜
第四章 袁金鎧と袁慶清
1科挙落第生の逆転
2袁慶清の苦悩と覚悟
第五章 于冲漢と于静遠
1語学堪能者の宿命
2「大漢奸」への道
3于静遠の幻想
おわりに
註
参考文献一覧
あとがき
索引
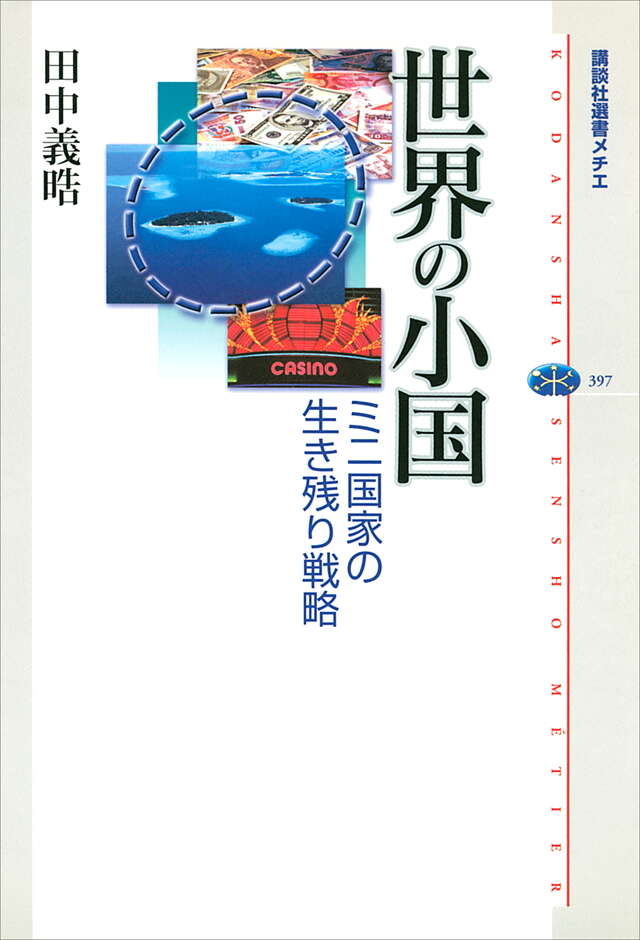
2015.07.24発売
世界の小国 ミニ国家の生き残り戦略
講談社選書メチエ
したたかな外交戦略と個性的な経済政策。大国主導の国際社会を生き抜く術とは?
ツバルのドメイン名ビジネス、バハマのオフショア金融センター、ルクセンブルクの欧州外交戦略……。大国ではありえない個性的でしたたかな国家運営をする小さな国々。最高の政治的贅沢か、それとも国際社会のお荷物なのか? 世界の国家数の2割強を占め、今後も増え続けるであろう小国の魅力と、小ささゆえの有利性と不利性を国際関係論のエキスパートが論考する。
【目次】
はじめに 新たな国際的プレーヤー
今、なぜ小国なのか/小国の定義
第1章 ツバルという国
週二便の国際線/独立への道/依存経済/ドメイン名ビジネス
第2章 小国の系譜
「小面積の共和国」という理想/古代都市国家の興亡/中世・近世ヨーロッパの小国家群/第三世界との共通点
第3章 小国の誕生
「世界最古の共和国」サンマリノ/激動のヨーロッパ史の中で/「植民地独立付与宣言」を追い風に/国連が「産婆役」/主権国家といえるのか/民族自決権の功罪
第4章 国際政治のキャスティング・ボート
「世界の良心」/京都議定書をめぐる対立/IWCをハイジャック/援助外交のコスト・パフォーマンス/共産主義を崩壊させたバチカン/保守的教義への批判
第5章 グローバリゼーションという逆説
世界のオフショア金融センターとして/「タックス・ヘイヴン」バハマ/ダーティー・マネーの温床?/タックス・ヘイヴンvs.経済協力開発機構
第6章 太平洋島嶼国をめぐる国際政治
「不穏な太平洋」/米ソ角逐を手玉に/中・台の援助競争/フィジーをゆるがせた民族主義/ソロモン諸島の「国家破綻」/変化した安全保障のパラダイム
第7章 カリブ海と太平洋の小島嶼経済
両地域の類似点、相違点/経済困難を抱える太平洋の小島嶼国/オセアニア島嶼経済の四類型/より発展したカリブ海地域/「3S」に賭ける/地域統合でさらなる発展
第8章 欧州の伝統的小国家群
経済オリンピックの勝者/成功の背景/モナコのジレンマ/リヒテンシュタインとサンマリノの経済戦略/「小国性」を武器にするルクセンブルク
第9章 アラブの小さな首長国
カタールとバーレーン/「中東のCNN」アルジャジーラ/アメリカとサウジアラビアのはざまで/「レンティア国家」/岐路に立つバーレーン
第10章 アフリカ大陸の六つのミニ途上国
小さな最貧国/「富める国と貧しい民」赤道ギニア/観光立国セーシェル
終 章 小国が拓く新時代
政治的ダーウィニズムをこえて/小国から見た世界/不安定要因か、社会の木鐸か/日本との関係
あとがき
参考文献
小国案内

2015.07.24発売
空の実践 ブッディスト・セオロジー(4)
講談社選書メチエ
宗教の実践の意味とは何か
世界的碩学による大好評講義シリーズ第4弾
仏教の中核思想「空」とは何か。自己否定とそれを通してのよみがえりという「空」の実践のプロセスから、実践行為としての仏教の本質を考究する、碩学渾身の思考。
【目次】
はじめに
第一章 空の実践
第二章 空と縁起
第三章 空性と自性
第四章 行く人は行くか
第五章 言葉を超える
第六章 『般若心経』における空
第七章 空の実践と真言
第八章 空の実践と三身仏
第九章 実践の行程──井上円了のパラダイム
第一〇章 よみがえる世界──空海におけるマンダラ
第一一章 空の実践の二方向
索引

2015.07.24発売
誓いの精神史 中世ヨーロッパの<ことば>と<こころ>
講談社選書メチエ
言われた言葉には魔が宿る
誓いに込められた中世人の世界観を読み解く
誓いの言葉はなぜ間違えてはいけないのか。なぜ文書よりも言葉が重視されたのか。決闘の勝ち負けによって真偽が定まり、目撃していなくても事件の証人になることができる、その根拠はどこにあるのか。西洋中世の特異な習俗から、中世人の「こころ」に迫る。
【目次】
序
第一章 ことばの射程
ことばと文化/文字の文化と声の文化/証しのかたち/この証書が目に入らぬか/記憶に対する疑い/記憶から記録へ?/声の権威/正義はつくられるもの?/ことばと身振り/「誓い」はからだを介して行なわれる/ことばと意図のせめぎあい/いまなぜ「誓い」なのか
第二章 「誓い」の場
人を試す「誓い」/神明裁判/証明手段としての「誓い」/決闘/よろめき夫人!?
第三章 人を信じる「誓い」
信頼を基盤とする社会/雪冤宣誓/「誓い」だけで犯罪は立証可能になる/宣誓補助人と証人──名誉にかけて誓う/合意形成の場/讒訴に対する不信感/『狐物語』/勝敗より和解を/「誓い」から証言へ/なくならない決闘/『最後の決闘』/正義は決闘では決められない
第四章 人を縛る「誓い」
言葉の呪縛力/『黄金伝説』/偽誓──意図はどこに?/ブルヒャルトの『教令集』/「誓い」の解除をめぐる争い──叙任権闘争/中世の秩序をゆるがす大問題/形式から意図へ/「誓い」の「内面化」/異端審問──裁かれた乙女、ジャンヌ・ダルクの断罪/「誓い」の変容を象徴する事件
第五章 「誓い」の位相
「誓い」の本質は何か/封建制の「誓い」/「誓い」の絆/『帝国年代記』/強化される「誓い」の力/「誓い」と教会/「誓い」の禁止/二種類の「誓い」/相互盟約/ザクセン戦争/神の平和/誓われた平和/ラントフリーデ/平和令の変質/「誓い」の義務/「誓い」のかたち/臣従の誓い/「誓い」からの脱却/「誓い」の拒絶・回避/「誓い」のヒエラルヒー/代行宣誓──王の不可侵性の構築/変化のきざし/戴冠式の「誓い」/テ・デウム賛歌
結び
註
あとがき
索引

2015.07.24発売
ホワイトヘッドの哲学
講談社選書メチエ
超難解な思考をあざやかに解説! ホワイトヘッドの世紀は来るか!?
本書は、ホワイトヘッドという哲学者のひじょうに偏った入門書である。読者の方々が、ホワイトヘッド自身の本を手にとってみようか、という気になられることだけを目指した。他意(?)はない。わかりやすさを重視したので、かなり強引なところもあると思う。特に入門篇は、こちらの興味にぐっとひきつけて書いた。淡々と説明だけをするというのは、どうしても性にあわない。それぞれが、1話完結のエッセイとしても読めるように工夫したつもりだ。上手くいったかどうかは、保証の限りではない。もちろん全体として一貫した流れはある。いってみれば、本書全体が、ホワイトヘッドが考えたこの宇宙とおなじあり方、つまり【非連続の連続】になっているといえ・・・といいのだが。<[まえがき]より>
【目次】
まえがき
第1章 入門以前 ホワイトヘッド哲学の見取り図
1 ホワイトヘッドの世紀
2 出会い
3 なぜかくも難解なのか
4 哲学は詩である
5 【こと】と【もの】
6 ひとつの出来事とはなにか
7 電磁気的な時代
8 相対論と量子論
9 生きいきとした自然
10 具体的なもの
第2章 入門篇 ホワイトヘッド哲学そのもの
1 唯一無二のそれ(actual entity)
2 〈わたし〉ということ
3 非連続の連続
4 かかわり方(prehension)
5 知るための手がかり(eternal object)
6 フィーリングの海
7 物質と記憶
8 象徴によるつながり(symbolic reference)
9 自己超越体(superject)
10 一元、二元、多元
11 神と世界
第3章 応用篇 エポック的時間とはなにか
1 エポックとはなにか
2 純粋持続
3 刹那滅
4 エポック的時間
あとがき
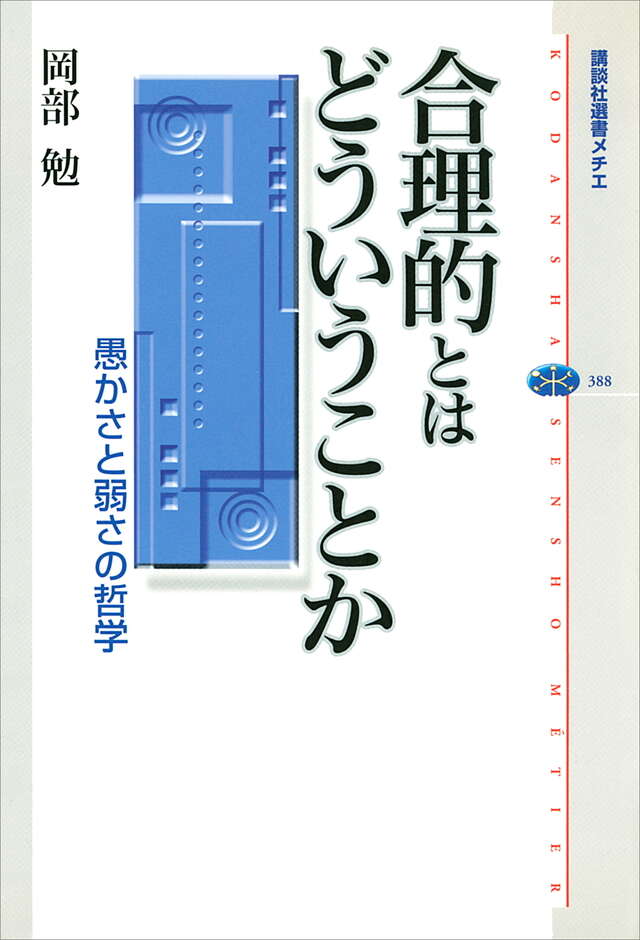
2015.07.24発売
合理的とはどういうことか 愚かさと弱さの哲学
講談社選書メチエ
私たちは本当に“理性的存在”か?
なぜ私たちは、不合理な行動をしたり、意志の弱さや愚かさを見せたりしてしまうのか。それらの行為は「理性」に反したものなのだろうか。この問いから、人間であるという、そのあり方の本質が見えてくる。進化の歴史から日常的な問題まで幅広いスケールで繰り広げる「合理的である」ことをめぐる思考の冒険!
【目次】
序章 不合理な存在
日常の合理・不合理という問題/社会性と計画性/犯罪と推理/人間の愚かさと弱さ/人間性の表現/用語の説明
第一章 人間の不合理・愚かさ・弱さ
1 意志の弱さと行為の選択
自己決定という問題/意志の弱さと規範性/合理性の要求/人のあり方/基礎的合理性と規範的合理性/合理性の能力の喪失/可能性と現実性
2 こころの仕組み
価値と目的の生成/意識の必要性/行為の選択装置/感情と理性の対立図式/感情と欲求のシステム/感情の役割と儀式/感情と象徴能力
3 人間性の成熟
理性の起源/目的の実現/意志の弱さと選択された行為/成熟の三つの段階
第二章 人間だけが不合理であり得る理由
1 人間性の起源
遺伝子的な仕組み/人間になる仕組み/人間と動物の連続と不連続/理性的存在/言語と理性
2 不合理性の源泉
BBQとサバンナの風景/自然発生的な小集団社会/言語の役割/集団維持システム/言語の発達/連帯と協力
第三章 不合理・愚かさ・弱さと常識の不寛容
1 私たちが求める合理性
合理的な根拠/公正さの要求/ソクラテスの問題/意見の収斂/ソクラテスのジレンマ
2 プロフェッショナリズム
専門家モデル/認知主義者/道徳的葛藤/合理的解決/自発的能力/技術的知識と合理性
3 アマチュアリズム
自然の制約/自然言語/洗練された形而上学者/秘密を解く鍵/変更を可能にする仕組み/規則に従う/推論の一般性/日常の推論
第四章 人間の自然・不自然と不合理
1 自然・不自然・不合理
人間の自然/自然主義/第二の自然/活動・行動・行為/人間に固有の活動/身体的条件/行為の記述と評価と説明
2 自然的世界と価値の世界
反自然主義/構成主義の考え方/複数の自然言語/言語使用の正しさ/外的制約/幸福の追求/反実在論/実在論の可能性/愚かな生
註
参考文献
あとがき
索引

2015.07.24発売
仏とは何か ブッディスト・セオロジー(3)
講談社選書メチエ
宗教の本質を問う
世界的碩学による大好評講義シリーズ第3弾
あらゆる宗教の根源存在である「聖なるもの」は、仏教においてどのような姿でイメージされたのか。儀礼をキーワードに、仏・菩薩と人間との関わりかたの具体的なプロセスを通じて、いよいよ仏の本質へと迫る。
【目次】
はじめに
第一章 仏のすがた
第二章 仏への行為
第三章 ヴェーダ祭式ホーマ
第四章 ブッダの涅槃
第五章 仏塔の意味
第六章 プージャー│宗教行為の基本型
第七章 ジャータカ物語と仏の三身
第八章 大乗の仏たち│阿弥陀と大日
第九章 護摩│儀礼の内化
第一〇章 浄土とマンダラ
索引
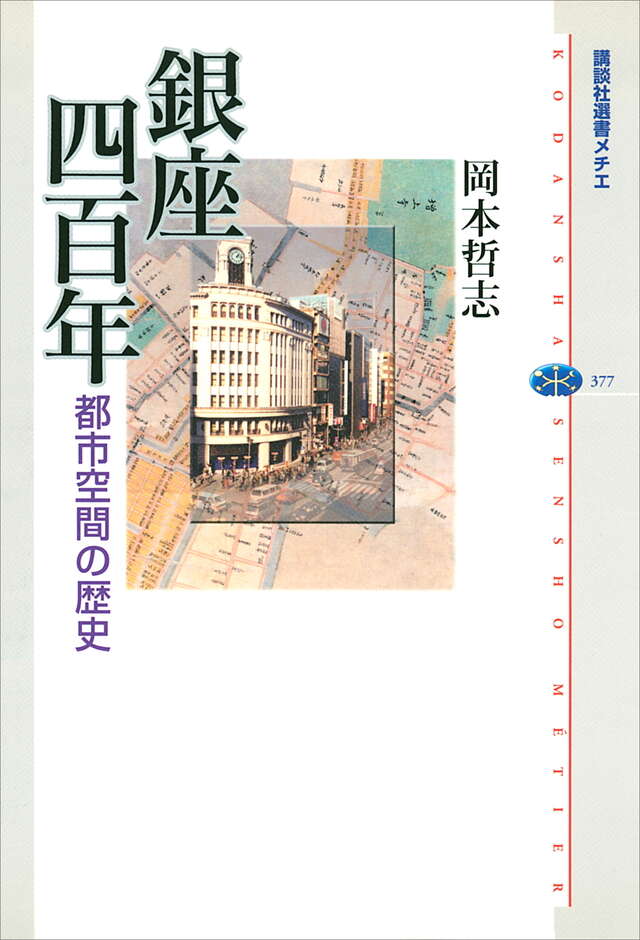
2015.07.24発売
銀座四百年 都市空間の歴史
講談社選書メチエ
「銀座の空気」はこうして作られた
江戸の誕生から町人地としての発展、明治の煉瓦街建設からモダン都市成立、そして戦後の変容。魅力あふれる銀座という街の空気は、幾重にも重ねられた、都市の歴史が作り出したものだった。都市研究者が自身の足で街を歩きつくし、資料を丹念に読み込み、銀座の構造と進化の過程を鮮やかに描き出す。
<本書の内容>
はじめに
第一章 現代の基層を読み解く(江戸初期)
1 江戸城下町の空間演出の手法
2 空間をつくりだす知恵
3 寛永期に表現された江戸
第二章 明暦大火後の街づくり
1 変化する町人地、変化しない町人地
2 変容した街区構成を読み解く
3 町屋敷内の空間変容プロセス
4 江戸時代の銀座の空間表現
第三章 江戸と融合した煉瓦街建設の試み(明治初期)
1 西洋風街並みの出現に向けて
2 日本初の西洋風街並みの出現
3 明治初期の社会変化と土地動向
4 近代における銀座の選択
5 江戸の街区構造を活かした煉瓦街
第四章 人の和が育てた街の厚み(明治後期)
1 江戸の骨格を近代に継承する構図
2 煉瓦街建設後の街の変化
3 モダン都市空間への予感
4 空間の多様性と街のコントロール・システム
第五章 歴史の文脈に裏付けられたモダン都市の創造(昭和初期)
1 近代の主役が集まる場所
2 街並みのモダンと銀座フィルター
3 産業から脱皮する三十間堀川沿い
4 街と建築がつくりだす空間の緊張感
第六章 戦後から現在に至る銀座
1 戦後における土地と建物の変容動向
2 都市空間の仕組みと路地構造
3 期待される新たな銀座像(外堀通りとみゆき通り)
おわりに
注
参考文献
索引

2015.07.24発売
身体の哲学 精神医学からのアプローチ
講談社選書メチエ
人は皆やっかいな身体を生きている
心と体は別ものではない。互いに交差し合い、しかも他者のからだへと開かれている。拒食症、解離症、境界例などの心-身に関わる病例に依りながら、「こころ」と「からだ」の問題を根底から問い直す。
【目次】
はじめに
第一部 身体という原点
第一章〈エス〉から始めよう
1 心身問題
2 グロデックの思想
3 生命的主体としての〈エス〉
4 十字架を背にしたキリスト
第二章 身体の精神病理学
1 基礎学問としての精神病理学
2 人間学的実存論
3 精神疾患をどう名づけるか
第二部 身体の諸相
第三章 疎外する身体 拒食/過食症
1 女子高生の症例
2 「拒食/過食症」
3 ボディイメージと自己の成立
4 被投性と「私」
5 自己肯定感の希求
第四章 乖離する身体 解離症
1 男子専門学校生の症例
2 歴史から見た解離
3 「解離症」
4 主体性の欠如と解離感
5 解離の症候論
6 過剰身体の乖離
7 ハイマート
第五章 癒合する身体 境界例
1 女子大生の症例
2 境界例の歴史
3 陳述のもつ身体性
4 境界例感と投影同一化
5 間身体性における非人称の主体
6 自己存在の問い
第三部 身体の構造
第六章 生のキアスム
1 二重の身体とノスタルジー
2 ハイマートと一次愛
3 関係としてのキアスム
4 「私」という存在
第七章 時間としての身体
1 身体の声を聞く
2 身体のセクシュアリティ
3 キアスムと癒し
4 それぞれのキアスム
5 ハイマートから未来へ
おわりに
参考文献
索引
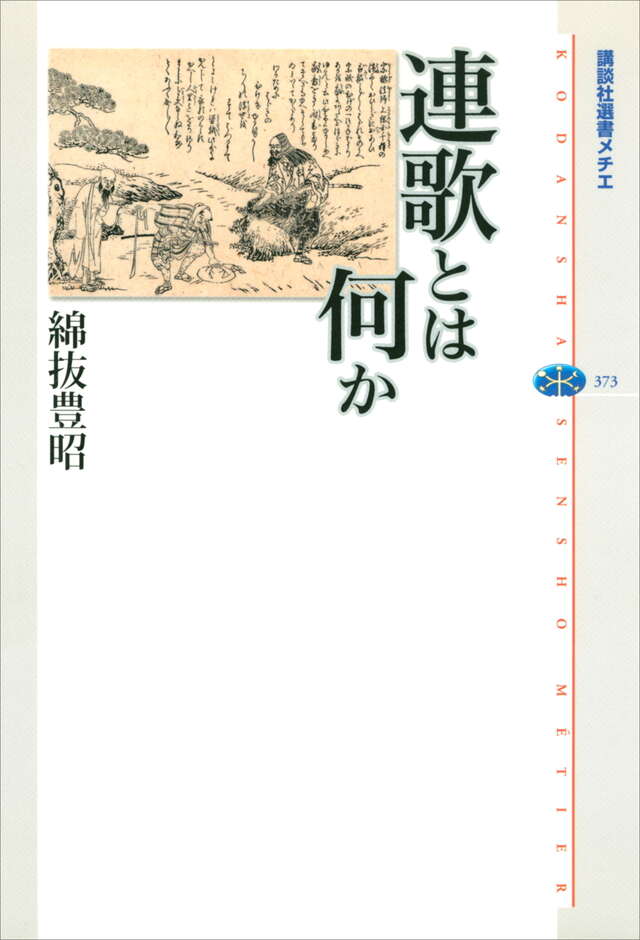
2015.07.24発売
連歌とは何か
講談社選書メチエ
中世人がもっとも愛した文芸の全貌
創作しつつ味わい、味わいつつ創作する、機知と友愛のアート。二条良基・一条兼良・宗祗ら天才の仕事を軸に、能・茶・花をしのぐほどの人気を誇りながら、近代とともに忘れられた文芸の全歴史をたどる。
[本書の内容]
はじめに
第一章 連歌の世界
1 「連歌」とは何か
2 短連歌の世界
3 長連歌の世界
4 連歌会の空間
第二章 連歌の式目
1 式目の世界
2 「水無瀬三吟百韻」を読む
第三章 連歌の歴史──起源から安土桃山時代まで
1 日本武尊から鎌倉時代まで
2 二条良基と本格的連歌の始まり──南北朝時代
3 連歌七賢──室町時代その一
4 天才宗祇とその弟子たち──室町時代その二
第四章 連歌その後
1 地方への広がり──中世から近世へ
2 安定と停滞──近世の連歌
3 明治以後のこと
註
おわりに
索引

2015.07.24発売
項羽と劉邦の時代 秦漢帝国興亡史
講談社選書メチエ
鴻門の会、四面楚歌――
『史記』の虚実を読み解く
「秦を滅ぼすものは必ずや楚ならん」――。中国を最初に統一した秦帝国は、なぜ短期間で滅んだのか。なぜ農民出身の劉邦が項羽に勝利したのか。秦と楚、2つのシステムという観点から「鴻門(こうもん)の会」「四面楚歌」に代表される『史記』史観をとらえ直し、漢王朝成立までのドラマを描き出す。
【目次】
はじめに もう一つの項羽と劉邦
竹簡や木簡が語ること/秦と楚の社会システム
序 章 始皇帝と秦の統一
始皇帝陵と兵馬俑/秦国の興起/秦の富国強兵──商鞅の変法/法制と軍事編成/統一の理念/なぜ短期間で滅んだのか
第一章 南方の大国・楚
楚文化のイメージ/懐王の時代/長江流域の統合──鄂君啓節/楚の社会と習俗──包山楚簡/楚都の陥落/東方の楚国へ
第二章 秦帝国の地方社会
秦代の郡県制/地方行政と労役/沛県の官府と社会/劉邦と周辺の人びと/王族たちの怨み/東方社会の人びと/項梁と櫟陽の獄掾
第三章 陳渉・呉広の叛乱──楚国の復興
二世皇帝と扶蘇/辺境への徴発/秦の制度と戍卒/扶蘇と項燕を称す/陳王となる/楚国の復興をめざして/陳王の死
第四章 項羽と劉邦の蜂起──楚のもとで
秦と東方の異なる原理/始皇帝の巡行と江南社会/項梁・項羽の蜂起/楚の国家体制/沛県の蜂起/沛公の社会基盤/項梁の死/鉅鹿の戦い
第五章 秦帝国の滅亡──「鴻門の会」の謎
関中に王とする約束/項羽と章邯の会盟/沛公の行軍/覇上に駐屯する/鴻門の会/樊〓の自慢話/咸陽城の焼失
第六章 西楚覇王の体制──二つの社会システム
十八王の分封/漢中へ──分封への不満/関中の掌握/漢の社稷を立つ/義帝の死と諸侯/彭城の戦い
第七章 楚と漢の戦い──戦略と外交
戦いに敗れて/人質からみた楚国/韓信の戦略と兵法/斉をめざす韓信/生産と軍事補給/広武山の対面/外交の知恵を学ぶ/漢覇二王城での会見
第八章 項羽の敗北──第三の男、淮陰侯韓信
東方への進軍/垓下の戦い──四面楚歌/烏江での最期/項羽をめぐる伝え/楚王韓信の処遇/楚の体制の終わり/地域を再編する試み
終 章 漢王朝の成立──地域社会の統合
項羽と劉邦の評価/両陣営のブレーン/長安と地方社会/功臣から劉氏の封建/高祖の死と呂后/武帝と司馬遷/東アジアのなかで
あとがき
参考文献
戦国・秦漢時代の年表
人名索引

2015.07.24発売
儒教と近代国家 「人倫」の日本、「道徳」の韓国
講談社選書メチエ
忠孝、人倫、理想道徳……
日韓それぞれの近代思想史!
同じく儒教を政治思想の基盤としながら、日本と韓国はなぜ、異なる近代化の道をたどったのだろうか。伊藤仁斎に代表される近世儒学の人倫論と、水戸学、明治憲法、教育勅語の関係とは。朱子学を柱とする韓国は、いかにして文明開化から戦後の朴正煕大統領の維新憲法にまで至ったか――。両国の近代と政治思想を問い直す画期的論考。
【目次】
はじめに
第一章 近代国家の基盤思想としての近世儒教
1 伊藤仁斎と人倫
2 性は気質である
3 韓国における普遍価値の追求
4 道徳理想主義への希求
第二章 西洋文明の登場とその受け入れ方
1 啓蒙思想としての文明開化論
2 西欧中心の文明開化──福沢諭吉
3 儒教中心の文明開化──兪吉濬
第三章 日本の近代国家への移行
1 国家理念の形成
2 万世一系の皇統
第四章 日本の近代国家の思想的組み立て
1 明治憲法
2 水戸学の「正名論」と「忠恕」
3 教育勅語と国民道徳
4 忠と孝、そして人倫
第五章 韓国の近代思想の諸相
1 近代意識の始まり
2 世界観の変化
3 朝鮮における近代意識の挫折
第六章 韓国の維新憲法と国民教育憲章
1 思想史からみた植民地時代
2 近代国家の樹立への構想
3 国民意識の高揚
4 近代国家への経験
おわりに
註
あとがき
索引
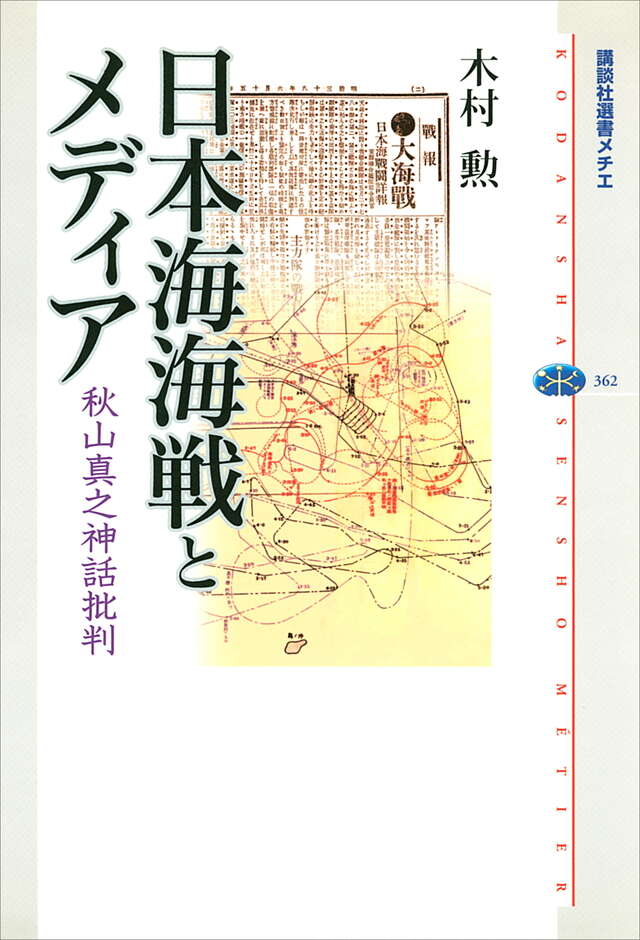
2015.07.24発売
日本海海戦とメディア 秋山真之神話批判
講談社選書メチエ
極秘海戦史でわかった語られざる真実
連合艦隊司令長官・東郷平八郎とその参謀・秋山真之。この軍神と天才によって敢行された丁字戦法によって、連合艦隊はロシアのバルチック艦隊を撃破――。日本海海戦の勝利は胸のすく快挙として昭和の軍国主義イデオロギーの核心を形成していく。その伝説の影響は今日にも及ぶといって過言ではない。これまで明らかにされることのなかった史実を、第一級史料『極秘明治三十七八年海戦史』を丹念に読み解き、浮き彫りにするとともに、神話を作りあげていったメディアの側をも批判的に検証する。
【目次】
はじめに
序章 日本海海戦イメージの変遷
「天気晴朗なれども波高し」は暗号か/日露戦争への道/史料について
第1章 「敵前大回頭」とは何か 21
一八〇度ターンは当然のこと/軍関係者は「大転舵」/「大回頭」の出自/無線通信のトラブル/円運動は遭遇予定地点のズレから始まった/艦隊編成について
第2章 軍神の誕生
緒戦の旅順口攻め/夜襲作戦の実際/山本五十六の批判/三度の閉塞作戦/秋山の「高ぶり」/副官電に登場した「軍神」/「成功」と報じたのは新聞/マカロフ提督戦死
第3章 ウラジオ艦隊、潰滅せず
戦艦「八島」沈没の隠蔽/輸送船被害キャンペーン/上村艦隊の苦渋/「報道の自由」時代か/体面をとりつくろう体質/八月十日、決まらなかった丁字戦法/八月十四日、ウルサン沖海戦
第4章 秋山作戦の迷走 109
「四月十二日」戦策/「四月二十一日」改訂追加戦策/「五月十七日」追加戦策/「五月二十一日」改訂戦策/藤井証言「艦隊戦策変更の真相」/藤井証言「奇
襲隊取止めの真相」/藤井証言「津軽海峡転位についての会議の真相」/島村速雄の遅参/東郷は気配り調整型
第5章 「開戦後三十分で勝利」したか
二時四十五分決着とした「戦闘詳報」/秋山が強調した「三十分」/第二戦隊「独断専行」のはじまり/第一戦隊と別れた第二戦隊/公刊戦史の奇妙な記述/検証されなかった「独断専行」/ロシア側が評価する上村の行動/「主将は口喧しき号令者にあらず」/ロシア戦史のロジェストウェンスキー評価
第6章 メデイアはどう報じたか 185
丁字戦法と明治三十七年「一月九日戦策」/海軍PR文と七段構え/事実を秋山の「論」に押し込む作為/PR文は特ダネか/丁字戦法成立の経緯/抜擢された
秋山の才/丁字戦法の明治三十七年、同航戦の三十八年/島村速雄の気質と秋山真之の傷
終章 その日とそれ以後
あとがき
資料 1 戦闘詳報 2 海軍PR文 3 連合艦隊解散之辞
索引

2015.07.24発売
起請文の精神史
講談社選書メチエ
小さな紙片に蔵された、広大なる精神宇宙
なぜ天照大神に誓いを立ててはならないのか。神と仏はどちらが上位か。本地垂迹の本質とは何か。中世日本の巨大なコスモロジーは、一片の起請文の中にある。神仏習合から新仏教まで、中世人の豊饒なる精神世界の全貌に迫る。
【目次】
序 章 方法としての起請文
第一章 起請文を読む
1 神文への着目
2 神仏の序列
3 日本の仏
4 弥陀と閻魔
5 死霊の系譜
第二章 神と死霊のあいだ
1 古代の神観念
2 〈命ずる神〉と〈応える神〉
3 御霊とモノノケ
4 〈応える神〉としての疫神
第三章 垂迹する仏たち
1 あの世の仏とこの世の神仏
2 中世人にとっての本地垂迹
3 浄土信仰と垂迹の役割
4 生身仏の時代
第四章 神を拒否する人々
1 コスモロジー論の検証
2 神を拒否する人々
3 神祇不拝の根拠
4 なぜ垂迹を排除するのか
5 法然の決断
終 章 パラダイムに挑む
引用参照文献一覧
あとがき
索引
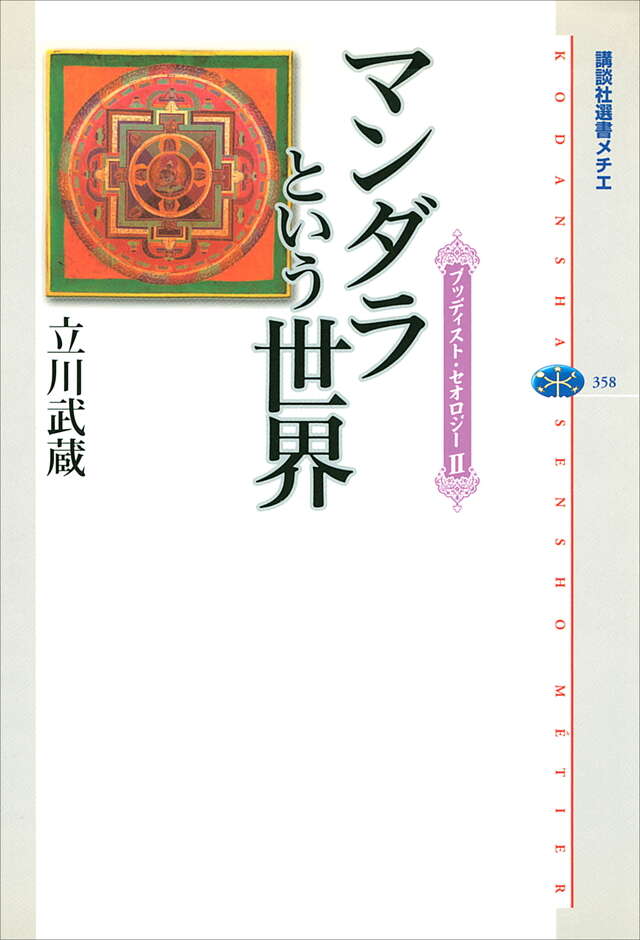
2015.07.24発売
マンダラという世界 ブッディスト・セオロジー(2)
講談社選書メチエ
聖書、インド思想、近代哲学、そして仏教
明快に語りおろす「世界」の本質
いま、社会の急激な変化に対して、仏教のうたう「普遍的な悟り」は有効なのか? 死すべき自分が「他者」の存在を理解できるのか? 各宗教の「世界」把握の方法論をたどり、現代日本に求められる世界観の体系を解明する。
【目次】
はじめに
第一章 世界に対する態度
第二章 自己空間と他者
第三章 世界の中にあること
第四章 縁起と世界
第五章 自然と神
第六章 行為と存在の弁証法
第七章 『旧約聖書』における世界
第八章 『新約聖書』における世界
第九章 インド思想における世界
第一〇章 仏教の世界観
第一一章 世界としてのマンダラ
索引
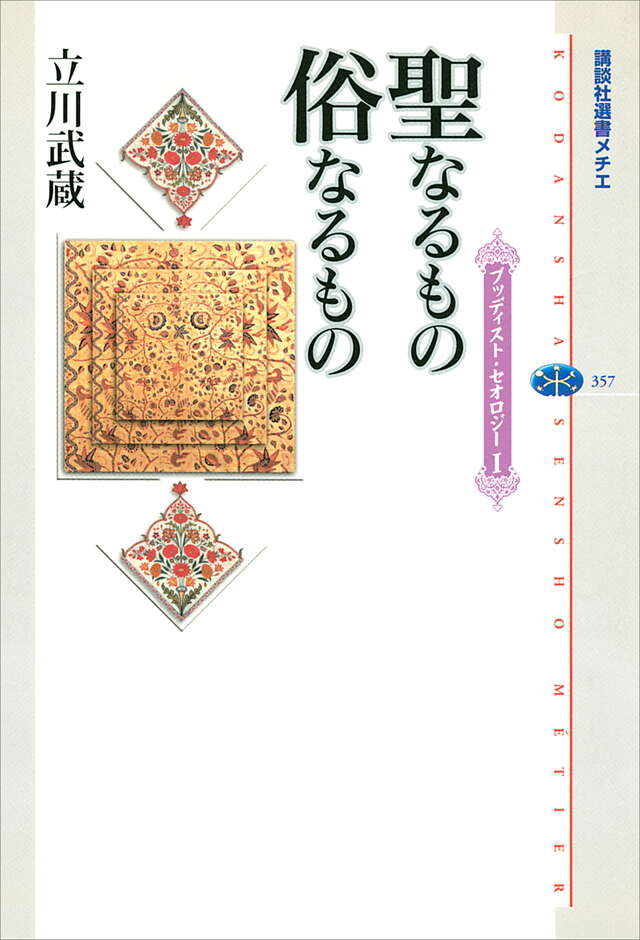
2015.07.24発売
聖なるもの 俗なるもの ブッディスト・セオロジー(1)
講談社選書メチエ
諸宗教の多元的共存は可能か?
「仏教の神学」に挑む連続講義、開幕!
宗教という営みは何を目標としているのか? キリスト教、イスラム教、ヒンドゥー教、そして仏教。異なる世界を出発点としながらも、その上に伝達可能で整合的な知の体系を構築することは、神学的方法論によって可能になる。「聖なるもの」を問う、仏教学第一人者の野心的な講義がはじまる!