新刊書籍
レーベルで絞り込む :

2015.07.24発売
フィリピンBC級戦犯裁判
講談社選書メチエ
マニラの惨劇と戦犯達の苦悩、そして裁判と恩赦をめぐる、語られざる現代史。
「BC級戦犯」の歴史にあらたな光を当てる実証研究。
独立国家として歩み出したフィリピン政府は、戦後の国際状況と対日関係、そして激しい国民の怒りを前に、この裁きに、どのような意義を見出し、困難に直面したか。
一五一名の被告は、いかにして裁かれ、獄中を過ごし、そして処刑、恩赦に至ったか。
日比両国の数多くの資料と当事者たちの証言を丹念に検証し、これまで様々に語られてきた戦犯裁判という問題に、実証の光を当てる試み。
【目次】
はじめに
第一章 フィリピン人の対日感情──一九四五年の原風景
第二章 独立国家としての挑戦──フィリピンの対日戦犯裁判
第三章 モンテンルパの時代──関係性の修復に向けた模索
第四章 恩赦──「怒り」と「赦し」の狭間で
おわりに
注
あとがき
略語表
写真出典一覧
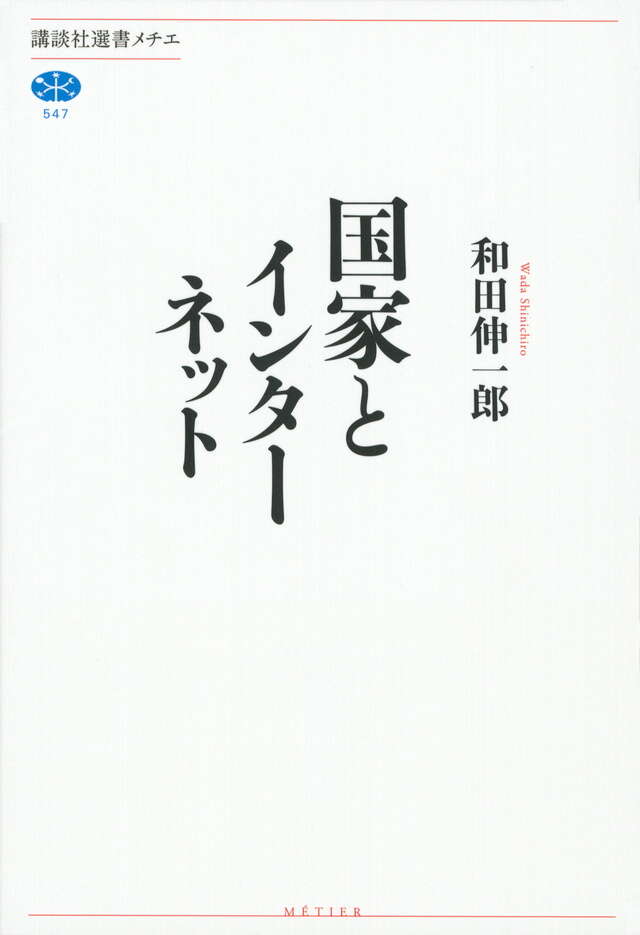
2015.07.24発売
国家とインターネット
講談社選書メチエ
グローバリゼーションの時代、国家とメディアの関係は敵対か、はたまた共存か? IT技術は〈人間〉への福音か、それとも呪いか? ──来るべき世界における権力・メディア・人間の関係を根底から考察する。
【目次】
まえがき
序 章 ネットを〈創造〉したのは誰か
第一章 三つの担い手
第二章 国家とイノベーション
第三章 国家とその《外部》
第四章 新自由主義国家とインターネット
第五章 アラブ動乱とソーシャル・メディア
第六章 インターネットの軍事化
終 章 過剰露出される社会
さいごに──二一世紀は二〇世紀の遺産を食いつぶすだけなのだろうか
註
主要参考文献
謝辞

2015.07.24発売
イスラムと近代化 共和国トルコの苦闘
講談社選書メチエ
「世俗化」=「近代化」、「イスラム」=「反動」では、ない。「共和国トルコの父」ケマル・アタテュルクによって否定されたはずのイスラムは、なぜその後も長く生き残ったのか。幾重にも複雑に絡まった糸を解きほぐし、イスラム世界における近代化の問題を「脱イスラム」のフロントランナー、トルコ共和国の歩みから読み解く。
【目次】
序章 オルハン・パムクと「東洋vs.西洋」
第一章 トルコ共和国成立前後における改革とイスラム
第二章 ポスト・アタテュルク時代のイスラム派知識人
第三章 一九五〇~七〇年代のイスラム──ヌルジュとトルコ‐イスラム総合論
第四章 第三共和政下のイスラム──ギュレン運動、公正発展党
終章 ふたたび「東洋vs.西洋」
引用出典一覧
関連文献
あとがき
執筆者紹介

2015.07.24発売
義経の冒険 英雄と異界をめぐる物語の文化史
講談社選書メチエ
「義経」の物語は、どのように生まれ、そして時代とともに変容していったか。大国主から鬼の国に至るまで、物語の基層を探る旅! 一篇の御伽草子『御曹子島渡』を手に携えて、英雄・義経の物語をめぐる旅が始まる──。『古事記』の大国主神話、吉備真備入唐譚、坂上田村麻呂と悪路王、鞍馬寺の毘沙門天信仰、陰陽道、蝦夷ヶ島などなど、古代から近世までを縦断する義経物語の遍歴を検証し、跡づける冒険的力作!
【目次】
はじめに
第一章 『御曹子島渡』の謎
第二章 鞍馬の山奥から
第三章 東北というトポス
第四章 兵法書の秘密
第五章 中世都市京都の周辺
第六章 吉備真備入唐譚をさかのぼる
第七章 蝦夷ヶ島へ
おわりに
参考文献
引用・参照資料

2015.07.24発売
ドイツ観念論 カント・フィヒテ・シェリング・ヘーゲル
講談社選書メチエ
「いま」「ここで」、〈それでよい〉と語る勇気。近代的思考の基礎を作ったドイツ観念論の四人の代表的哲学者。彼らの思想の核心には、歴史の「これから」におのれの身一つで踏み出す勇気と決断があった。先達の思想を受け継ぎ、かつ乗り越えて行くダイナミックな思想の歩みを、これまでになく平易かつ明快に解説する。(講談社選書メチエ)
「いま」「ここで」、<それでよい>と語る勇気
近代的思考の基礎を作ったドイツ観念論の四人の代表的哲学者。彼らの思想の核心には、歴史の「これから」に、おのれの身一つで踏み出す勇気と決断があった。先達の思想を受け継ぎつつ、かつ乗り越えて行くダイナミックな思想の歩みを、これまでになく平易かつ明快に解説する。
[本書の内容 ]
●ドイツ観念論とは?
●カント『純粋理性批判』の「歴史哲学」
●フィヒテの『知識学』──フランス革命の哲学
●シェリング──自然史と共感の哲学
●ヘーゲル『精神現象学』──真理は「ことば」と「他者」のうちに住む

2015.07.24発売
戦前昭和の国家構想
講談社選書メチエ
関東大震災の三年後に始まった戦前昭和とは、震災復興=国家再建の歴史だった。
社会主義、議会主義、農本主義、国家社会主義という四つの国家構想が、勃興しては次の構想に移っていく展開の過程として、戦前昭和を再構成する!
【目次】
プロローグ
I 社会主義
II 議会主義
III 農本主義
IV 国家社会主義
エピローグ
註
参考文献
あとがき

2015.07.24発売
古代エジプト文明 世界史の源流
講談社選書メチエ
世界史の中で古代エジプト文明が果たした役割とは何か。ミノア、ヒクソス、アッシリア、ペルシア、ギリシア、ローマ……西洋世界の源流のひとつとしてエジプトを捉えたとき、まったく新たな歴史像が立ち上がる。最新の研究成果をふんだんに盛り込み、「外」とのインタラクションという視点の下にその興亡を描き直す、画期的試み! (講談社選書メチエ)
一神教の起源・「モーセ」と「アクエンアテン」、エジプト王国最後の象徴「クレオパトラ」、謎の民族「海の民」の正体、世界に広がる「エジプトの神々」と「来世信仰」、異民族「ヒクソス」の実像と「最古の戦争」カデシュの戦い
歴史の焦点がここにある!
世界史の中で古代エジプト文明が果たした役割とは何か。ミノア、ヒクソス、アッシリア、ペルシア、ギリシア、ローマ……西洋世界の源流のひとつとしてエジプトを捉えたとき、まったく新たな歴史像が立ち上がる。最新の研究成果をふんだんに盛り込み、「外」とのインタラクションという視点の下にその興亡を描き直す、画期的試み!

2015.07.24発売
ギリシア正教 東方の智
講談社選書メチエ
「東」のキリスト教――その深い智慧への誘い
カトリックともプロテスタントとも異なる「もう一つのキリスト教」。
東西教会分裂の原因となった「フィリオクェ」問題、アトス山などの修道生活で発展した独自の瞑想技法、華麗にして深遠なるイコンの世界など、「東」のキリスト教思想の奥義に迫る。

2015.07.24発売
音楽とは何か ミューズの扉を開く七つの鍵
講談社選書メチエ
この不可思議な芸術が持つ“魔力”の根源への探究
空気の波動である音が、時に甘美に心を溶かし、時に激しく魂を揺さぶる魔法となる。この不可思議な音楽というものの正体を、クラシックをはじめ、ロック、民族音楽などの多彩な音と音楽学にとどまらない多様な視点から探究する。すべての音楽好きに贈る、あざやかでかろやかな論考。
【目次】
第1章 音楽は魔法である Music is magic?
第2章 音楽はシステムである Music is system?
第3章 音楽は表現である Music is expression?
第4章 音楽はリズムである Music is rhythm?
第5章 音楽は旋律である Music is melody?
第6章 音楽はハーモニーである Music is harmony?
第7章 音楽はコミュニケーションである Music is communication?
エピローグ──結語に代えて
注
あとがき

2015.07.24発売
鎌倉仏教への道 実践と修学・信心の系譜
講談社選書メチエ
「旧仏教」を読み直し鎌倉新仏教のルーツを探る
鎌倉新仏教はゼロから生まれたのではなかった。偉大な祖師たちの思想が生まれる背景には、先行する有名無名の宗教者たちによる、さまざまな試みがあった。山林修行、戒律の問題、経典への信仰など「実践」をキーワードに、これまで見過ごされてきた、新仏教を準備したさまざまな運動に光を当てる。
【目次】
序章
第一章 優婆塞仏教の系譜
第二章 成熟と分裂──寺院社会の「出世」と「出世間」
第三章 実践と修学をつなぐモノ──経典信仰の諸相
第四章 信心の地平──夢想と観想
第五章 信心のゆくえ
終章
主要参考文献目録
図版出典
あとがき
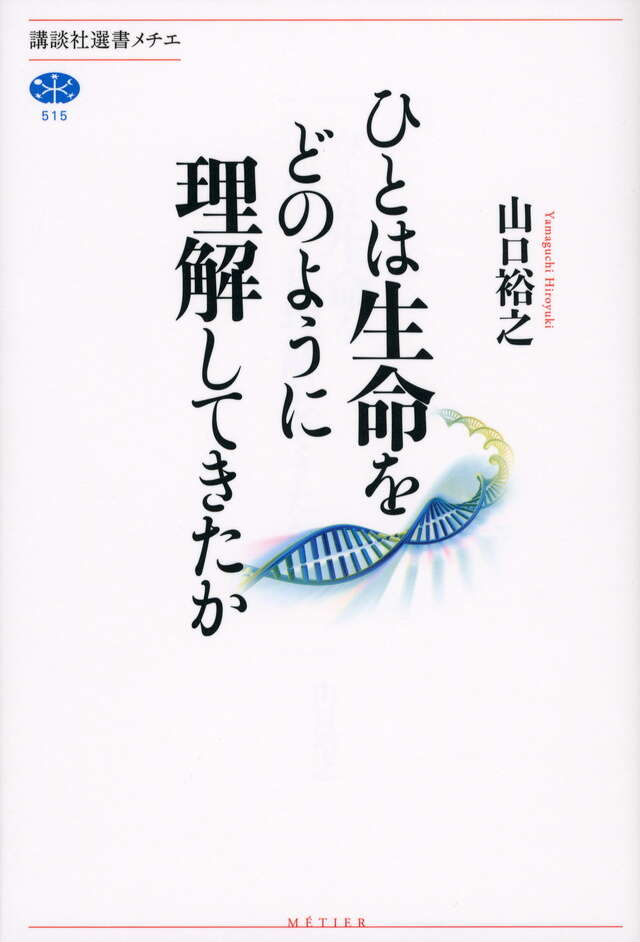
2015.07.24発売
ひとは生命をどのように理解してきたか
講談社選書メチエ
「科学の見方」を問い直すエピステモロジー
DNAから何がどこまでわかるのか?
分子生物学や遺伝科学は「生命」をどう考えているか?
科学は、何を生命として捉え、分析してきたか?
現代生物学が拠って立つ論理と成立構造とは?
「遺伝子」概念が孕む揺らぎとは?
ダーウィン以前から、分子生物学や遺伝科学が急速発展するポスト・ゲノムの現代まで「生物学」の成立過程を辿り、「科学の見方」を哲学の視点から問い直す、生命のエピステモロジー。
【目次】
序章 生物学と哲学
第1章 生命科学の急発展と「遺伝子」概念の揺らぎ
第2章 生物学の成立構造
第3章 二つの遺伝子
第4章 機械としての生命
終章 「生命の存在論」へ向けて
注
引用文献一覧
あとがき

2015.07.24発売
どのような教育が「よい」教育か
講談社選書メチエ
〈よい〉教育とは何か。根本から徹底的に考える。「ゆとり」か「つめこみ」か、「叱る」のか「ほめる」のか──教育の様々な理念の対立はなぜ起きるのか。教育問題を哲学問題として捉えなおし現代教育の行き詰まりを根本から解消する画期的著作! (講談社選書メチエ)
〈よい〉教育とは何か 根本から徹底的に考える
「ゆとり」か「つめこみ」か 「叱る」のか「ほめる」のか──
教育の様々な理念の対立はなぜ起きるのか。教育問題を哲学問題として捉えなおし現代教育の行き詰まりを根本から解消する画期的著作!
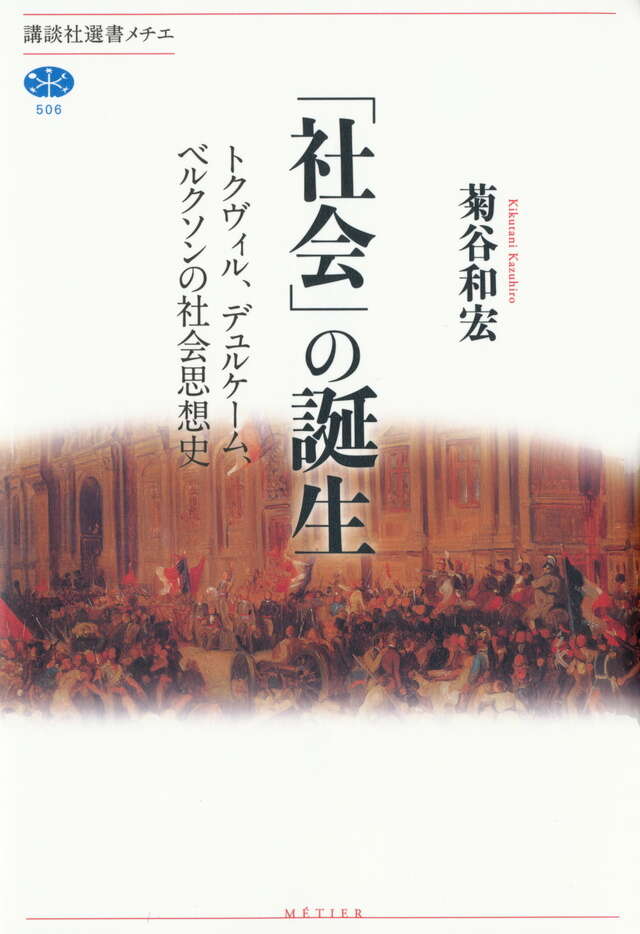
2015.07.24発売
「社会」の誕生 トクヴィル、デュルケーム、ベルクソンの社会思想史
講談社選書メチエ
19世紀フランス、二月革命。
そこから人は、超越性に包まれた「世界」から「社会」という概念を生成した
神という超越性に包摂された世界から、社会という観念が切り離されたとき、「社会科学」が生まれた。
19世紀フランスに生まれたトクヴィル、デュルケーム、ベルクソンという三者を、ひとつの流れとして読み解く、これまでにない「ユニーク」な思想史!
【目次】
序 分解する現代社会──「社会」という表象
第1章 トクヴィル:懐疑
第2章 デュルケーム:格闘
第3章 ベルクソン:開展
終章 誕生した社会:絡繰──相互創造の網と人間的超越性
あとがき
参考文献
注
用語解説
年表
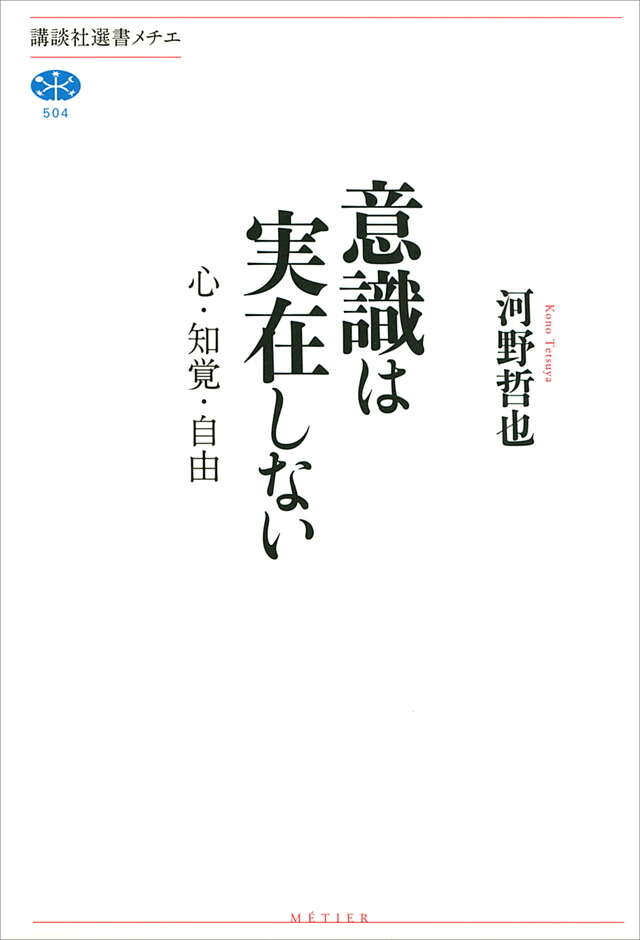
2015.07.24発売
意識は実在しない 心・知覚・自由
講談社選書メチエ
近代的思考の限界を超える! “脳が世界を見ている”のではない! あなたの心は“環境”に広がっている!
心は身体の中に閉じ込められてはいない。知覚は脳に投影されるものではない。
そして、自由とは知覚する世界を探索することである──。
心の哲学やアフォーダンス理論、認知科学、脳性まひと自閉症の当事者研究などの最新の知見が、私たちの世界の見方を根本的に刷新する!
【目次】
序論 環境と心の問題
第1章 拡張した心
第2章 知覚とは何か――クオリアは存在しない
第3章 意図と自由の全体論――当事者研究とアフォーダンス
第4章 社会的アフォーダンスと生態学的記号論、そして、アクターネットワーク
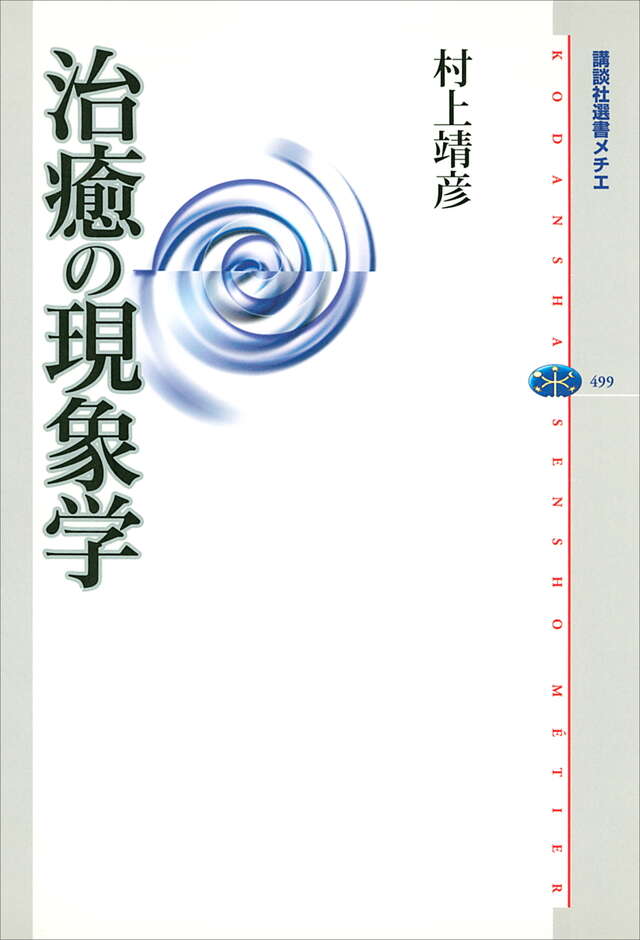
2015.07.24発売
治癒の現象学
講談社選書メチエ
哲学と精神病理学、その交叉点で探究する「回復すること」の核心
人が「回復する」こと、とくに不安や精神の病から回復するとは、いったいどのような出来事なのか。
「治る」という不可思議な経験の意味と構造を求めて、フッサール以来の現象学が培ってきた「経験の構造」の探究を、精神病理学の臨床的知見と交叉させて、あらたな地平を切り拓く試み!
【目次】
序章
第1章 夢と自然治癒
──フロイトの「イルマの注射の夢」
第2章 芥川龍之介の不安
第3章 沈黙と夢
──空想身体の運動
第4章 超越論的テレパシー
──二人で作る創造性
第5章 椅子とうんちの物語
──行為の型と現実を囲い込む状況X
第6章 原ユートピア
──現実の反転について
終章 ジャン・ジュネの歌
──超越論的テレパシーに抗して
結語 空想身体の自由としての治癒
注
用語集
参考文献
索引
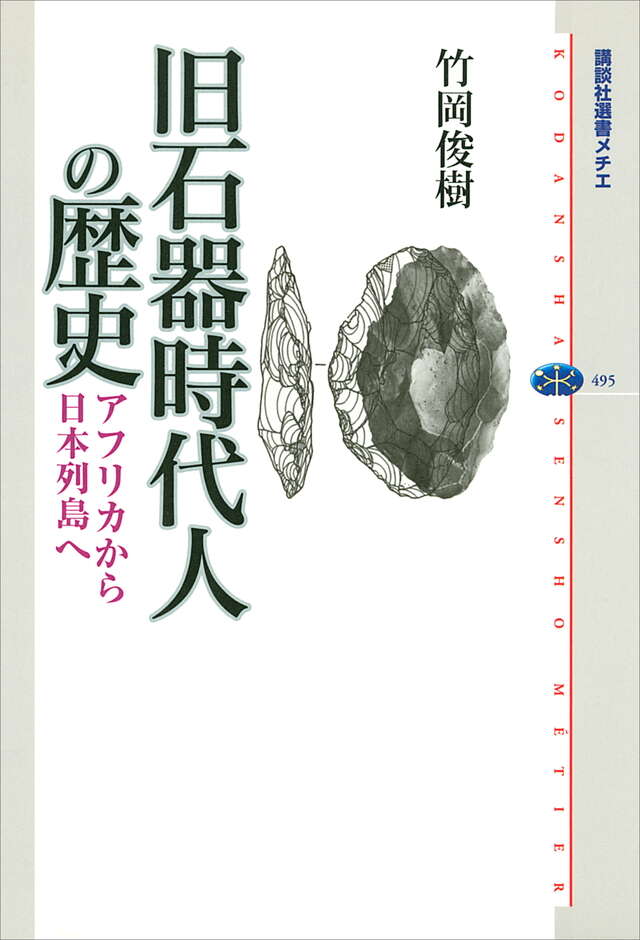
2015.07.24発売
旧石器時代人の歴史 アフリカから日本列島へ
講談社選書メチエ
物言わぬ遺物=石器から旧石器時代の実像に迫る
石器しか資料がない中で、いかにして旧石器時代を知ることができるのか。
「捏造」事件の摘発にも深く関わった石器研究の第一人者が、石器の詳細な分析から、現代人とはまったく異質な旧石器時代人の文化を解明する。
【目次】
はじめに
第一章 私たちは何者か─人類の「進化」と人間の成立
1人類はどのようにして「進化」したのか
2人間はどのようにして成立したのか
第二章 岩宿遺跡の発掘から前期旧石器時代遺跡捏造事件へ
1文化の捉え方と文化の発展の論理の研究史
2前期旧石器時代研究の歴史
第三章 石器研究の方法
1研究方法の形成
2石器製作作業の分析方法
第四章 日本列島における旧石器時代の文化と歴史
1後期旧石器時代以前と後期旧石器時代初期の文化
2新石刃技法をもつ石器群
3国府系文化の変容
4文化の変容についての問題
第五章 遺跡はどのようにして形成されたのか
1環状ブロック群
2茂呂系文化のブロック群
3文化の荷い手はだれか
後記
引用文献
索引
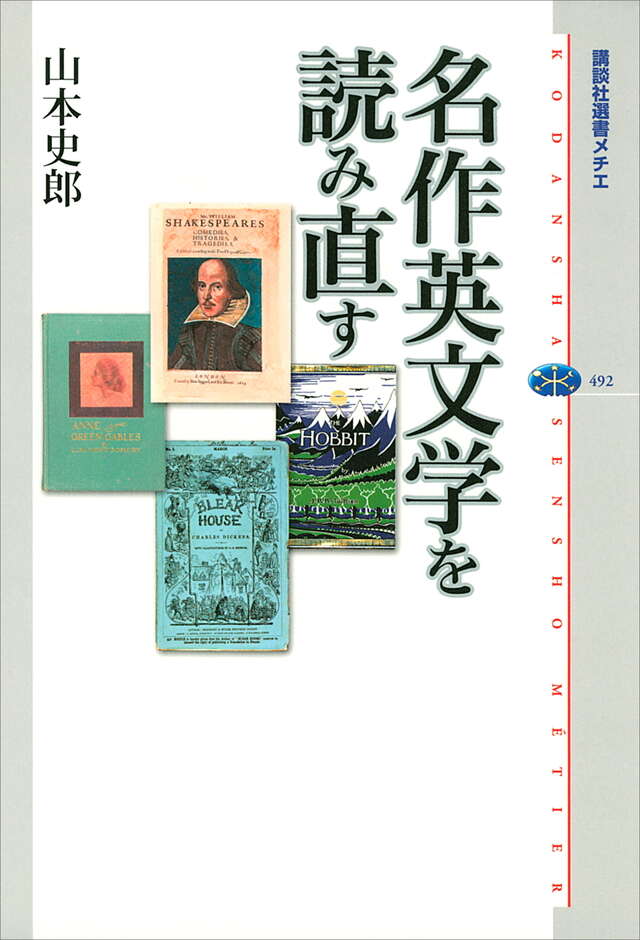
2015.07.24発売
名作英文学を読み直す
講談社選書メチエ
秘密の花園、ロビンソン・クルーソー、アーサー王……
東大教授と一緒に英文学を遊ぼう
『秘密の花園』『赤毛のアン』=少女小説。
『ロビンソン・クルーソー』『ホビット』=冒険小説。
そう思い込んできたみなさん、慣れ親しんできたこうした作品には技アリ、しかけアリ、意外な意味がたくさん隠されているものです。「東大生だって、英文学に通暁しているわけじゃない。恥ずかしながら五十路になってやっと、そんな学生たちの微妙な空気を読み取っておもしろおかしい講義ができるようになった(はず)」とのたまう東大教授が、豊穣な英文学の世界にご案内いたします。
【目次】
はじめに
第1部 物語の中の「もう一つの物語」
第1章 隠されたテクスト
──『秘密の花園』にはどんな花が咲いているのだろう?
第2章 『ロビンソン・クルーソー』とモノモノモノ
──モノの饗宴と小説の誕生
第3章 ほんとうはこんなに笑えるトールキン
──ユーモアのレトリックを発掘する
第4章 『赤毛のアン』現象を読む
──ひそかに抹殺された「物語」
第2部 時代が生み出した「別の物語」
第5章 不倫千年
──アーサー王伝説を造り上げてきた三角形
第6章 つわものたちの夢
──マクベスの主題にもとづく変奏曲
第7章 変貌するテクスト
──『荒涼館』にはなぜ様々な花が咲くのだろう?
注
参考書目
あとがき

2015.07.24発売
交響曲入門
講談社選書メチエ
クラシック音楽の最高峰、交響曲のすべてがわかる!
おすすめディスクガイド付き
交響曲には「構造」と「論理」がある。「交響曲の父」ハイドンからモーツァルト、ベートーヴェンをへてブラームス、ブルックナー、マーラーへ。前代の課題を引きつぎつつ交響曲というジャンルに自らの個性を加えてゆく各作曲家の創意と工夫の跡を丹念にたどりながら名曲の高峰を経巡る、もう一歩深い鑑賞への誘い。
【目次】
目次
まえがき─クラシック音楽の聴き方
第一章 誕生
1 器楽の新しい波
2 交響曲への道
第二章 交響曲の雛形─ハイドン
1 ハイドンの交響曲創作の流れ
2 交響曲のプロトタイプ─交響曲第九五番ハ短調
第三章 交響曲の確立─モーツァルト
1 中期の創作
2 高峰への登攀
3 「深き淵より」─交響曲第四〇番ト短調
4 器楽の王=ジュピター
第四章 ベートーヴェン
1 《エロイカ》の飛躍
2 古典主義芸術の粋 ─交響曲第五番
3 《運命》以後
4 最後の境地 ─《第九交響曲》
第五章 ポスト《第九》─シューベルトとベルリオーズ
1 シンフォニスト、シューベルト
2 《グレート》
3 ベルリオーズの《幻想》
第六章 ロマン派交響曲
1 メンデルスゾーンとシューマン
2 歴史に堪える交響曲 ─ブラームス交響曲第一番
3 ロマン派交響曲
第七章 ブルックナーとマーラー
1 ブルックナー
2 達成点 ─交響曲第八番ハ短調
3 マーラー
4 否定への意志 ─マーラー交響曲第六番イ短調《悲劇的》
5 総合 ─交響曲第九番ニ長調
第八章 国民楽派のシンフォニストたち
1 ドイツ音楽の拡散
2 ドヴォルザーク
3 チャイコフスキー
第九章 二〇世紀と交響曲の未来
註
ディスクガイド
あとがき

2015.07.24発売
マニ教
講談社選書メチエ
キリスト教がもっとも恐れた謎の世界宗教の全貌
世界初の包括的入門書
ゾロアスター・イエス・仏陀の思想を綜合し、古代ローマ帝国から明代中国まで東西両世界に流布しながら今や完全に消失した「第4の世界宗教」。「この世」を悪の創造とし全否定する厭世的かつ魅力的なその思想の全貌を、イラク・イラン、中央アジア、北アフリカ、ヨーロッパ、中国に亘りあまねく紹介する世界初の試み。
【目次】
プロローグ――マーニー・ハイイェーとマーニー教
第1章 マーニー教研究資料の発見史――西域の砂漠から南シナ海沿岸の草庵まで
第2章 マーニー・ハイイェーの生涯――「イエス・キリストの使徒」にして「バビロニアの医師」
第3章 マーニー・ハイイェーの啓示――現世の否定と光の世界への帰還
第4章 マーニー教の完成
第5章 マーニー教教会史1――エーラーン・シャフル
第6章 マーニー教教会史2――ローマ帝国
第7章 マーニー教教会史3――ウンマ・イスラーミーヤ
第8章 マーニー教教会史4――中国

2015.07.24発売
僧兵=祈りと暴力の力
講談社選書メチエ
「霊験」への帰依、異界への畏れ、俗世の「道理」を超えた論理
彼らはなぜ恐れられたか
祈りによって人々に安心と喜びをもたらす、仏法の徒たる僧侶たち。しかし、中世という時代がはじまるにつれて、彼らの中には武器をとって、合戦を引きおこし、人々に恐怖を与えた者たちがあらわれた。暴力と祈りの力をあわせもつ彼らは、いかなる原理のもとに行動したか。比叡山延暦寺を舞台に、多彩な「悪僧」たちが跋扈し、「冥顕の力」をもって世俗権力、社会とわたりあう姿を描き出す!
【目次】
序――祈りと暴力の中世史
第1章 悪僧跋扈の時代
第2章 冥顕の中世
第3章 天台仏法の擁護者・良源
第4章 恠異・飛礫・呪詛
第5章 霊験と帰依
第6章 都鄙を闊歩する大衆・神人
第7章 強訴とはなにか
第8章 善なる大衆の時代へ
結――中世と現代の間