講談社現代新書作品一覧

論証のレトリック
講談社現代新書
説得力、論証力のある言論を展開するには何が必要か? 事柄の利害・善悪、正と不正を見分け、説得に役立つレトリックと、筋道だった議論の仕方を身につける「技術」を教示する。
「言語の技術」の必要性――何かある事柄に関する知恵や知識や技術を備えておりさえすれば、ただちにその事柄についての言論の能力も備わり、容易によく話したり書いたりできるのかというと、かならずしもそうではありません。それぞれの道の専門家が皆、自分の専門の事柄についてよく論じることができるとはかぎらないのを見ても、そのことは明らかでしょう。ある事柄について、全体として明瞭で、論証力、説得力のあるよい言論が展開できるようになるためには、当の事柄に関する知恵や知識や技術を備えるだけでなく、ものの言い方や書き方についての心得や訓練が要るのです。言い換えると、「言論の技術」といったものを何らかの仕方で学んでおく必要があるということです。――本書より

〈心配性〉の心理学
講談社現代新書
誠実で良心的に生きようとするとき陥りがちな心配と不安のたえまない悪循環。心の深層に光を当てながら対処法を模索する。
自分の心の内にのみ――たとえば、「上役や教授など権威ある人と会わなければならない」ことに対して感じる心配を考えてみましょう。この場合、相手の人によって身体が傷つけられるわけではありません。なにか取られるわけでもありません。自分が低く評価されるのではないか、気に入られないのではないかということを心配しているのです。低く評価されても、気に入られなくともなにかを失うわけではないのです。ですから、このときの心配とは、あなたの心の中だけのものなのです。親に気に入られないと不安を感じる無力な幼児の気持ち、これが権威ある人に対して無意識のうちに再現されてしまっただけなのです。――本書より

どこでどう老いるか
講談社現代新書
「超高齢社会」の到来を目前にして、医療体制や介護・福祉の備えは万全か? 老人病院の現状、各種の施設や在宅介護の問題点を探り、老いの未来を展望する。
モデルなき時代――昔、時間がもっとゆるやかに流れていた頃、周囲に普通にみられた老いのモデルはごく自然であたりまえで、怖くも惨めでもなかった。大黒柱として生活を切り回していた働き盛りの頃の暮らしそのままに、少しずつゆっくりと時間が降り積もったというふうで、自分もこうして老いるのかと素直に受け入れられる姿であった。今、長寿時代の老いの様相は一変して、身近に見聞きする老いの姿は辛いものが多く、自分がどこでどう老いるのかが一向にみえてこない。どこでどう老いるか。私たちは自分でそれを決めなければならない。――本書より

アンコ-ル・ワット
講談社現代新書
インドシナ半島の中央に次々と巨大な寺院を完成させたアンコール王朝。建造に費した年月は? 回廊に描かれた物語とは? なぜ密林に埋もれたのか? 遺跡研究の第1人者がカンボジア史を辿りながら東南アジア最大の謎に迫る。
アンコール王朝誕生――アンコール遺跡群は、壮大で、しかも建築装飾の素晴らしい建造物ばかりである……。訪れる人たちは、並はずれて強大な王権が存続し、王はこれらすべての建造物をつくりだした最高責任者であったと想像してきたにちがいない……。だがしかし、実際の歴史をひもといていくと、それはまったく異なる史実が判明するのである。アンコール朝の長い歴史上においては、実力のある王が次々と登位し、その王座を必死に守ろうとして、命を落とすこともあったという史実がわかっている……。新都城の造営の理由は、王の単なる虚栄心からではなく、王たる者が神から授けられた崇高な使命を遂行し、王権の確立を都城造営の形で見せる必要があったからに他ならない。――本書より

女人政治の中世
講談社現代新書
将軍の正室、後家、あるいは生母として、武士階級の女性がどう政治と関わったか。北政所なども含めて描く。
御台所の権限――政子が想定する御台所像は、棟梁が全権を握り、無力な御台所がそのかたわらに寄り添う、というものではなかった。頼朝に知らせるべきことは、御台所にも知る権利がある、というものであった。御家人に対し住屋破却命令が出せるという検断権の掌握とならんで、内々の指示を与える権限をも、政子は主張したのである。文治元年以後、政子は頼朝とともに、正月には栗浜明神に参詣、2月には源頼朝が父義朝の冥福を祈って創建した南御堂の事始に渡御(出席)、10月、御堂供養導師本覚院公顕が鎌倉に下向したのに対面している。このように公的行事、特に神社や寺院への参詣は、頼朝と御台所の2人が出かけ、ついでに主だった御家人の家に立ち寄るなどして、主従関係の絆をより強めておくことが、以後、2人の手でなされているのに注目しておこう。――本書より
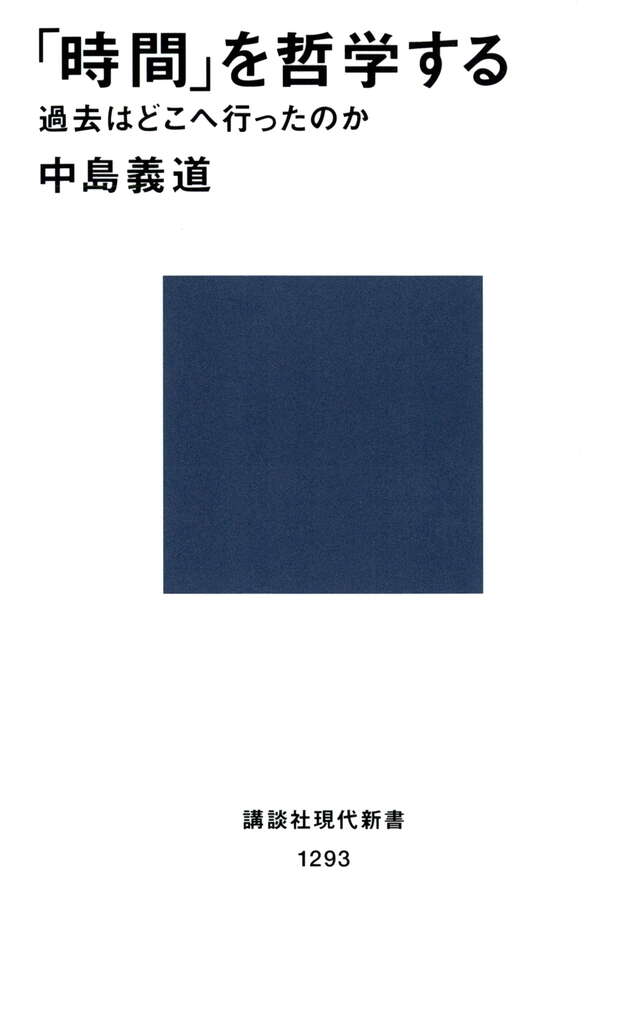
「時間」を哲学する
講談社現代新書
超難問「過去はどこへ行ったのか」を考える。過去体験はどこか空間的な場所に消えたのか。未来は彼方から今ここへと到来するのか。過去―現在―未来という認識の文法を疑い、過去が発生する場を見きわめる。(講談社現代新書)
超難問「過去はどこへ行ったのか」を考える。過去体験はどこか空間的な場所に消えたのか。未来は彼方から今ここへと到来するのか。過去―現在―未来という認識の文法を疑い、過去が発生する場を見きわめる。

日光東照宮の謎
講談社現代新書
絢爛豪華な日光東照宮は徳川家康を「神」と祀る。なぜ日光の地なのか。東照大権現とはいかなる神か。創建にまつわる謎と、彫刻群が伝える壮大なコスモロジーを解読。
江戸のほぼ真北――東照宮を江戸の真北に祀るということは、都城制における大内裏の位置を北端に設けるのと同様の意味があったのではないか。すなわち、久能山において神として再生された東照大権現が、江戸城の真北に遷座されることによって、その神格が「宇宙を主宰する神」と一体化されたことを意味しよう。つまり、東照大権現を「宇宙を主宰する神」へと昇華せしめるために、江戸城の真北に遷座しなければならなかったのである。これこそが、東照宮の日光遷座の最大の理由であったのである。――本書より

イスラム聖者
講談社現代新書
中世のイスラム社会には数多くの聖者が存在した。ある聖者は雨を降らせる奇跡を行ない、またある聖者はひとびとの病を癒した。やがて彼らは民衆を先導し、時の権力と拮抗しうる力を持ちはじめる――これまでは光の当たらなかったイスラムの民衆の生き生きとした素顔を、聖者伝から読む。
イスラム史を読み直す――聖者は治癒や雨乞いという民衆の願いをかなえてやったり、民衆の盾となって権力者に抵抗することもあった。……従来イスラムの歴史研究では、年代記は事実に基づく記録であり、年代記の史料批判による研究が重視されてきた。一方、聖者伝は、ほとんどが架空の記録とされ、歴史資料として用いることは邪道とされた。……ここで私に課せられた仕事は、「聖者伝」という「ネガの画像」に光を当て、イスラム中世に広がっていた豊かな社会と生き生きとしたひとびとの顔を映し出すこと、そしてイスラム史の読み直しを試みることである。――本書より

エイズの生命科学
講談社現代新書
免疫とはどのようなものか? レイロウイルスとは? HIVによる免疫破壊のメカニズムを平易に説き、感染治療の原理と可能性を探る。また、日本の薬害エイズをも視野に入れ、「エイズ」を通じて知る命のサイエンス。
インターロイキン1と発熱・痛みの関係――生体の持つディフェンス・システムにおいて、発熱の役割とはいったい何であろうか?……マクロファージは外敵が侵入したことを知ると、インターロイキン1を放出して、体温を上昇させ、T細胞とB細胞を速く成長させる。これと同時に、マクロファージ自体も「飲み込む」活動が活発になる。すなわち、体温の上昇が免疫細胞を活性化している。……次に、「痛みと生体防御の関係」について述べてみよう。……インターロイキン1が筋肉組織に放出されると、筋肉のタンパク質に分解が起こることが確認された。筋肉が分解すれば、組織が破壊されるから痛みを感じるのだろう。それと同時に、化学的にはタンパク質の中に蓄えられていたエネルギーが放出される。……病気になった時に感じる不快感は、病気と戦うために必要なエネルギーをタンパク質の分解によって得ていることによる。……この痛みがあるから、私たちは免疫と外敵と戦っていることを実感できるのである。こうしてライフサイエンスが発展することによって、少しずつではあるけれども、私たちの身体に関する素朴な疑問が解けていく。――本書より

軽症うつ病
講談社現代新書
人はひとりでにゆううつになる。そのとき? 軽症化しつつ広範に現代人の心にしのびこむ内因性ゆううつを「気分」の障害としてとらえ、共通に見られる心身の諸症状、性格との関係、回復への道筋を明解に説く。(講談社現代新書)
生真面目で心やさしい人々をおそうゆううつ、不安。おっくう感。軽症化しつつふえている理由なき現代的うつ状態への対処法と立ち直りの道筋を明快に説く。
第3の「ゆううつ」――脳に原因があっておこる「ゆううつ」と、心理的な悩みにひきつづきおこる「ゆううつ」……実はもうひとつ、第3の「ゆううつ」があって、話をいささか複雑にするのです。私たちはこの第3を「内因性のゆううつ」と呼んでいます。内因性とは文字どおり「内側からひとりでに」「目覚まし時計が一定の時刻になると鳴るように」おこるという意味です。脳に大きな障害はない。原因となりそうな身体病もない。たとえば、うつ気分をひきおこすことの知られている内分泌疾患もない。逆にまた、そういうことがあれば誰だってゆううつになるであろうような、はっきりした心因的環境的な出来事も先行していない。ひとりでにおこってくるというしかない。そういう場合です。――本書より

英語の世界・米語の世界
講談社現代新書
英語と米語は、本家と分家の関係。源は同じでも、発音やイントネーションから単語の意味や用い方、スペリングにも差異がある。2つの言語の異なる相貌を歴史の中に探る。
微妙な違いはなぜ起こる? ――“ブリティッシュ・イングリッシュ”と“アメリカン・イングリッシュ”の真の差は、人々が考えている以上に大きいのだ。それは、アクセントとか語彙とか、外にはっきりと出てくるものだけではない。眼には見えず、耳にも聞こえず、だがどこかに存在する微妙な違い――どう定義したらよいのかもわからない多くのことが、会話には強く影響するのだ。例えば、どういう速度で話すのか。センテンスとセンテンスの間をどれくらいあけるか。どういう人に対してどの程度丁寧にすればよいか。何かを言おうとするときのごくふつうの話し方は? 会話のテーマとして、話題にしてよいものは何か、よくないものは何か。これらのことは、それぞれの国の中でも、個人差があり、地域差、階級差もある。だが、同時に、イギリスとアメリカの文化の差もかなり強く影響している。……言語の差とは、実はこれらすべてを含んだものなのである。――本書より

写真美術館へようこそ
講談社現代新書
“まなざしの芸術”――写真は、何をどのようにして表現してきたのか。古今東西の名作・快作を集めた“紙の上の美術館”へご案内。その魅力と本質を縦横無尽に語り尽くす、本格的写真入門。
「写真表現とは何か」――そこで当館の展示では、あえてその「写真表現とは何か」という基本的な原理を考えてみようと思うわけです。具体的には写真史のはじまりから現代までほぼ時代順に5つの部屋を設けております。それぞれの部屋がまた3つくらいのパートに分かれている。第1室の「光学・発明・絵画」だったら「写真がなかった頃」、「写真の誕生」、「絵画と写真」、第2室の「鎖・肖像・裸体」は「鏡と“顔”」、「向こう岸のイメージ」、「裸体の饗宴」といった具合です。つまり私のもくろみといたしましては、第1室から第5室までざっと見ていただければ、写真表現に関わるいろいろな問題について、19世紀から現在までの写真の歴史も含めて自然に無理なく理解することができる、そんな展示をめざしています。あまりにも欲ばりな企画で、うまくいくといいのですが……。――本書より

哲学の謎
講談社現代新書
私が死んでも世界は続くだろうか。理由は? 「時が流れる」のは本当か。他人に意識があるとなぜわかる? 実在、知覚行為、自由など哲学の根本問題を専門用語ではなく日常生活レベルで考察する画期的対話篇。(講談社現代新書)
「時間は時速1時間ぐらいで流れている」かな!?
他者・意味・行為・自由など、哲学の根本問題を日常生活レベルの
対話形式で問い直したロングセラー
哲学ってこんなに面白い!
「世に哲学の専門家は少なくない。……そして数多くの論文が生産される。だが、根本的な問題であればあるほど、もとの粗野な姿のまま残されている。もし、学問や職業と無縁の素人たちが、成熟も洗練も無視して無邪気で強靱な思索をそこに投げ掛けたなら、哲学の専門家たちも立ち往生するしかないだろう。必要なのはただ、知的蛮勇なのだ。」(はじめにより)
【目 次】
1 意識・実在・他者
2 記憶と過去
3 時の流れ
4 私的体験
5 経験と知
6 規範の生成
7 意味の在りか
8 行為と意志
9 自由

恋愛の英語
講談社現代新書
出会いから結婚・別離までの関わりを、3組のカップルと、心に残る映画や小説の名シーンの味わい豊かな会話にたずねる。英語表現という窓を通して展望する、男と女の「異文化」コミュニケーション。
empathyを深める会話――あたりさわりのない答えをしたければ、“Just fine.”でよかったのです。しかし、彼女は違った選択をします。……“But it's not what I dreamed about as a girl.”と真情を吐露します。初めて会った人に対してここまで語るのは、なかなかの勇気が要る決断と言えるでしょう。なぜ勇気が要るかと言えば、人間は正直な気持ちをシェアする時、自分をvulnerableな(傷つきやすい)状態に置くことになるからです。一方、そうした気持ちの分から合いをされた場合、相手の側にも危険は生じます。心のこもったこのコミュニケーションのボールをきちんと受け止めることができるかどうかという危険です。危険と言うよりも、機会と言ったほうが良いかもしれません。相手の深い思いを受け止めて、より深い人間関係を築くという機会です。さりげない質問に大してこれだけの深みのある答えをした相手を失望させない反応ができるかどうか、そこに2人のその後の関係はかかっています。――本書より

禁酒法=「酒のない社会」の実験
講談社現代新書
「高貴な理想」とは裏腹に、もぐり酒場の隆盛、密輸・密造業者の暗躍をもたらした禁酒法とは。華やかな「ジャズ・エイジ」を背景に問う。
家での密造――調合することすら面倒と考える人には、ワインに変化する葡萄汁があった。カリフォルニア州の葡萄栽培農家の中には、各地へ葡萄をそのまま「フルーツ」としてではなく、葡萄汁やそれを濃縮したものにして送り出す者がいた。ニューヨークでは、それをさらに固形石鹸のように固めたものまでが販売された。農務省がテストした結果、上手に発酵させて寝かしておくと、葡萄汁は60日間ほどで、12パーセント程度のワインに変化することがわかった。農務省の警告を逆手に取った業者は、アルコール飲料へ変化するから注意するようにという「警告文」を、商品につけて売り上げを伸ばすことができた。――本書より

イギリス王室物語
講談社現代新書
1000年の伝統をもち、今も華麗に輝くイギリス王室。「残虐非道」のヘンリー8世、自信家の処女王エリザベス1世、快楽の王子ジョージ4世など、大英帝国の栄光を築いた強烈な個性たちを描く。
イギリス王室の「伝統」――ウィリアム1世から数えれば約900年、全ヨーロッパに華麗なネットワークをもつに至ったイギリス王室だが、……王室史をひもとくとき驚くのは、歴代の国王にずいぶんいろいろな性格をもった人間、それもいささか破天荒な人物が多いということである。詳しくは本文に譲るけれども、まず目立つのが好色というのか、ともかく色事にかかわる話題を提供してくれる国王が数多い。……ヘンリー8世を筆頭として、現在のチャールズ(たぶんいずれ国王になるだろう)に至るまで、程度の差はあれ色がらみの話はこの王室の伝統という気がする。けれどもこのことと同時にあえてつけ加えておきたいのは、国王あるいは王室の人間が、イギリス最高の貴族としてそれなりの義務も果たしているという点である。たとえば第8章にとりあげる在位わずか1年足らずだったエドワード8世、ウィンザー公だとて、女遊びのあいまに世界各地をとびまわり(あるいはこの逆といったらいいか)、親善訪問によってイギリスという国の宣伝にこれつとめていた。――本書より

戦うハプスブルク家
講談社現代新書
中世的秩序をゆるがし、新たな国家間システムを生み出す契機となった、ハプスブルク家(旧教)・新教諸勢力間の悲惨な長期抗争の推移をたどる。
白山の戦い――晩秋の霧がたちこめていた1620年11月8日、プラハ近郊のわずか標高38メートルの小高い丘、白山で戦闘が起きた。……戦闘は2時間と続かなかった。……文句なくカトリック連合軍の圧勝であった。……注目すべき点は、勝利者フェルディナント2世の明確な意志が余すところなく貫かれたその戦後処理である。このことがやがて全ドイツを、そして全ヨーロッパを以後30年近くにわたって恐ろしい戦争に引きずり込んだのだから。――本書より

捨聖・一遍上人
講談社現代新書
南無阿弥陀仏とただ一度(=一遍)唱えるだけで、極楽に往生すると説いた鎌倉仏教最後の祖師。族縁はすべて捨て去り、おどり念仏で全国をまわり、女人非人をも救済した希代の生涯を描く。
遊行と賦算――一遍は全国を旅した。ただ1人で念仏を勧めることを念仏勧進という。また、この仏法を説いて旅をすることを遊行という。念仏勧進に当たって「南無阿弥陀仏決定往生六十万人」と印刷した大人の人指し指大の紙のお札を配った。これを賦算と言っている。念仏勧進に必要な仏法の所持物以外は一物も持たなかったので、捨聖と言われるようになったのである。こうして、南は九州の大隅から北は奥州江刺に至るまで念仏札を配って歩いた。それは多く下駄ばきの遊行であった。人は胸に吸い込んだ空気を大きく吐き出すと、次はまた空気を吸い込む。一遍は一切を捨てることで、その空となった部分を念仏勧進で満たそうとしたのである。――本書より

ヒトはなぜ子育てに悩むのか
講談社現代新書
「母親語」の力、父親の役割、ことばの発達。赤ちゃん研究の意外な知見から、育児の常識を読みかえる。
母親語という現象――実際に、母親語という現象を頭のかたすみに残して、日常の私たちの会話に耳をすますと、意外なほどいろいろなものが見えてくる。まず乳幼児が学習を成立させるうえで、母親語は大切な機能をはたしている。そもそも「母親語」と命名されたのは、母親による高く抑揚の激しい口調が、子どもにとって重要な意味を持つという事実によっている。けれども母親ばかりが、母親語を語るのではない。父親も子どもに向かって用いる。この「父親語」は母親語とまた、違った作用をするらしい――本書より

「大東亜共栄圏」の思想
講談社現代新書
「侵略」を「解放」と呼んだ「聖戦イデオロギー」を支え、拡めたのは誰か。当時の人々の心性を綿密な資料考証から描く。
「聖戦」のイデオロギー――そもそもこのような問題発言が、なぜ繰り返しなされるのであろうか。もしそれが、戦争中盛んに宣伝された「聖戦」論の一面を率直に表現したもので、しかも当時の国民に広く浸透していた常識に近い見解であったとするならば、問題の根は深く、そして重いとみなければならない。太平洋戦争は、全国民の自主的・積極的な参加・協力を不可欠な前提条件とする総力戦であった。いわゆる上からのファシズム化と総力戦を可能にした社会的要因の1つは、国策に賛同・協力せざるをえないような非常時の社会的風潮の全国的な高まりだったように思われる。――本書より