講談社選書メチエ作品一覧

嗜好品の文化人類学
講談社選書メチエ
栄養にならないものになぜ惹かれるのか
[本書に登場する嗜好品の一例]
韓国のおこげ湯/イタリアのエスプレッソ/タイ、ラオスのキンマ/モンゴルの馬乳酒/メソアメリカのタバコ/ブラジルのガラナ/アンデスのコカ/インドのパーン/カメルーンのコーラ/エチオピアのコーヒー/中国の果物/イエメンのカート/台湾のビンロウ/パプアニュ-ギニアのビール/サモアのカヴァ/コンゴ民主共和国のゾウの脂/マダガスカルのウミガメ食/ネパール・マガール人のブタ/パキスタンのルーフ・アフザ/シベリアのパジミクタ/中国・トン族の便汁
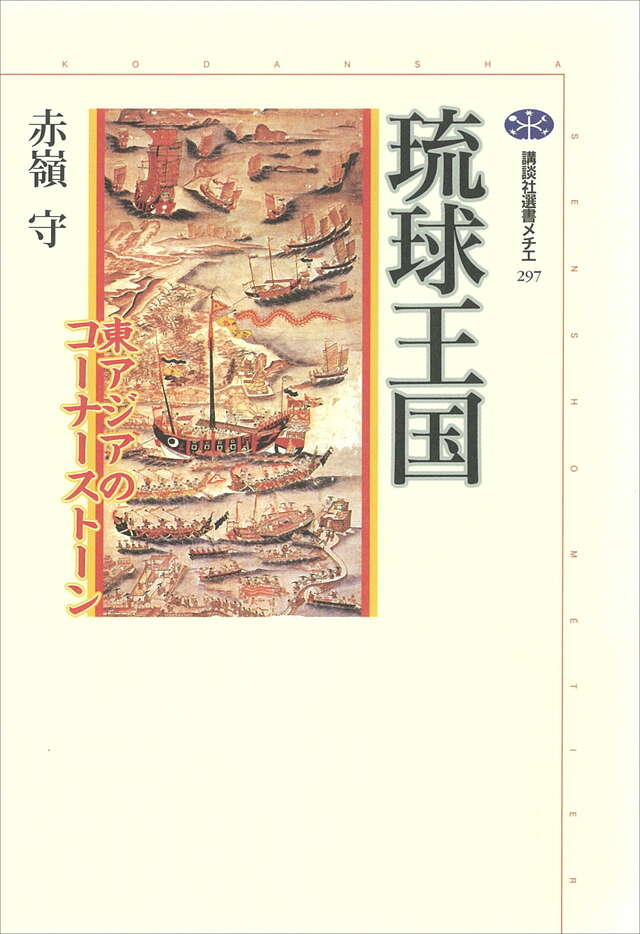
琉球王国
講談社選書メチエ
海の通商王国=琉球。その繁栄の糸口は明の倭寇対策にあった。国家の中枢に食い込み交易の実務を担う華僑たちの実像。「死旅」と呼ばれた中国皇帝への進貢の旅の実際、薩摩支配下での中国・日本「両属」を巧みに使い分けた生き残り政策など、新史料を駆使し新たな琉球像を提示する。
海の通商王国の700年
海の通商王国=琉球。その繁栄の糸口は明の倭寇対策にあった。国家の中枢に食い込み交易の実務を担う華僑たちの実像。「死旅」と呼ばれた中国皇帝への進貢の旅の実際、薩摩支配下での中国・日本「両属」を巧みに使い分けた生き残り政策など、新史料を駆使し新たな琉球像を提示する。

知の教科書 ヘーゲル
講談社選書メチエ
西洋哲学史に起きた大地震
ヘーゲルは1つの切断線である。哲学の歴史的展開を綜合し、完成させることによってギリシア=西洋哲学を終わらせたヘーゲルはまた、現代思想の豊かな源泉ともなった。難解といわれる壮大な体系の見取り図を示す入門書。

「膝栗毛」はなぜ愛されたか 糞味噌な江戸人たち
講談社選書メチエ
現代人は本当の面白さを知らない!
現代人は本当の面白さを知らない! ヤジさんキタさんは江戸っ子ではない? しかも同性愛関係にあった? 艶笑と猥歌に満ちた内容から、このような設定が現代日本人の知識から切り離されてしまった「膝栗毛」。20年にわたって書き継がれ、200年にわたって享受された大ヒット作の「笑いの本質」と「文化現象の構造」に肉迫する。
【目次】
関連地図
はじめに
第一章 『道中膝栗毛』の笑い
1 『道中膝栗毛』理解のための基礎知識
2 『東海道中膝栗毛』の執筆方針
3 嘘と失敗だらけの二人組
4 色気と食い気
5 性的視線と「表裏」の文学
第二章 「膝栗毛物」という文化
1 受容史二〇〇年
2 『道中膝栗毛』のマルチメディア展開
3 『道中膝栗毛』の言語史
4 数々の異本「膝栗毛物」
5 大ヒットの原因
補章 『道中膝栗毛』の出版と作者十返舎一九について
おわりに
注
索引

読むことの力
講談社選書メチエ
本という他者とケンカする愉しみ
<東京大学比較日本文化論テーマ講義>
●「読む」「聴く」そして「時間」/林 望
●装幀としての磁力/毛利一枝
●翻訳者は「作者代理」か「読者代表」か/柴田元幸
●ダイモーンの声を聞く――哲学書を読む/門脇俊介
●<意味の他者>を読む/野矢茂樹
●奇跡物語の「心」/大貫 隆
●中世の遺言が言い残したこと――コンスタンツ市民の遺言を例にして/甚野尚志
●記紀を読むことのリアリティー/神野志隆光
●隠者の読書、あるいは田園の宇宙/齋藤希史
●読むことの苦楽――「美人図」詩とその周囲をめぐって/ロバートキャンベル
●春本のエクリチュアー/浅野秀剛
●パリ写真集――ことばと写真の交響/今橋映子
●詩を読むよろこび/小池昌代×宮本久雄×藤井貞和

関西弁講義
講談社選書メチエ
<独立した言語>を学ぶ
新たな知の営みへ!
関西人は声が大きいのではない。声が高いのである。関西人は関西弁を変えようとしないのではない。変えられないのである――。音韻、文法、語彙。標準語とは異なる独自の体系を持つ関西弁。北大の人気教師がユーモアを交えて綴る、関西弁の教科書。

対称性人類学 カイエ・ソバージュ(5)
講談社選書メチエ
カイエ・ソバージュここに完結 第5巻
新たな知の営みへ!
神話、国家、経済、宗教、そして対称性人類学へ。「圧倒的な非対称」が支配する世界の根源を問う冒険、ここに堂々完結。抑圧された無意識の「自然」は甦るのか?「対称性の論理」が切り開く新たな世界とは?野生の思考としての仏教を媒介に、来たるべき形而上学革命への展望を示す。

江戸の情報力 ウェブ化と知の流通
講談社選書メチエ
手法の革新と知の蓄積
タテ=上意下達の伝達経路にとどまらず、ヨコ=私人同士のネットワークとウェブ化が花開いた時代。情報量の増大のみならず、手法の革新が新しい知のストックを築く。日本人の情報=知の感覚を育んだ江戸の底力を検証。
【目次】
はじめに
第一章 「公」の情報ネットワーク 情報の創出と管理
1 「公的情報」の環境整備
2 「上意下達」と「横並び感覚」
3 「鎖国」による海外情報の占有
第二章 「私」の情報ネットワーク 「公的情報」を補う
1 武士たちのパーソナル・ネットワーク 広がる水平的回路
2 特定領域での情報網 蘭学から国学まで
3 新興勢力の情報網 町人たちのネットワーク
第三章 情報のウエッブ化 新しい情報発信と全国展開
1 不特定多数への情報発信
2 ニーズへの対応 速報性と宣伝力
3 各地での生活情報発信
4 ゆとり情報の創出 モバイルの時代へ
第四章 日本的情報伝達の手法 ウエッブ展開を促したもの
1 「パッケージ」としての歌舞伎
2 感性情報の魅力
3 「語り」コミュニケーション
4 浮世絵の精神
第五章 「知」のインフラを創る 情報のストックと組織力
1 巧みな組織力
2 多様な「スタンダード・モデル」の創出
3 情報のストックと「公」「私」の役割
4 「公」「私」のパワー・バランス
むすびにかえて
参考文献・史料

長城の中国史 中華vs.遊牧六千キロの攻防
講談社選書メチエ
<中華>VS.<遊牧> 2000年の攻防
山を削り谷を埋め、2000年の歳月をかけて築かれた中華世界の防波堤=長城。それは、澎湃と興起する遊牧民対策への最終回答たり得たか。秦の始皇帝から明代まで、長城を巡り展開する壮大な中国史。
【目次】
プロローグ 長城はなぜ作られたか
第1部 秦の始皇帝と長城
第2部 歴代の長城
第3部 明の長城――点から線へ
第4部 明の長城――充実と終焉
エピローグ 長城とは何だったのか

英語にも主語はなかった
講談社選書メチエ
主語の謎――英語は? 日本語は?
日本語に「主語」はない。それどころか、英語における「主語」の概念すら、実は歴史上遅れて発生した特殊なものなのだ。「主語」は普遍性を持たない文法概念なのである!1000年の言語史を遡行して、「天」の言語と「地」の言語を解き明かす、壮大な比較文法論。

中高年健康常識を疑う
講談社選書メチエ
粗食のほうが長生き? 家族との同居が幸せ? すべて高齢者を疎外する誤情報である!8割以上の高齢者が自立し、社会貢献している事実。旧来の保健・社会・栄養常識を塗り替える「老年学」の成果とは。天寿をまっとうし、豊かな死を迎えるために何をすべきか。中高年への福音書。
【目次】
はじめに
序 章 高齢者が社会を支える
第一章 老人の健康常識の嘘
1 食生活と栄養
2 やせ信仰の軌跡
3 血中コレステロールへの錯誤の軌跡
第二章 孤独死する老人は英雄だ
1 高齢者差別(エイジズム)
2 直角型の老化と高齢者の能力
3 高齢者の能力の実態
4 孤独死する老人は英雄である
第三章 世代間信頼と相互扶助
1 孝養意識の国際比較
2 戦後のわが国の世代間問題
3 世代間の社会・経済的関係
4 高齢者の若者世代へのサポート
5 高齢者の相互扶助
6 適切なサポート、不適切なサポート
7 情は他人のためならず
第四章 天寿をまっとうするには
1 すべての人が不幸死するストーリー
2 沖縄と百歳長寿者にみた救い
3 終末期は長いか短いか
4 最終臥床期間
5 死生観をめぐる問題
終 章 豊かな死にむけて
引用参考文献
あとがき
索引

文明史のなかの明治憲法
講談社選書メチエ
<国家のかたち>はこうして描かれた
「噫憲法よ汝已に生まれたり」国の内外で識者から迎え入れられた明治憲法。ウエスタンインパクトとナショナリズムの19世紀、木戸、大久保、伊藤、山県らが西洋体験をもとに描いた<この国のかたち>とは? 日本型立憲国家が誕生するまでのドラマを描く。

阿弥陀聖 空也 念仏を始めた平安僧
講談社選書メチエ
一たびも南無阿弥陀仏という人の蓮のうえにのぼらぬはなし
いかなる凡夫愚人も、ただ「南無阿弥陀仏」と唱えるだけで極楽往生で生きる……法然の浄土宗より200年の昔、ただひとり市中に遊行し、「一念往生」の思想を実践した空也。「捨ててこそ」の一念に貫かれた思想と行動、その本質とは。浄土教の歴史を塗り変える、本格的「空也」伝。
【目次】
まえがき
一、念仏の祖師の開いた安心の道
1 空也の実像を求めて
2 阿弥陀聖の登場
3 あたたかい思想
4 捨てて生きる
二、謎の出生と遍歴修行
1 空也の名をどう読むか
2 謎の出生と生育
3 少壮の日の遍歴
4 剃髪出家の謎
5 一切経を読む
6 孤島・湯島観音の祈り
7 奥羽巡錫の謎
8 山中修行
三、阿弥陀聖の念仏唱導
1 市聖
2 卒塔婆の歌
3 神泉苑の病女
4 南都興福寺
5 一同の念仏
四、東山道場の仏事
1 比叡山の大乗戒
2 十一面観音像を祀る
3 金字大般若教書写供養
4 西光寺の草創
5 慈悲行
6 閻魔への書状
五、入滅とその後
1 入滅往生
2 金鼓と錫杖
3 六波羅蜜寺と空也の墓の謎
六、心に所縁なし 空也念仏の風光とその思想
1 発心求道
2 市中はこれ道場
3? 捨ててこそ
4 空と慈悲の念仏
5 結び
略年譜
資料『空也上人の為に金字大般若経を供養する願文』(原漢文の訓み下しと略註)
あとがき
索引

安倍晴明の一千年 「晴明現象」を読む
講談社選書メチエ
老人? 狐の子? 美貌の貴公子?
1000年にわたる変貌の軌跡
わずかな史実から、いかにしてスーパーヒーローは生まれたか。
『今昔物語集』の説話から説経節の「狐の子伝説」まで、また歌舞伎から現代の伝奇小説・マンガの美貌の貴公子まで、刻々と変貌する「晴明現象」に託された人々の心性を探る。
【目次】
少し長いプロローグ 「せーめーさん」詣
第1章 それは『帝都物語』から始まった
第2章 院政期における「晴明現象」
第3章 近世初期の晴明――狐の母の物語
第4章 平安京は「四神相応の地」か
第5章 時代のなかの晴明
第6章 晴明の「敵役」たち
第7章 近代・現代文学における晴明イメージの変転
エピローグ
あとがき
参考文献
索引

皇后の近代
講談社選書メチエ
近代化への激動の中、皇后の果たした役割とは? 皇后美子(はるこ)・節子(さだこ)・良子(ながこ)、明治から三代の物語。聡明で学究肌、維新後の宮中改革に積極的だった美子皇后、病弱な大正天皇を補佐し、神ながらの道に邁進した節子皇后、春日のごとき良子皇后、それぞれの足跡を追う。
【目次】
はじめに
第一章 近代皇后の誕生
1 金剛石もみかすは
2 一条美子の入内
3 宮中改革
第二章 皇后の仕事
1 内廷夜話と金曜陪食
2 皇后、国民の前に姿を見せる
3 皇太子嘉仁の誕生
第三章 宮中と西欧化の進展
1 天皇と皇后の女性観
2 皇室外交のかなめとして
3 洋装化する皇后
4 憲法発布と大婚二十五周年
第四章 世代交代のきざし
1 名宮嘉仁妃の選定と東宮結婚
2 美子皇后伝説
3 「婦人の社会的進出」
第五章 寄り添う皇后 節子皇后
1 明治の先代とは異なる二人
2 天皇の病状発表へ 「健康」という価値
3 慈善恩賞の府としての天皇制
4 母子対立
第六章 神ながらの道に邁進する節子皇后
1 筧克彦の進講
2 『神ながらの道』の世界
3 宮中とキリスト教
4 プロパガンダとしての「救癩」事業
第七章 イデオロギーとしての母性
1 天皇裕仁と良子皇后
2 動員される皇后たち
3 総動員体制
4 「人間宣言」後
あとがき
註
主要人名索引

知の教科書 批評理論
講談社選書メチエ
楽しい「知」の世界へようこそ――
批評理論を知れば<読むこと>がこんなにも面白くなる
具体的なテクストから予期しない、おもしろい解釈が生まれる――。
読者反応論からニュー・ヒストリシズムまで、<読む>という行為を追究した批評理論の各々の魅力を、実践を通してわかりやすく紹介。文科系学生必携の一冊。

倭国の謎
講談社選書メチエ
中国史書に現われる「倭王」とは何か。奴国王はじめ、紀元前の統治者はいつ邪馬台国にとって替わられ、さらにはいつ皇室に敗れたのか。皇室の「神話」から排除された神々が語る「倭国」の真実。
【目次】
はじめに
第一章 倭国はどうして樹立されたか
1 倭国の出現とその意味
2 最古の氏族=アヅミ氏の国造り
第二章 神々と邪馬台国
1 弥生の大国・出雲
2 出雲古族の国々
3 大己貴が大物主となったわけ
4 三輪山・大物主は邪馬台国の山・神
5 “生ける治癒神” 卑弥呼の秘密
6 治癒神からタタリ神へ
第三章 初期九天皇は実在か架空か
1 九天皇非実在論を検討する
2 初期九天皇は全員実在した
3 初期皇室と「日向」
第四章 皇室の真正系図と記紀神話
1 皇室の系図を書き直す
2 原初の皇室の姿
第五章 邪馬台国から皇室へ
1 『古事記』の崩年干支
2 皇室の東遷・物部氏の東遷
3 尾張氏の東遷・天若日子族の滅亡
4 二回あった出雲の国譲り
5 邪馬台国時代の皇室
6 天日槍の渡来と服属
7 二人の「ハツクニシラス天皇」とは
第六章 倭王神功皇后と“倭の七王”
1 神功の朝鮮政策と七支刀
2 『高句麗広開土王碑文』の解説
3 稲荷山鉄剣銘文はどう読むか
4 “倭の七王”論
あとがき
注
索引

謎の哲学者 ピュタゴラス
講談社選書メチエ
奇行の人が発見し、教団が伝えたものとは?
三平方定理の発見者とされるピュタゴラス。数々の奇行が伝えられる哲学者は、イタリア半島南端に秘密の教団を主宰し、「数は万物の原理である」ことを看破した。プラトン・アリストテレスに刺激を与え、哲学の地下水脈となった謎の思考に迫る。
【目次】
第一章 ギリシャでいちばんユニークだった哲学者
1 古代ギリシャの哲学者群
2 エンペドクレスの活躍
3 エンペドクレスが手本としたピュタゴラス
第二章 同時代人の見たピュタゴラス
1 ピュタゴラスと「ピュタゴラスの定理」
2 同時代人の証言
3 証言から見えてくるピュタゴラス像
第三章 ピュタゴラスをソクラテスに語らせるプラトン
1 プラトンの描くソクラテスの変節
2 ピュタゴラス的言葉を使って語るソクラテス
3 親代わりのソクラテス
第四章 アリストテレスが伝えた奇行と奇妙な戒律
1 アリストテレスとピュタゴラス
2 プラトン説に反論するアリストテレス
3 アリストテレスのピュタゴラス理解
第五章 思考の地下水脈となったピュタゴラス
1 プラトンからプロティノスへ
2 プロティノスの魂論
3 ネオ・プラトン派とピュタゴラス
ピュタゴラス関連史
註
参考文献
索引

知の教科書 ニーチェ
講談社選書メチエ
哲学史の十字路に佇む孤独な怪獣
誤解され続けてきた哲学者ニーチェ。
病気に苦しむ哲学者の健康法とは、発狂後に描かれたただ1枚のスケッチが告げるものとは、思想誕生の秘密とは――。喜劇的で少し哀しい生涯を辿りながら、そのラディカルな思想の全貌を明らかにする。
〈本書の内容〉
●プロローグ――新しき海へ
●ニーチェの生涯と思想
●ニーチェのキーワード――教養俗物/ニヒリズム/ディオニュソス的なもの
●三次元で読むニーチェ――ニーチェ百景/アリアドネと2つの三角形/敵たちよ、敵などいないのだ
●著作解題――『人間的な、あまりに人間的な』/七つの序文/『道徳の系譜学』
●エピローグ――新しき海から
●知の道具箱――ブックガイド/ニーチェの軌跡

賢治を探せ
講談社選書メチエ
賢治の<すごさ>はどこにあるのか?
<文学者>賢治の真価を問う「仁義ある宮澤賢治論」
日本文学史上最もラディカルな作家=宮沢賢治。賢治が終生追い求めた「まことのことば」とは何だったのか。初期短歌から「銀河鉄道の夜」まで主要作品を精読し、文学の根源へと肉迫する賢治をスリリングに描く!
【目次】
序章 宮沢賢治とは誰か 「仁義ある」賢治論のために
1 仁義なき賢治論
2 文学者賢治
第一章 表現のはじまり 短歌から『春と修羅』へ
1 表現のアポリア 初期短歌
2 「わるひのき」から修羅へ
3 言葉を奪われた者 修羅誕生
第二章 まことのことばを求めて
1 ことばとウソ 「鹿踊りのはじまり」
2 なぜウソは生まれるのか
3 言葉がはじまるとき 「なめとこ山の熊」
第三章 貨幣と言葉
1 狐けんと貨幣
2 出版資本主義下の文学 賢治の生きた時代
3 物々交換と貨幣による交換
第四章 三人称
1 差異と反復 「竜と詩人」
2 介入する第三者
3 差異はなぜ生まれるのか
4 転機=「青森挽歌」
第五章 銀河鉄道の彼方へ
1 ユートピアとしての銀河鉄道
2 とまどうジョバンニ
3 働くジョバンニ
4 ジョバンニとは誰か
終章 「作家賢治」の旅立ち
註
参考文献
初出一覧
あとがき
索引